6
夜が沈み、青ずんだ雨の夜明けを見届けながら
ティファレトは1人で、ガラスの檻の中の人形のように佇んでいた。
脆くも分厚いガラス越しに、動き回る管理人たちに視線を向ける。
雨は止まない。
長らく人の通わなかったあの通路に人が集まっているのを見ると、
晴らしどころない悲しさに包まれる。
もう自分も、随分と昔に孤独になったはずなのに。
ここにいるセフィラ達は、みんなそうだ。
何人揃っても孤独だった。
ただどこかでともに、
孤独を共有していることだけが救いだった。
それだけだった。
「……、……」
音のない声で呟く。
――――――――――――――――――
アルジャーノンは、未だ長椅子の上で、膝に乗せたままのPCのキーボードを弾いていた。
横には少し俯き気味の皿面がいる。
顔が見えないが、眠っているのかもしれなかった。
259は、給湯室からコーヒーを持ってくると、
静かにアルジャーノンの前に置いた。
「アルジャーノン、お疲れ様です。どうぞ」
「ああ、ありがと…」
「無理しすぎず、休める時に休んでください」
259が心配しながら、そっと優しく微笑む。
アルジャーノンはその言葉に頷きながらも、視線はPCから離れない。
「うん…でも、俺もできるだけのことはしておきたいんだ。これは専門外だけど…」
"専門外"と言いつつも、アルジャーノンはまるで慣れているかのような行動力だった。
なんとか防護隔壁のシステム復旧の目処が立った今、
別室のレストと巡回中のルシフェニア、三人共同で遠隔から作業をしている。
その片手間に、アルジャーノンはこの施設の正体についてデータを照らし合わせていた。
消えてしまったはずの、この施設の履歴を辿る。
オフラインでも閲覧可能な施設の記録共有庫を見たところ、
残念なことに同じ状況で記録が抹消されている施設は500以上あり、
この中から絞り出してデータを吸い出すのは、容易ではないことが分かった所だ。
「そうですね…」
259はそう呟くと、持ってきていた毛布を皿面の肩にそっとかけた。
反応がない所、本当に眠ってしまっているようだ。
日付が変わって随分時間も経つ。
集結した管理人たちも、施設内の探索に出向いた者と、休息に入った者といる。
訓練に差し支えないよう、259は極力サポートに回りに目をくばっていた。

―――――――――…六日目。
かなり遅くまで暗躍していた管理人達は、朝を迎えても、緊張したまま休憩時間を過ごしていた。
当然思うように休めていない。
この状況下において、雨の音はリラックスを促すどころか、
まともに休めずに溜まった疲労や緊迫した不安を更に煽る。
「ふわぁ…」
皿面はお面越しにあくびをしたらしかった。
重い目蓋を開けた先には、彼を心配して相席についた259がいる。
259は皿面と目が合うと、眼差しを察してそっといつものように微笑んで見せた。
柔和ではあるが、初日の彼の微笑みと少し違う点をあげるとするのならば、ほんの少しだけ
“管理人たち危険に曝すわけにはいかない”といった緊張感をどことなく漂わせている所だろうか。
他の管理人たちも、確実に疲労が蓄積している表情をしているが、顔にでない管理人たちも多い。
レストもその内の一人だ。
「あ…レストくんおはよう…」
「レスト、おはようございます。昨日はお疲れさまでした」
レストは、彼らの眩い宝石の輝きを見つけると、その挨拶に頷いて応えながら、歩み寄ってきた。
静かなヒールの音がカフェテリアの音楽に紛れて近付いてくる。思えば彼女がここに立ち寄ることは珍しい。
彼女は、彼らのドリンクの入ったソーサーに、静かに何かを添え置いた。
極自然な、何かの差し入れをするように、さりげない動きだった。
お菓子の差し入れかと見まごうような、しかし一見クールなモノクロな包みに入ったそれは、
もちろん差し入れなどではなさそうだ。
睡眠不足の目を凝らしてよく見ると、それは小さなカードを入れたらしい包みだった。
驚いた皿面と259は、一度顔を見合わせる。
「…?
これはなあに…?」
首を傾げる皿面に、しばらく周りを警戒してから、彼女は口を開いた。
「カモフラージュだ。
下層部にあった謎の扉のキー。ティファレトの手紙が真実ならこれで開くはずだ。
発行は3枚までが限度だ。これはお前たち二人に渡しておく」
「…!!」「……?!」
あまりにも唐突だったので、二人はその場で言葉を失う。
「ルシが見張ってはいるが、どこで彼奴らに情報が洩れるか分からん。
このキーは周りにも見せないようにして、所持しておけ」
今朝に託してきたあたり、レストもどうやら昨夜かなり遅くまで作業をしていたらしいが、それにも関わらず、彼女の顔色はひとつも変わらないまま、凛としている。
(ティファレトの手紙…)
昨晩のこと、ティファレトが紙くずのようなメモを落としていったことを思い返す。
内容の全文を知っているのはルシフェニアとレストだけだ。
ただ、この訓練施設が異常であるということを告白した内容であるらしいことは少しだけ聞いている。
「…下層の謎の扉、そこには何があるんですか?」
259が極めて小さい声で尋ねる。
カードは未だソーサーの上だ。
しかし彼女はそれには答えないで目で促す。
「………時を待て」
しばらくの沈黙の後、彼女はそれだけ告げると、颯爽と二人の席を後にした。
直後、彼らはカードキーをポケットにしまうと、緊張からぎこちない動きを見せながらも、自然に振る舞った。
*
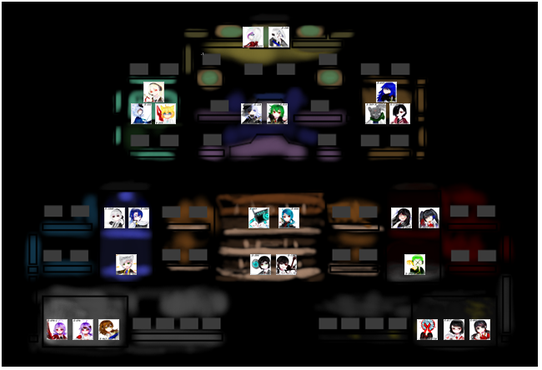
『アラートの部屋数、並!
クリフォトカウンターも異常無っしん!』
333はモニターを見上げ、リズミカルに呟く。
本日福祉チームに配属されている彼だが、これまでのことを踏まえて、順序よく施設全体を見渡している。
無論、本来の管理人の仕事だ。
「レストさんとルシフェニアさんが見てくれたんだから…大丈夫」
384は自分に言い聞かせるように呟く。
口元は震えている。
「ダンナイダンナイー。
深呼吸でもしとくか?」
「う…うん」
にやにやと茶化すように726に言われたが、促されるまま384は深呼吸をしてみた。
ついた呼吸の先、抜けきらない緊張が、芯を残して揺れている。
本日の異常が何も見られないところを見て
一抹の不安とでもいうべきか、
何かおかしな胸騒ぎを覚えていた。
「やっと6日目というか、もう6日というか…
今日と明日は何もないまま無事に終わってくれるとありがたいんだけどな…」
アルジャーノンが背伸びをしながら苦笑混じりに呟いた。
髭があくびにそよぐ。
彼は寝不足にも関わらず、安全に事を終わらせたい一心と、
施設の謎に対する歯がゆさに、無理をしてくれている。
昨晩も時折、私物のケース…ホドの写真に目を向けては思い悩んだ顔をしていた。
「そうだね。
…でもアルジャーノンくんは、できるだけ温存して過ごしてもらっててもいいかい?」
ウィリーがアルジャーノンにそう言うので、彼は一瞬ぎょっとした。
「ああ、なんとなくなんだけどね」
途中でそう付け加えられたが、ウィリーの勘に今まで世話になった分、
これから何か起こり得るのだということに身構えるしかなかった。
「ウィリーはすごいよな!
おかげでここの父様とも色々話せた!
ここにいる間あとどれくらい会いにいけるかな」
「もうすぐここの父様とさよならなのです…」
満足げに微笑むブランダーの背後で、寂しそうにシャオは呟いた。
その肩に、ブランダーは、ぐっと身を寄せて笑って見せる。
「またここに遊びに来こようぜ。
それになんていっても、僕たちにも帰るところがあるだろ?」
ブランダーの力強くもきょうだいを気遣う腕に、大きく揺れたシャオは、虚空の瞳をそっと伏せて、静かに頷いた。
マルクトの空っぽなアナウンスが響いてくるのを尻目に、
一同はお互いを励まし合ったり、元気付けあったりした。
*
それはまだ、
白昼を終えたあたりのことだった。
訓練は順調に運び、正常な緊張感に満ちていた。
皿面が懲戒チームのメインルームでどきどきしながら待機していると、ひとりでに扉が開いた。
またか、と扉の方を振り向くと、
案の定、ひらひら入ってきたのは罰鳥だ。
「わっ!つつかないで…!」
彼は即座に頭を庇い、縮こまる。
無論、反射による報復が命取りだからだ。
脱走に気付くのが遅れて、他の部屋に避難しそびれてしまったため、姿勢を低くしてとにかくひたすら祈る。
しかし、しばらくして皿面は、罰鳥の飛行パターンがいつもと異なっていることに気付いた。
(あ、あれぇ…?)
罰鳥は、高度を変える様子がないまま、高い位置を羽ばたき続け、やがて彼の頭上も通り過ぎて、出ていってしまった。
白く小さな姿は、どこか向かうべき場所があるかのようにも見える。
一瞬きょとん、とした皿面だったが、我に帰ると、すぐにセピラのモニターを見た。
落ち着いて罰鳥の進行方向を確認する。
震える指が、やがて罰鳥をとらえると、モニターの熱がやけに熱く感じられた。
(…も、もしかして……)
皿面は息を呑んだ。
とうとう来てしまったのだ。
*
ソーニャが作業を終えて、セピラに戻ろうとすると、背後から気配がした。
その途端、今いる廊下のライトが弱々しく点滅し、やがて消えた。
彼女は咄嗟に壁に背をつけて銃を握る。不慣れながらの対処法だ。 暗闇の中、非常用電源の頼りない小さなライトが等間隔で確認できる。
そして、それらと全く違う、眩しい火の灯りが遠くで揺れている。
何かがのそのそと、大きな巨体を揺らしながらゆっくりと、その収容室の小さな扉から這い出してきた。
「大鳥さん…」
脱走を知らせる赤いランプを尻目に、それとは全く異質の眩しい目が、いくつも浮かんでいる。
天井につきそうなくらいの巨体をゆっくり弾ませながら、無数の目が近付いてくる。
暗い廊下、眩しいランタンの灯りが場違いにあたたかい。
幸いにも、大鳥の脇と廊下の壁には隙間があり、くぐり抜ければ背後を狙うこともできる。
しかし、それができなかった。
自分はもう魅了状態にあるのかもしれないと、疑うくらいに。
「……」
その無数の目が、いずれも自分を見ていないことに気付いたのは、大鳥が真横に来てからだった。
やがて、大鳥はソーニャとすれ違う位置をとっくの間に通りすぎており、アブノーマリティが違うエリアに移動すると電気の灯りが戻った。
「……?」
彼女は一呼吸置くと、すぐに施設内に連絡を繋いだ。
「"情報チーム、ソーニャ。大鳥さんが脱走しています。
どこか行くところがあるように見えたのですけれど……"」
「"こ、こちら懲戒チーム…罰鳥はすでに脱走してるよぉ…!
ね、ねぇ、…もしかしたら…"」
皿面の震えた声が重なる。
とても怯えていることが伝わってくる。
無論、怯えているのは、彼だけではない。
施設内で緊張が高まる中、これが先日までの異常とは無関係の、正常な危機だということに、皮肉にも納得した。
あたりは少しずつ波立って行くように騒がしくなり始める。
不安が募りつつある中、333の通達で確信と恐怖に変わった。
『こちらは333だよ!中央本部チームのセピラ、エリア3に黒い森げーと出現を確認!かんりにんは先に行くねー!』
モニターの中には、すでに中央本部の真ん中で、ただひたすら333が黒々としたゲートに炎の羽を注ぎ込んでいる姿があった。
いち早く発見して福祉チームから走ってきてくれたらしい。
眩しく燃える名誉の羽は、それでもゲートの奥まで照らすことはできないまま、別の世界に繋がっているような、暗闇を通過していく。
『黒い森の入り口』。
これが出現しているということは、すでにアブノーマリティ、罰鳥、大鳥、審判鳥の三体が脱走しているということを示していた。
384と726が既に加勢してゲートの鎮圧を試みている。
「来ないで…!来ないで…!」
384の、喉の奥で止めようとしていた不安が、苦し紛れに溢れた。
星の音も煌めきながらゲートを砲撃したが、名誉の羽と同じように、そこには光を吸収する闇が口を開けているだけだった。
「了解」「OK。すぐ行く」
333の呼び掛けに、続々と他のルームに配属された管理人が了解し、駆け付ける。
中央本部の三階は、あっという間に管理人達で埋め尽くされた。
*
先ほどまで作業をしていたジョンは、少し出遅れたが速やかにエレベーターに向かった。
終末鳥だけは、勘弁してほしいところだ。
ゲートの鎮圧は、ほぼ不可能と言われている。
人が集中している中、自分の魔弾がどれだけ安全にコントロールできるか分からないが、全員が全力で阻止しなければ、不可能は不可能のままだ。
いつも通りのコントロールで上手くいくはずだ。
彼は、溜め息に近い深呼吸をする。
後ろからもう一人、一緒に来た人影が同じ方向へ向かっている。
ジョンはちゃんと、"彼が乗ってから"エレベーターで移動した。
――――よかった。出遅れてしまったが、すぐに一緒にかけつけようではないか。
「終末が来るとか。なんとかがんばりましょう」
ジョンが呼び掛ける。
『………………』
――――ええ、そのつもりです。
返事はなかった。しかし、彼にはそんな言葉が返された気がしたのである。
「さぁ、行きま――――」
エレベーターと同時に、ジョンの呼吸が止まった。
振り返ってしまったのである。
彼がエレベーターで同室していたのは。
管理人の一人などではなく、
審判鳥そのものだったのだ。
審判鳥がエレベーターを降りるより先に、ジョンは意識が遠退くのを感じた。

*
「このままじゃ間に合わない…!!」
384の小さな叫び声を聞きながらも、726はギリギリまでゲートを鎌で斬りつけていた。
先ほど入っていった罰鳥、大鳥。
その度にゲートはより完全なかたちになって、修復されていく。
すぐそこまで審判鳥が迫ってきていた。
「是、来るぞ…。全員一度通路へ退け…!!」
キャロルが周りに呼び掛ける。
全員で鎮圧を試みたが、大鳥が入る直前も、罰鳥が入る直前も、あと少しのところで全く傷が入らなくなっていた。
明らかに不自然な現象が起こっている中、それでもゲートの破壊を試みる管理人たちは、なかなか退避せずに張り付いている。
726は、384に腕を引かれなければ攻撃を止めなかったし、1006も、キャロルに担がれるまで攻撃を止めなかった。
ミカンは、本体に腕を引かれてやっと我に返って退いた。
不可能と分かったところで、退く気はなかった521と810が、817に呼び掛けられてやむをえず、バックステップで身を引く。

*
――――怪物の叫びともに、終末鳥は現れた。
細い首がもたげる赤く痛々しい頭、
金色の無数の目が散りばめられた大きな翼、
牙を伴って腹に大きく開いた赤い口。
赤く濡れた開眼、金色の光を湛え、包帯の巻かれた爪先まで血がにじんでいる。
ゆっくり床を引っ掻く音が響き渡り、巨体は一瞬にして空気を支配した。
*
「"怪物"、か…」
中央本部、隣の通路に急いで逃げ込んだ一同が呼吸を整える中、サイレンは小さく呟いた。
その呼び名を哀れむような、悲しさを含んだ声だった。
途端、ものすごい地響きが走った。
収容施設内は地下とは思えないほど大きく揺れ、管理人たちはよろける。
辺りの灯りは、揺れとともに、不安定に点滅し、至る所で小さな悲鳴が上がる。
「みっ、皆さん、落ち着いて下さい!
静かなオーケストラの時のように、再び攻撃の色属性で隊列を組みましょう…!」
384は周りを宥めるように緊張にひきつった声を発した。
彼がいちばん怯えているのではないかと思うくらい、震えている。
気を抜いたら彼自身が気絶してしまいそうな中、必死に冷静を保とうとしているのだ。
身を寄せ合うようようにした管理人の一同から、259がそっと乗り出す。
「そうです。落ち着いて行動すれば、安全に鎮圧は完了します!
私は黄昏の闇が広がりきってしまう前に、
モニターから卵の位置を確認してきますね。」
「ま、まって259くん…!
モニター、見に戻って大丈夫?」
怯えている皿面の言葉に、259は安心させようと笑顔で応えた。
「259は平気ですよ。少しだけ、待っていてくださいね」
彼は隊列を組み始めた管理人たちを背後に、ひとり、中央本部セピラに戻る。
各セピラルームに備え付けられたモニターは、確かに便利だが、セピラからでないと確認できない難点がある。
終末鳥はテレポートしたのか、すでにそこにはいなかった。
血に濡れた床と深々と刻まれた爪痕だけが、その強烈さを物語っている。
彼はそっと身を進めると、モニターを覗き込む。
「…これは……」
―――砂嵐。
あろうことか、画面が確認できず、施設内の様子をうかがうことができなくなっていた。
さきほどまで見渡すことができたというのに、何も見えない。
彼は、息を呑んでモニターから通達ボタンを押してみる。
「みなさん、聞こえますか…!」
音が反響してこない。
「…!」
再び、床が大きく揺れ、灯りは不安定に点滅する。
彼は揺れが未だ収まっていない中、姿勢を崩すとなくすぐに待機場所の通路に走った。
259が戻ってきたとき、すでに隊列は三小隊にわけられて先導者を決め、彼の加勢を待つだけだった。
『大きな目』の鎮圧に向かう、白と青装備の管理人。
『小さなくちばし』の鎮圧に向かう、黒と青装備の管理人。
『長い腕』には、赤装備の管理人が向かい、他の卵の鎮圧が完了してから合流すると言った流れだった。
「259さんっ…!ど、どうでしたか?」
戻ってきた259に384は震える声で駆け寄る。
表情は今にも不安で倒れそうだ。
259は少し上がった息を整え、緊張した面持ちで口を開いた。
「…皆さん、落ち着いて聞いてください。
―――……中央本部のモニター、壊れています。」
「なんだって…!?」
思いもよらない言葉に、アルジャーノンが耳を疑って叫ぶ。
ここにいる全員が驚愕している。
モニターが破損とあっては、卵の位置も、クリフォトを暴走させられて脱走したアブノーマリティも確認できない。
「モニターだけじゃありません。通達機能も壊れています。
中央本部だけだと良いのですが、他のルームに確認に行かなければなんとも言えません…。」
一同は再びざわつき始め、抑えようのない緊張と不安が浮かび始める。
「探し回ってぶっ叩けばいいだけだろうが」
1006が、周りの動揺に苛立ちをあらわにした、その時だった。
「一人足りない…?
皆さん、ジョンさんがいらっしゃいませんわ…!」
あたりの違和感に見渡していたソーニャが叫んだ。
彼女は先ほどまで、白の隊列に加わろうか、黒の隊列に加わろうか迷いながら、人数を確認しに辺りを見渡していた。
彼女の言葉に、アルジャーノンが並んで辺りを見渡す。
「確かに居ない…
さ、最後、ジョン君を見たやつはいるかい?」
「僕が同じコントロールチームだった。
終末鳥が来る直前、彼が作業に行ってたのは知ってるけど」
521が静かに首を横に振るだけだった。
「ジョンくん…一体どこに…」
皿面が震えながら小さく呟く。
モニターが確認できない以上、他の管理人達の居場所も安否も特定することができない。
「と、とにかく、ジョンくん捜索と終末鳥ちゃんの鎮圧よ…!」
混乱の空気がどよめく中、クルミが手を鳴らした。

「いい?皆で無事にこなして終えるために、ひとつに捕らわれすぎてはダメよ。
今から散開してジョンくんと、卵を探しましょ…!
他セピラのモニターが無事なら良いけど、これだけのことがあっては、壊れているのが前提だわ。
もし卵を見つけて自分たちの破壊対象なら鎮圧、そうでないなら下手に手を打たないで探し回って。
通達機能が壊れているなら、すれ違った時に情報を共有しましょう。」
「そうですね。ジョンを見つけたら、彼を保護しながら戦いましょう。」
クルミの言葉に259は付け加え、一同は頷いた。
その瞬間だった。
再び、地響きとともに施設内が大きく揺れる。
電気が不安定に点滅し、今度はとうとう一部点かなくなった。
「通路に居ても危険じゃないかな。
今日は『夢見る流れ』も収容されてるからね。
ここも、いつ徘徊経路に選ばれるか分からない」
ウィリーは微笑を浮かべたままだったが、口は一文字に結んでいる。
『今から散開だー!』
「了解」「おう!」「はい!!」
333の言葉に一同は隊列ごとに別れた。
怯えが見えていても、全員の足取りに迷いはなかった。
*
すでに多くの場所でアラートが開始していたらしい。
至る所でアブノーマリティたちが脱走している気配がした。
333が走りながらいち早く察知する。
『宇宙の欠片だー!』
「ひっ…」
暗くなり始めた通路で突然遭遇するアブノーマリティは、危険度の有無に関わらず、384を飛び上がらせた。
宇宙の欠片が『終末鳥』の出現を祝福するかのように響きを上げて歌うのを、726が別の鼻歌交じりに応呼して、リボンのような細い足をダ・カーポで切り伏せた。
間髪いれずにキャロルがユースティティアで横向きに吹き飛ばす。
鎮圧は完了しても、未だせせら笑うような引っ掻く音が響いていた。
彼らが辿り着いた記録チームセピラには何もなかったが、戻ろうと通過した福祉チームで巨大な卵『小さなくちばし』を発見した。
白っぽい卵は幼子が遊ぶように、手を振るように、赤いくちばしを出して、小さく揺れている。
「ここじゃない…!私達が探しているのは『大きな目』…」
384が落胆したかのように呟いて、モニターの動作確認をしたが、記録チームも福祉チームも同じく砂嵐だった。
通達機能に至っては、機械ごと破損が見て取れる。
『んわっ!』
再び施設が大きく揺れたので、333がよろめいたのを、側にいたサイレンが支える。
同時に施設内の電気が再び少し点滅してから、完全に戻らなくなった。
あまりの暗さに、333が名誉の羽を取り出してみたが、いつも眩いはずのその灯りは、何か暗い。
恐らく、電気が落ちたのではない。
何か目の間で薄い暗幕が下りたかのように錯覚する感覚。

「…行きましょう。セピラから出ないと終末鳥がテレポートしてくる可能性があります。
私たちがこれを壊すと、かえって混乱を招きます。
黒装備の管理人達にすれ違ったら、福祉チームのセピラに向かうように伝えましょう。
暗いので気を付けて下さい」
サイレンが押し殺したような声で告げ、一同はその場を後にした。
*
「これは…『長い腕』ですね。」
抽出チームのセピラに辿り着いた管理人達の中、暗がりの中揺れている包帯の巨大な卵を見て、817が呟いた。
審判鳥の頭をそのまま模したような夥しい包帯に巻かれて、一対の羽が揺れている。
先ほどの揺れから、一向に電気の灯りが戻らない。
抽出チームの灯りも同じだが、碑文の金色の光だけは怪しく部屋を照らしていた。
「さぁこんなところに長居は無用だ。俺たちが探しているのはジョン君と『小さなくちばし』。
これを壊してもいいんだが、俺たちだけじゃ時間がかかる。ほかのみんなに知らせて合流しよう。
ここもモニターがイカれてるみたいだし、早くここを出たほうがいい」
青攻撃に免疫を持つこの卵に対し、隊列から817と810とレストを抜いたら、強力な火力を持つ管理人は限られる。
アルジャーノンが辺りをひと通り見渡してすぐに一同とセピラを後にしようとした時だった。
――――突然、
眩い光が抽出チームのセピラを照らし出した。
停電になってからは、それは人を惹きつける光だった。
美しく、仰々しく、フィルターのない管理人たちからは、本物の外の光に見えた。
黄昏。
暗く染まり始める前の、見事なまでの夕日。
一日の終わりの、眠りにつき始める赤い太陽。
誰もの足を引き留めるような、美しい黄昏。
フィルターをつけた管理人達からは、ただ乱暴に書きなぐったような赤い炎が渦巻いて見えるが、それでも足を止めるには充分だった。
我に返ったクルミが急いで号令をかける。
「…!!来たわ!みんな!!すぐにここを出て…!!」
夕日の光が止んだころ、辺りは再び暗闇に包まれる。
一度に部屋に圧迫した空気が押し寄せ、ゆっくりうごめく巨大な怪物の吐息で充満する。
暗闇に確かに蠢く者。神聖と見紛う影。
間もなく眩んだ視界の闇が晴れて、無数の星の光が浮かび上がった。
そこにいた全員が、しばらくその光景に見惚れている。
「急いで!!」
817が言ったのも、まるで聞こえていないように、
一部の管理人たちは未だ、それを見て立ち尽くしていた。
終末鳥を目の当たりにして、
立ち尽くしてしまったソーニャと皿面、
美しい景色に見惚れたようなシャオとブランダー、
興味の対象としたウィリーとアルジャーノンまでもが足を止めている。
「みんな…!何やってるの…!!」
クルミが叫ぶが反応がない。
自分すら息が止まりそうになりながら、身体が闇に溶けるように完全停止するような錯覚をする。
暗闇の中で、無数の目が光り始め、一斉に佇む人々を見た。
その姿に圧倒されていたのか、見惚れているのか、恐怖で意識が飛んでいるのか。
察した817がソーニャと皿面の手を掴んで引き、アルジャーノンたちの方へ走る。
「みなさん…!走ってください…!!」
817の声と、白い翼を見て我に返ったアルジャーノンがウィリーの腕を引いて走り出し、
ブランダーもシャオを抱えて走り出した。
終末鳥の無数の光が流れるほんの寸前、
彼らはなんとかエレベーターホールへ逃げ込むことができた。
「あぁ、…あんな見事な景色でも、命を落としたら終わりだな」
「すまない…あまりにも綺麗な光景だったからね…」「ごめんねぇ…」
走ってきたアルジャーノンが呼吸を整える横で、ウィリーが苦笑交じりに、皿面が震える声で応えた。
「あれを撃って完了にしようぜ」
ブランダーが実際に撃ち抜いてしまえそうな気迫で呟く。
「……」
「大丈夫ですか、ソーニャさん」
抽出チームセピラに面したエレベーターホールで、座り込んだソーニャに、817が覗き込むようにして尋ねる。
呼吸を思い出したように「はい」と、呟いた彼女の目はこちらを見ていない。
反応は明らかに異常だった。
これでは、鎮圧はおろか、隊列を組んで動き回ることの足かせとすらなってしまいそうだ。
「休んでて…、って言いたいところだけど、ここで一人残しておくのは、かえって危険よ。
この揺れの中、クリフォトも暴走してところどころ色んな子たちが脱走してるはずだわ。
ソーニャちゃん、歩ける…?」
クルミが覗き込むように声をかける。
「…はい、大丈夫です…」
彼女は未だどこかふらふらした様子で静かに頷いた。
*
「『長い腕』の卵、コントロールチームにもなかったです…!」
一足先にコントロールチームを覗いてきたラサが、息を切らしながら一同の列に戻ってきた。
安全チームにも、卵は発見されなかった。
彼らはエレベーターが行き渡っている上層部の構造を幸いととらえて、一時散開して偵察していた。
再び収容施設内が大きく揺れてから間もなくして、深刻な顔をした本体と、その脇から緊張感と嬉しさが入り交じった表情のミカンが戻ってくる。
「ホドのチームに大鳥ちゃんの卵を見つけたの!」
全員が合流できたのを確認し、259もいつものように優しく微笑んで頷いた。
「良かった…。白い装備の管理人達に知らせましょう。
私達の標的である『長い腕』は、上層部にはなかったので、次は中央本部の他の階層も見…―――」
「ルドル・タじゃルドル・タじゃ!!!よう来たのお!!おうおうふふふ!!!!」
259の言葉を遮って、突然叫びだしたのはキャロンだった。
常に酩酊しているが、更に息を荒げて突っ込んでいった方向には。
裾から雪のような何かを撒き散らす、ツギハギだらけのトナカイがいる。
いつの間にか脱走していたそれに彼女は、
まるで愛しい者への再会のように、恥ずかしいまでの戯れを行っており、やがて涎をすすることを忘れている。
「きゃ、キャロン先輩…?!」
ラサが頬を赤らめて愕然としながら目を両手で覆い、259も目を覆いながら指の隙間から見て、本体が軽蔑の表情を浮かべながらミカンに背を向けさせている。
その中から1006が躍り出て、冷たく薙刀を向けた。
「んなことしてる場合じゃないだろ」
彼が吐き捨てた直後、刃は軌道を描いてルドルフのツギハギを裂き、変わり果てたサンタの中身を溢し広げる。
みるみるうちにそぎ落とされ、赤攻撃が弱点であるそりのルドル・タは、すぐに収容室に戻された。
「あんまりじゃ…あんまりじゃぁ…おーいおいおいおい……」
赤く投げ出されたサンタの血と、雪溜まりの広がる床の上で、キャロンがアヒル座りのまま、おいおい泣いている。
メアリーはため息交じりに歩み寄ると、E.G.Oを身に着けてない方の手を彼女に差し出して、行動を促した。
「キャロン急いで下さい…。これが終わったら好きなだけルドル・タ舐めてもいいですから。」
「約束じゃよ…?」「はぁ…」
この状況下何が脱走していつ遭遇するのかわからないが、どうであれスムーズにいかないことは確かだ。
1006が一瞬で対処できるもので幸いだったかもしれない。
メアリーがため息をつくのを背後に、先ほどまで顔を赤らめていた259が強く顔を左右に振る。
「中央本部の他の階層も見に行きましょう。
もし、白装備の管理人たちを見かけたらすぐに教育チームに行くように伝えるんです!」
259が足早に歩みを進めながら言いつつ、ちょうどよく
中央本部上部、エリア2で管理人達の隊列すべてが鉢合わせとなった。
暗がりの中、管理人達は呼吸を整えながら、お互いの状況の共有をする。
「…無事でよかった!!抽出チームのセピラに『長い腕』を見つけたよ!」
「教育チームに『大きな目』、あったぞ」
「福祉チームには『小さなくちばし』があります」
「なぁ、ジョンはまだ見つかってないのか?」
再び合流した一同の中、ブランダーが辺りを見渡している。
暗がりでよく見えないが、彼には辺りが見えているらしかった。
一同は顔を見合わせて、首を横に振る。
その時、再び施設の床が揺れた。
皿面が大きくぐらついて、座り込み、思わず手をついた所、慌ててアルジャーノンが支えた。
「だ、大丈夫か皿面くん」
「…ご、ごめん…」
恐怖で今にも全体で崩れ落ちそうだ。
クルミは皿面の項垂れがちな顔に、お面越し、目線の高さを合わせると、静かに呟いた。
緊張している。
「…皿面くん、ソーニャちゃん、よく聞いて。
今から白装備管理人達の隊列に加わって、
一番近いエレベーターホールに留まるのよ。
大鳥ちゃんの卵を破壊した後の白装備の管理人達に保護してもらえば、
少なくともばらついて待機するよりはずっと安全だわ」
"絶対大丈夫だから"、とは言えない。
いくら夢見る流れや、貪欲の王等の廊下移動型のアブノーマリティや、終末鳥と直接の遭遇を避けられ、すぐに回避ができるエレベーターとはいえ、
困憊状態の二人は、白装備の管理人達が鎮圧に向かっている間、無防備だ。
「ごめんなさい…」
「ごめんねぇ…」
ふたりの震える声は、白い装備の管理人達に混ざり、中央本部を後にした。
「謝らなくていいから…」
どこに何が脱走して、どのくらいのエネルギーが消失していて、むしろ今日を終えて無事に訓練が終わるのか、
全員で生きて帰れるのか、ジョンの安否も何も分からなかった。
*
赤い装備の管理人達は、指定された抽出チームのセピラに到着する。
「速攻叩き割ってやるよクソ長い鳥」
1006が殺気立って、薙刀を振り上げると、碑文の僅かな光が刃に反射して、暗幕にくぐもりながらもぎらついた。
「いつ奴らが来るかわからない。警戒していけ」
「いくよー」
「はい!!」
本体は緊迫した声と共に銃を向ける。
ミカンもミミックを振りかざし、ラサはくちばしで後方から狙い撃つ。
メアリーが蒼い傷跡で外皮の包帯をわしづかんで引き剥がす横で、キャロンが卵を前に、美味しそうなものを見るような目でグラインダーMK.4で包帯を解き始める。
「よいではないかぁよいではないかぁ~!」
彼女だけは、この状況下も楽しそうである。
521が飛び掛かってミミックを掲げたが、ターゲットが動きまわらないことにやや物足りなさを感じているようだ。
259は床を蹴ると、真上から天国を突き立てる。
固い外角は叩く手ごたえだけを残すが、卵の感触ではない上に、なかなか割れる気配がない。
飛び散るのは血液のようで、大きく割れる様子もなく、少しずつ剥がれてきた包帯からは、また血色が見える。
「検知、黄昏の徴候を確認、終末鳥が来ます。一斉退避を推奨します」
ルシフェニアの言葉に、一同が素早く身を引く中、1006が留まっている。
「ちょうどいい。奴の頭を殴りたかったところだ。
パンチングボールに毛が生えたような頭しやがって」
夕日のような眩い光が辺りを照らし、
一同はその美しい光景に目を奪われたが、すぐさま退避し始める。
「っほぉ…!!!メアリー!!ご覧!!
ムーディじゃ!!!」
メアリーに引っ張られながら、キャロンは絶景に、拍子抜けするような声をあげる。

光が止み、出てきた巨大な影。
それが、その長い腕を振り下ろす兆候を見せる直前、1006はそのもたげた頭を、2、3発斬り付けた。
怪物の首は衝撃に大きく揺れたが、全ての攻撃を無効化する終末鳥単体にダメージとしての効き目はない。
無論分かっている。
すごく苛ついていたので、彼は殴らずにはいられなかった。
それだけのための斬撃だった。
「一人の管理人の危険を察知、救助します」
ルシフェニアが引き返して1006をさらりと抱き上げると、速やかにセピラ横のエレベーターホールに移動した。
「なっ…!!!またかよ!!!これ危機じゃねえから!!!」
この訓練期間中、要らぬ救助ばかりもらっている。
「1006先輩…!大丈夫ですか…?!」
「ひとりで無理しちゃダメだよー」
「ご無事でよかった……」
ラサとミカンと259が、健気に駆け寄ってくるので、1006はため息をついて項垂れた。
悪意の無い気遣いに囲まれる。
一方卵は、包帯がすり切れ始めて、その内側が見え始めたあたり、効果はあるらしかった。
どこのモニターも壊れていて確認できないので、『長い腕』の破損具合は分からないし、
終末鳥がいつ頃去るのか、戻るタイミングは勘と、気配の察知にかかっていた。
打倒の徴候が見える中、他にもアブノーマリティたちは脱走を始めている。
暗がりでよく見えないが、エレベーターホールの隅にも犠牲になったオフィサー達が眠っていた。
辺りに希望と絶望が
不快な密度で充満している。
*
――――森の香りだ。
辺りを見渡すと、ジョンは暗い森にいた。
むせ返るような緑の香りと、甘い露の匂いと、それにしめった黒い土の匂いが、嫌というほど鼻につく。
遠くに弱い点滅が見えることに気付く。
向こうから光がやってきたかと思うと消える。
その光景にしばらく見とれていた。
「――――――……くん!」
「…………………」
「ジョンくん!!返事をして!!ジョンくん…!!」
ふと、目の前がうっすら明るくなり、ジョンは誰かが自分の肩にすがり付いて呼び掛けていることに気付いた。
「………うぅ…」
唐突に視界が開ける。
先ほどまで見ていた光景との温度差に、周りを確認して、ジョンは呻いた。
森の香りなどではなく、錆のような匂いだ。生臭い血の匂い。
どうやら、撹乱して強い血の匂いを森の土の匂いに錯覚してしまっていたらしい。
自分にえもせずに嫌悪感が過った。
「よ、よかったぁ……」
正面からずっと呼び掛けていた皿面は、ほぅと胸を撫で下ろす。
そっと脱力した彼は、微かに震えている。
周りには形容しがたい惨状が、赤く濡れて広がっており、隅ではソーニャが磨耗しきったように座り込んでいる。
何故自分はここで倒れていたのか。
記憶がない。
「なにが…起こったんです?」
ジョンの問いかけに、皿面は口をわなつかせているのか、細切れに訴えだした。
すすけ始めた皿の面の下の表情を見なくても怯えているのが分かる。
「大変なことになってしまったんだ…。
しゅ、終末が……終末鳥が来てしまったんだ…」
「な、なん、だと…!!?」
ジョンは耳を疑った。
そうだ、確かあの時ゲートの破壊に招集されたものの、審判鳥とエレベーターで同室になり、恐怖のあまり気を失ってしまった。
あまりにも自然に審判鳥をエレベーターに乗せてしまったことを、彼は思い出した。
ゲートの破壊は、間に合わなかった。
「今…皆がそれぞれの卵の破壊にあたってるんだ。
僕たちはあまりに怖くて、皆に任せちゃったんだけど…すぐそこの教育チームセピラには白装備のみんながいる…。
でも、…でもクリフォトも暴走しちゃってて…
ぁあっちもこっちも、アブノーマリティが脱走してて…。」
皿面は恐怖に呼吸を乱しながら語った。
モニターが破損しているために通達を共有する術もなく、現在の周りの状況を把握することができない。
「ここなら、ある程度の危機は回避…できる、からね。
キミがここで無事に見つかってくれて…よかったよぉ…」
混乱ぎみに言い終えて皿面はがっくり両手を床についた。
ずっと気を張っていたのだ。
まだ緊張状態が続く中、せめて安否が気がかりだった管理人が目を覚ましてくれただけでも、気が緩む。
ジョンは、不安と恐怖に怒号を飛ばしたくなる気持ちを抑えた。
しかし、周りのエリアから聞こえる叫び声や、掛け声、アブノーマリティの暴れている音に、時折鼓動がばくつく。
今でも耳に、オフィサー達の悲鳴が焼き付いているようだ。
彼は口から微かに「くそ…くそ…」と吐き溢しては、目の前の皿面の少し安堵したらしい姿に、口をつぐむ。
それぞれ、手元のE.G.Oを握りしめるようにして、いつ侵入してくるかわからない脅威に怯えながら警戒していた。
HEクラスまでのアブノーマリティなら問題なく鎮圧できる。
しかし、ジョンが手にしているのは、魔法の弾丸だ。
今の精神状態で、充分なコントロールができるか、分からない。
共同線で皿面を巻き沿いにするわけにはいかない。
彼は、自分の手足が中途酸素供給にわずかにでも動くことを確認すると、魔法の弾丸を手に立ち上がった。

「脱走アブノーマリティが近くまで来ていないか、偵察に行きます。
……お二人はここで休んでいて下さい。」
ジョンの言葉に、皿面は驚くように顔を上げた。
表情は見えない。
収容施設内で、今動ける多くの管理人達が終末鳥の卵たちを壊すために戦っている。
万善なコンディションでないとはいえ、もう自分は動ける。
…だとしたら、すべきことは見えているのだ。
彼が廊下に出ると、辺りは夢見る流れの脱走を知らせるあたたかい水の感触の中で、
マッチガールと知恵を欲する案山子がこちらに向かってくるのが見えた。
辺りには蔦が蔓延しており、ここにはいない白雪姫の林檎の脱走を物語っている。
ジョンは、案山子に殺された職員が、いかに残虐な姿となっているかをよく知っている。
しかし、引き下がるわけにはいかない。
マッチガールはTETHクラスとはいえ、人の大勢いる場所に向かっては致死量のダメージを与える。
蔦に足をとられながらもこちらに向かってくる足取りからして、教育チームセピラに向かうことは察知できた。
「……ちくしょうめが」
彼は、冷静さを保っているわけではない。
ただ色々なものを押し殺して目の前を睨み、トリガーを引いた。
*
「っ…!!」
再び揺れた床に、クルミは耐えながら転びそうになったのを810が支えた。
「ありがと」と伝えるクルミの声を短く聞き届けて、810はすぐに目の前の『小さなくちばし』へ飛び掛かる。
黒の装備の管理人達は、今動ける人数が少ない。
その分、青装備の管理人達が数名フォローに加わっている。
『小さなくちばし』の卵は、さきほどよりも痛ましく血に濡れ、飛び出していたくちばしは力を失っている。
ぽっかり空いた口だけは、未だ閉じることもなく、揺れ続けている。
哀れにも、ぴしぴしと、ヒビの走る音が聞こえ始めるのと同時、
福祉チームの青い闇に、黄昏の光が広がった。
「来ます…!!」
817が叫んだ。
しかし、彼女は退こうとせず、なおも蛇の巻いた林檎の杖を振り下ろしては、卵の下から鎌を裂き上げさせている。
赤い鎌の花は美しく、黒々と咲く。
ウィリーも銃口を下ろすことはなく、夢中になってラエティティアで連続射撃を続ける。
くぐもった闇の中、マズルフラッシュはこの状況の時のためのように目を焼く。
シャオの銃口を向けた先からは、蝶が飛び交い、僅かな光に反射した白の蝶は幻想的に群れをなして昇る。
レストがふわりと飛び込んで剣を走らせると、青い軌道とともにそこに深く入り込んで大きく亀裂が入った。
「あと少しだ…!」
黄昏が静まりかけ、終末鳥の出現が見え始めているのに、アルジャーノンも退くに退けないで、叩き続けている。
「まだまだぁあ!!」
810が声を枯らさんばかりに叫んで、大剣を叩きつけると、亀裂はより大きく入った。
黄昏が止み、終末鳥の姿が現れた時。
「…」
天井に浮遊したブランダーの瞳は、黄昏が止んだ闇の中、青く光る。
その光と同じ色の閃光が煌めいて『小さなくちばし』をだけを貫いた。
白っぽい卵の破片は、赤く染まって床に転がる。

途端、怪物がうめき声をあげる。
「やったの…?きゃ…!」
「下がりましょう…!!」
クルミが目を疑っている間、817はすぐにその長身の彼女を抱き上げて引き下がった。
「き、キミたちも早く…!!」
「おおっ?」
アルジャーノンは、着地したブランダーと側にいたシャオの腕を引いて走り出し、
ぎりぎりまで見守っていたウィリーは彼らに押されるように下がる。
「いやぁ…それにしても素晴らしかったね。
ところであの割れた卵の中には、一体何があるんだろう?」
彼は未だに、とても興味深そうにすぐにでも戻りたそうにしている。
「き、気持ちは分かるけど、今はやめた方が良いだろうな…」
アルジャーノンも、ほっと一息ついて苦笑した。
彼らの標的は撃破された。
しかし、まだ終わりではない。
*
「…」
皿面は恐怖紛れに、ポケットの中に入れたままのキーを、外に見えないようにそっと取り出して見た。
無事に目を覚ましたジョンは、現在このエレベーターホールの周囲を巡回して戦っている。
彼が無事で安心した半面、鎮圧に赴いた姿を見届けて、皿面の心は動き始めていた。
相変わらず、強く揺れては収まる施設内。
エレベーターホールの隅には、完全停止しているソーニャがいる。
ジョンが巡回しながらアブノーマリティの鎮圧に向かっているとはいえ、
ここも絶対に安全とは言えない。
ふと視界の隅では、ソーニャが何か祈っているように見えた。
この状況で祈りの無力さはともかくとして、何かの動作があることに安心しかける。
しかし、それが祈りなどではなく、
彼女が胸に自身の銃口を突き付けている姿だと気付いたときには声が出なかった。
戦慄が走る。
「なっ…ぁ…」
引かれた引き金の音ともに、胸元から白い蝶が湧き上がり、
それを皮切りに空気が動いたかのように、言葉が出てきた。
「ソーニャくん、な、何を…!」
よろける足で駆け寄るが、恐怖で腕が届かない。
ふわりと視界を塞いだ白い蝶の群れが開けると、信じられないくらい、彼女はきょとんとした顔を上げてこちらを見ている。
「何、やって…。ええ…?」
「……驚かせてしまったようですわね。
ごめんなさい。」
とうとうおかしくなったのか、先ほどまで自分と同じく暗い顔をしていた彼女が、柔らかい微笑を浮かべている。
このまま自害してしまうのではないか、と思ったところで、彼女の手にしていた崇高な誓いが白であることに気付いた。
「キミ…これ、もしかして…」
皿面が言いかけたところ、彼女は微笑んで銃をしまった。
「もしかしてと、私も思っていたのですけれど、自分でやっても効果があるようですわ。
とても便利でしょう?」
彼女の言葉に、皿面は強張っていた腕が緩んだ。
「驚かさないでよぉ…」
声は未だに震えている。
しかし皿面は、彼女が全くパニック状態ではなかったことに薄々気付いていた。
自傷でバランスを取る人間は、この会社ではざらだ。
とはいえ、彼女はもう復帰状態にあるらしい。
先ほどとは全く違う様子で、優雅にゆっくり立ち上がると、すぐにでも卵の鎮圧支援に行きたそうだ。
この外側では、もっと酷い惨状が広がっているのだろう。
「……ねえ、ソーニャくん。
ちょっとお願いがあるんだけど……。」
皿面は息を呑んで彼女を見上げる。
もうここを動かなくてはいけない。
*
『大きな目』は、時々その卵の表面にある目をぎょろつかせながら、辺りを見渡している。
「いっ…今こっち見た…!?」
384が小さな悲鳴を上げて縮こまりながら、煌めく星の音を操り、726はただただいつものように星の音の光を反射するダ・カーポを振り下ろしている。
暗闇の中、持ち上げられた彼の口の両端は、卵の僅かに光る目に照らされて、
なんてことのない作業をやっているかのように、軽やかで淡々としていた。
『んいー!!』
333自身も無我夢中になって歯を食いしばりながら砲撃を続け、卵に火を灯し続ける。
相変わらずすごい量の炎の灯が注いでいるようだったが、
辺りの特殊な闇は、眩い光をかなり遮断しているようだ。
「大鳥ちゃんの卵に穴をあけるのは、気が引けるけど、しゃーない!!
絶望ちゃん、私に力を…!!」
555の鋭利な涙の剣は、暗闇に星座を描いてつき刺さる。
各々の微かな煌めきが、大鳥の怪しく光る目を、卵を、飲み込んでいく。
上空から無言で振り下ろされたサイレンの対価が、鐘のような響きを立てる。
卵は衝撃に震え、大きく揺れた。
黒っぽい卵の表面は、無数の目の光でよく見えないが、少しずつヒビが入っているらしかった。
「…ジョゴス」
「てけり・り!」
キャロルの側から流動体のようにして現れた玉虫色の不定形な生物が、僅かに発光しながら飛び掛かる。
リンクするように丸い目を開き、『大きな目』を包み込むように齧りついた。
黄昏が来たのは、その直後だった。
先ほどまでの暗闇も、まるで嘘だったかのように、辺りは夕焼けに似た眩い光に包まれる。
「皆さん!!退避しましょう…!!わぁっ!!」
384が手で促すも、終末鳥がテレポートしてきたのと、地を引っ掻いたのはほぼ同時だった。
揺れに足がもつれ、転びそうになり、彼を支えようと駆け付けた726までもよろける。
「てけり…りぃ…!」
「ひっ…あ、ありがとう…!!」
「おおー?」
瞬間、視界に飛び込んできた謎の生物の形の定まらない背に支えられ、384と726の二人は転ばずに済んだ。
それだけではない、その生物は大きく広がった身体で、ただ震えながら終末鳥のもう一度振り下ろされた腕を抑えている。
終末鳥のもう片方の爪の腕が床を押し、きぃきぃ響く。
かなり不安定らしい。
必至に抑えてこちらを守ってくれる様は、異形にして健気だ。
「禳、貰い受けるとしよう」
キャロルがジャスティティアを振り下ろすと、『大きな目』に入っていたヒビが大きく広がり、
揺れ落ちた。
怪物の呻き声が広がる。
*
赤い装備の管理人達は、再びテレポートしてきた終末鳥が去るのを、息を殺して待っていたところだった。
急に破裂音とともに、エレベーターホールに何かが、ずるり、と入ってきた。
「きゃっ何…?!」
「ああ^~~!!」
キャロンが何やら歓声を上げている。
あまりにも唐突すぎて、最初何が起こったのかラサには分からなかった。
―――蔦だ。
夥しい量の緑色の蔦が、エレベーターホールにひしめきながら伸び始めている。
「これは、白雪姫の林檎の…?
―――…!」
259が驚いて蔦に手を触れる。
見覚えのある深い緑が、ここに迫りくる危機を知らせていた。
「そんな…!エレベーターホールには、りんごちゃんは出てこられないはずじゃ…?!」
ラサは驚きながら辺りを見渡す。
みるみるうちに、それは少しずつ浸食してきた。
猛烈なスピードではないが、決して遅いとは言えない。
「先日までの異常…それに反して通常出現に見えた終末鳥。
アブノーマリティ達の行動区域に異変が生じてもおかしくない、か…くっ!」
本体が険しい表情を浮かべて、くちばしを手にした。
「このクッソ狭い部屋に出やがるか、腐れ林檎…!」
1006が悪態をつき薙刀を向ける先には、一際長い蔦がタワーを作り始めていた。
『白雪姫の林檎』が出現する前兆。
相手は、物理である赤攻撃にやや耐性を持ち、苦戦を強いられることは必須だ。
「E.G.Oくちばし黒ダメージ20%増加。
E.G.Oくちばし装備管理人の退避を推奨します」
ルシフェニアがプログラム口調で話すも、すでに白雪姫の林檎は姿を現したところだ。
林檎は、与えられた哀れな身体で、我が身の王子さまを信じて祈っている。
彼女は両腕に似た蔦を前に、待ちわびるおしとやかな少女の姿をしていながら、管理人達の身長を大いに上回っていた。
「逃げろといっても、セピラにはまだ終末鳥が居る。
エレベーターもこの様子で稼働するとは思えないな」
本体が怪訝そうな表情で吐き捨てながら狙撃する。
その向こう側にあるエレベーターは、中まで蔦がびっしりと伸びており、扉を阻害しているようだ。
本体の言うように、これで正常に動くようには見えなかった。
ふと、絡む蔦に足をとられそうになる。
本体とラサを庇うようにして蔦の隙間の床を蹴り、前に出たミカンは、大きくミミックを振りかざした。521も反対側からさながらミミックの鋏を作るようにして切り付ける。
「プリンセス、ボクがお部屋までエスコートしようか」
蔦は折れ、りんごも揺れるが、まだ致命傷には足りない。
蔦は、悲しみに暮れたような林檎を掠めながら、容赦なく未だに伸び続けている。
足場がほとんどなくなった。
足を取られないようにして、メアリーが飛び掛かる。
259が伸び来る蔦に負けじと天国の枝葉を掲げる。
「帰っていただきます…!!」
「虫食い林檎…サラダにして捨ててやる!!」
蔦も林檎の顔も、1006の薙刀が描いた鋭い亀裂を、するりと飲み込む。
「うひひひたまらんのうぅこのプレイ~!!」
背後から声がするのでラサが振り向いたとき、もうそれは始まっていた。
「あっ!キャロン先輩が…!―――――きゃぁっ…!!!」
「…!ラサさん…!!キャロンさん…!!」
悲鳴に振り返ったミカンの視界には。
蔦に縛り上げられて何やら楽しんでいるキャロンと、足をとられたラサが居た。
ずるりと伸びて覆い始める蔦は、次第に動ける範囲を削っていく。
ラサは転んだままくちばしで蔦を狙って発砲するが、焼け切れても次々とキリがない。
すぐにミカンが駆け寄って蔦を斬ろうと奔走する。
しかし斬っても新たに彼女たちに巻き付き始める蔦の成長は著しく、抑えるのに精一杯で
なかなか解放にありつけない。
「二人の管理人の危機を察知、救助しま―――…」
ルシフェニアが腕を伸ばそうとしたが、彼自身にも巻き付き始めた蔦は、
今にも彼の青い光を飲み込んでしまいそうなほど覆い隠していた。
普段、職員たちは。
こうやって襲われていたのか。
巻き付く蔦は次第に強さを増して、素手でもほどけないくらいに締めあがる。
足元から新たに手を伸ばしてくる蔦を、ミカンが必死に排除しているが、
その分林檎への攻撃勢力がそがれてしまう。
1006、521、本体、メアリー、259が最大火力で鎮圧に急ぐ。
捕らわれた三人の解放、否、少しでも現状維持するため保守に勤めていたミカンが突然足をとられて転ぶ。
「きゃっ!!」
「贋作…!!」
それに気付いて急いで駆けつけようとする本体に、蔦が迫ってくる。
「ほんたい…!!!あぶない…!」
彼女の声に、本体はすんでのところで蔦の直撃をかわしたが、肩に衝撃が走る。
「俺に構うな!自分と他のやつらの救助に…!」
全員の苦戦を確認した259が、普段優しいはずの眼の奥に確かな怒りを宿して、静かに告げた。
「……皆さんをこんな目に…
……許しません」
259はその時から、表情が一変した。
まるで別人のように、天国を猛スピードで突き刺している。
それは特殊な条件下に与えられる効果のパニック状態の時ように、敏捷性と攻撃力が先ほどより大きく上回る。
259の顔には、もはや笑顔が残っていた気配すらない。
天国の撒いた枝が、ヤドリギのようにりんごから吹き出しはじめ、1006と521の刃が追い詰め、メアリーがその虚空の目を塞ぐ。
危機に瀕したのか、白雪姫の林檎は最後の力をふりしぼって、蔦を大いに広げた。
その先には、捕らわれたままのキャロン、ラサ、ルシフェニア、ミカン、救助しようと苦戦する本体がいる。
「くっ、間に合うか…?!」
521がミミックを投げおいて、肉弾で突っ込もうとするも、蔦の方がわずかに早い。
もう誰もが駄目だと思った瞬間だった。
目をぐっと閉じる。
突然、周辺の空気が凝縮される。
「……?」
しばらくしても襲ってこない痛みに、ラサは恐る恐る目を開いた。
「こ、これ…!!浸食シールド…?」
自分たちをいくつものハニカム状の壁が円形に包む。
できるはずのない紫色のシールドが展開されていた。
蔦は彼らを通過するも、それはシールドに阻まれ大きく逸れる。
「"よ、よかったぁ…みんなぁ、大丈夫?"」
突然聞こえてきたのは、管理人…皿面の声だった。
モニターも通達機能も破損しているというのに、どこからか発声されている。

「その声は…皿面?!このシールドは…
まさか…お前、司令塔にいるのか…?」
「話はあとだ!行くぞ!!」
辺りを見渡す本体たちを背後に、1006が再び振りかぶって林檎を切り付ける。
林檎はそれを最後にあっけなく崩れさり、哀れにも残り落ちた林檎の頭はそっと元の部屋に戻された。
1006と521がようやくありつけた卵の破壊チャンスに走って行く。
林檎の頭を切りつけて着地した後の259は、
しばらくの静止後、すぐに我に返って、急いで五人の拘束を解き始めた。
259はさきほどの状態は、パニック状態ではなかったらしい、
鎮圧が完了すると、緊迫しているとはいえ、いつもの優し気な表情に戻っていた。
「みなさん、大丈夫ですか?」
「あ、ありがとうございます259先輩…!」
ラサも卵の鎮圧に向かいたい焦燥を抑え、すぐにミカン達の足元の蔦を外しにとりかかった。
「もうおわりかぇ…」
「何言ってるんですかあんた」
メアリーはキャロンに絡まっていた蔦を容赦なく切り裂くと、ルシフェニアに絡まった蔦を千切りに向かった。
*
「エレベーターが来ない…?」
384がいくら待っても開かないエレベーター口で冷や汗を流した。
二つの卵を破壊し終えた白、黒、青の装備の管理人達は、合流に抽出チームセピラへ向かおうとしていたが、懲戒チームエレベーターホールで足止めを食らっていた。
ボタンは反応しても、いくら待っても、登ってこない。
奥の方で緑の蔦がわずかに見えるのを、ウィリーは確認した。
「あれは、……白雪姫の林檎の蔦が絡まってるんじゃないかな。
まさかのエレベーターにも出現したのかもしれないね…」
「皆さん、無事だと良いのですが…」
先ほどまで単体で鎮圧に走り、全員と合流したジョンが呟く。
あの後ジョンは、『大きな目』を破壊した白装備の管理人達と合流し、皿面たちを呼びに行ったが、
二人はすでにいなかった。
床は以前から血濡れていたもので、新たに何かに襲われた痕跡は無かったが、
壁の一部が恐ろしく破壊されていたことを見ると、何かあったに違いなかった。
管理人同士で呼びかけ合い周辺を捜索するも、モニターが壊れている今、いち早く終末鳥の収束が優先された。
新たに安否不明の管理人が出てきて、一同は精神を地味に摩耗していく。
『おー!へるぱー!!』
333の声と同時に突然部屋に飛び込んできたオールアラウンドヘルパーを、一同は瞬時に一斉攻撃し、事なきを得た。
とはいえ、ここに待機し続けても仕方がない。
いつどのアブノーマリティが入り込んでくるか、誰にも分らない。
*
再び抽出チームセピラに駆け込んだ赤い装備の管理人達。
高く天秤の金属音が響くも、それは521によって阻害される。
終末鳥の金色の天秤は、上空から叩き落され、
1006の刃が入り込み、
最後の卵『長い腕』が大きく割れた。
先ほどのダメージもかなり蓄積していたらしい。再突撃から間もなくあっさりと割れた。
施設内に弱い揺れと、怪物の叫び声が力なく響き渡り、
背中に走る痛みと違和感が、黄昏の終了を告げていた。
「わっ・・・!」
終末鳥の最期を、別室の――
――無数のモニターの前で見届けていた皿面は、驚いてその場で両手をつく。
背中には大きな黒い靄…否、翼が生えていることに気付く。
黒に金色の無数の目。
闇の黄昏を過しもの。
終末鳥の鎮圧は無事に完了したらしかった。
「ぼ、僕ももらえるの…?」
皿面は驚きながらも、その背にある翼に恐る恐る触れる。
ふわふわだ。
「"皿面先輩、聞こえますか?終末鳥の鎮圧、無事完了しました!"」
声に耳を澄ますと、モニターにはカメラに向かって敬礼しているラサが見えた。
ラサや、全ての管理人達の背には、自分と同じ『闇の黄昏を過しもの』を授かっており、
抽出チームのセピラと、懲戒チーム横のエレベーターの二手で、管理人それぞれ自分たちに与えられたギフトに驚いたり触れたりしていた。
こうして見渡すと、全員無事のようだ。
「よかったぁ…えぇっと、
みんな、聞こえるかな…?」
皿面は収容施設内全体に通達の連絡を入れる。
―――管理人の場所。
これが管理人達の本来の仕事の席だ。
「"皿面くん…?!キミ今司令塔にいるのか…?"」
懲戒チームで足止めを喰らっていたアルジャーノンが、皿面を探して辺りを見渡す。
「…うん。レストくんがくれた鍵だよ。
抽出チームの長い廊下と、記録チームの長い廊下の間にある部屋に繋がっててね。
もしかしてと思ってここに来てみたんだけど…
……うわぁああっ!!…―――――――」
突然皿面の悲鳴が響き、通信は途切れた。
「皿面くん?!皿面くんどうしたんだ…!おい…!!」
急いで呼びかけても返事が無い。
「皿面先輩…!」「皿面さん…!」
「クソッ、何かあったのか…!」
至る所で管理人達が皿面を呼びかけてみるが、向こうの通達は途切れたままだ。
「皆さん…!こっちです!」
259が真っ直ぐ抽出チームの通路を走る。
辺りは『夢見る流れ』の脱走を告げる水で充満していたが、今相手にしている暇はない。
1006が舌打ち混じりに辺りを睨むのを背景に、
259はすばやくキーを取り出す。
懲戒チームで足止めを喰らっていた管理人たちも、サイレンに促される。
「記録チーム…記録チームの通路に急ぎましょう…!」
彼らも中央本部を横切り、ようやく記録チームの通路にたどり着いた。
「ソーニャちゃん!!大丈夫!?一体何があったの?」
長い通路の壁に、もたれかかるようにして項垂れていたソーニャがいる。
クルミが駆け寄って、肩に触れられた彼女は、うっすら目を開く。
「ク、ルミさん…?」
眼下に広がる血溜まりの縁は、凝固しているのではなく、焦げている。
何があったのか、なんとなく察して口を閉ざした。
そんな状態とは裏腹に、ソーニャはクルミたちを見てほんの少し安堵しているようだった。
「叫び声が聞こえて、私も向かおうとしたのですが……油断してしまって…
いえ、私のことは大丈夫ですから、皿面さんを…」
幸いにも崇高な誓いが耐性を持っていた。
ぽっかり銃痕を広げるには至らず、なんとか塞がったらしい。
「分かったわ、ソーニャちゃん捕まって。急ぐわよ。
…384ちゃん、星の音には同室の人に回復効果があったわよね。
力を貸してもらえる?」
クルミの言葉に384は落ちているトークハットを拾い上げ「は、はい…!」と震えながら、焦げた血溜まりの上を滑らないように渡った。
記録チーム奥に続く扉は半開きになっており、誰かが出入りした痕跡が残っていた。
*
「皿面…!」「みんな…!!」「…!!」
「わっ…み、みんなぁ…!」
扉を開いて視界が開けた先。
そこは、管理人の普段駐在する司令塔と、とてもよく似ている作りとなっている部屋だった。
いくつかのモニターは青白く点灯し、現在の施設内の様子を投影している。
すでに抽出チーム側から侵入した管理人達が、その光景に目を奪われて固まっていた。
部屋の中央では、モニターを背に皿面が人影に拘束されている。
「…役者は、揃ったようですね。」
一同は目を疑った。
聞き慣れた声だ。
「…アン、ジェラ…?」
この閉鎖された小部屋、アンジェラが皿面を拘束している。
あろうことか皿面の首元をしっかり強く、固める様に。

「これは、なんの真似ですか…?!
アンジェラ…!!皿面を離しなさい!!」
259が声を珍しく荒げて叫んだ。
訊ねられたアンジェラは、ただ姿勢を変えず、微笑を浮かべるだけだった。
「……私は……
…私は、アンジェラではありません」
細い笑いの後、伏せていた彼女が瞼を開くと、その瞳の色は金色などではなく、黒々としていた。
薄暗い司令塔の暗がりの中、それはどこまでも奥深くに繋がっているような錯覚をする。
「なっ……」
驚愕する一同を前に、彼女が未だかつてしたことのないような表情を浮かべさせた。
悲しみと嬉しさが入り交じるような高揚、
しかし暗い表情だ。
「実に良い…実に興味深い結果でした。
ロボトミーコーポレーション…
…まさかこの部屋に入ってくるとは、計算外ではありましたが。」
彼女は…――否、アンジェラの姿をした何かは、不可解で不明瞭なことばを紡ぎ始めた。
アンジェラの面影を操って唄うように。
「管理人たちは、自らどう行動することが最善かを考え、自らの意思で動く。
それは盲目にして方位を失った愚かな堕ちゆく星。
職員たちが行動するよりも、管理人たちによる行動の方が
アブノーマリティから産出されるエネルギー量は多く、
純度もはるかに高いのです。」
「お前は…一体何者だ?アンジェラの姿を使ってまで…
ロボトミーコーポレーションの中枢区経由を騙ってまで、一体何者なんだ…?!」
苛立ったように本体が問いかける。
しかし、それは目蓋を伏せると音声だけアンジェラのまま
透き通った笑いをこぼすだけだった。
「――――――…キミ…もしかして、ウイルスかい…?
それも、意思を持って行動するマルウェア……」
ウィリーの静かな言葉に、アンジェラの姿をした何かは、
未だに皿面を拘束したまま、そっと首をかしげて見せた。
白い肌が、より一層白く見え、辺りを凍り付かせる。
「……ご名答。さぁ、もうお気づきでしょう…。
これは実験を兼ねた、エネルギー強奪計画だったのです。
あわよくば、あなたたちを拘束し、この会社の技術を利用して、
より高エネルギーを発生させるアブノーマリティを生み出し、回収したかった。
あと一日あれば、可能だったものを…
―――…本当に、台無しになってしまいましたね?」
「ひゃっ……」
手元の皿面を脅しかけるように、腕を力ませた。腕の中で皿面が小さな悲鳴を上げる。
その声は、アンジェラの声のまま、落胆していたようだった。
「こちらも答え合わせをさせていただきましょうか。
何やら、一部の映像が乱れて映らなくなったかと思えば、
X-394がロスト。X-228は不審な動きをし始めるも、精神汚染は検出されない。
試しにX-228を魔弾で撃つと、精神汚染時と違って、ちゃんとその場で座り込みましたね。
大方、X-228がパニックになってあなたを殺害し、無意味に徘徊しているように装いたかったのでしょう。
実際はカメラの配線を破壊し、X-394がX-228の床に乱射する蝶の影に隠れ、
各エリアのカメラの死角を選んでここに来た。
……違いますか?」
彼女の淡々とした凍るような言葉に、ブランダーは明らかなる殺意を眼に灯した。
「父様を…利用したのか…オマエ……
…オマエ…無機物の分際で…」
ソーニャは、ブランダーをそっと制し、
アンジェラの確認には答えずに、静かに見据える。
「あなたは…誰なんですか?
なんのためにこんなことを……」
「私はただの"ウイルス"ですよ。名乗るほどのものでもない。どこにでもいる、とても一般的な。
…そう、破壊と強奪を実行する、一般的な、ね。
さて、まず、この管理人さんから、どうしてくれましょうか…」
腕の中で怯える皿面を見て、一同は焦燥に駆られた。
「待って下さい!人質は私が代わります!
皿面を解放してください!」
『かんりにんが人質になるよ!』
「僕が代わろう…」
259、333、521が次いで、取引を持ちかけたが、アンジェラの姿を借りたウイルスは全く動じない。
「死なない人質に、なんの価値がありますか?
取引として、全く成り立ちません。」
体質をすべて知られてしまっている。
一同が緊迫した空気の中、ただ成す術もなく、愕然としていた。
レストとルシフェニアも、この訓練施設内のハッキングを繰り返してきたが、
相手には全く足跡がなかった上に本当の正体がわからない。
何の取引材料もない。
取引も何も、これは一方的な強奪だ。
「何をしたら…みんな助かるの…?」
ミカンが純真に真っ直ぐな瞳で見てくるのを、ウイルスは満面の笑みで迎えた。
「そうですね。
では手始めに、貴女を貴重な検体として―――」
アンジェラの身体を借りた者が言いかけ、ミカンに手を差しのべかけた、その時だった。
破裂音とともに、急に天井に吊り下げられていた形だけの電灯が、弾けるようにして落下した。
「…!!!!」
「皿面さん、早く!!こ、こっちだおい…!!」
落下してきた電灯に気を取られ、一瞬腕の力を抜いたアンジェラから、皿面は急いで滑り抜けてきた。
すぐ保護するように、管理人達は震える彼を列に覆う。
先ほど怒号交じりに叫んだのは、ジョンだった。
見ると彼は、魔法の弾丸を手に、天井に吊り下げられた電灯のコードを撃ち落としていたようだ。
ものすごい音を立て、アンジェラのすぐ真横を落ちた電灯は、大きく破損し、飛び散ったガラス片はモニターの青白い光を浴びてキラキラと散らばった。
飛び散るガラス越しに、彼女は微笑んでいる。
「―――いいでしょう。
高純度のエネルギーは回収完了できました。
皆さんをアブノーマリティに変貌させて回収する計画は破綻しましたが。
ここにもう用はありません」
アンジェラの姿を借りた何かは、彼女の顔のまま不敵な笑みを浮かべる。
その手は宙を漂い、何かに触れた。
「それでは、皆さん、地獄へ
"行ってらっしゃい"―――」
アンジェラの言葉を借りるように言い終えると、それは力なく崩れ落ちた。
側にいた259が、すぐさま駆け付けて彼女を抱きとめる。
空色の髪がさらさらと流れてその表情があらわになると、彼女はすでに瞳を閉じており、もう何の反応もない。
先ほどまでの面影は微塵もなく、いつもの目蓋を閉じた彼女の顔があるだけだ。
「…気絶しているようです。」
259の表情からは笑顔が消えたままだ。
異様な空気の中ウィリーが呟く。
「これは…終わりではないね…」
その目は普段の笑みを浮かべながらも、危機感を察知していた。
 アイスでも
ホットでも・*゜
アイスでも
ホットでも・*゜