2
―――――…二日目。
どうやら雨は降り続いているらしい。
施設内は穏やかで静かな朝を迎えた。
しっかりと出撃時間を伝えられていても、各自目を覚ます時間帯はそれぞれで、管理人たちの人影もまばらだ。
休憩時間と題したそれは、休息も食事も、結構マイペースにとれるし、出撃前の会議まで自由な時間が取れる。
二日目の会議は、訓練施設のイェソドから伝達があって招集された。
二日目にしてようやく危惧性の高いアブノーマリティの情報の説明があるらしく、会議室に歩みを進める管理人達の中に再び緊張感が漂い始める。
会議が始まる少し前のことだった。
「うーん…なんとなくなんだけどね」
昨日に次いでウィリーは、259と共にモニターを見上げている。
「やはりそれぞれのアブノーマリティたちの収容場所はランダムじゃないかな。
今日に入ってアッシャー、アツィルト、関係なく危険度の高いアブノーマリティが居ると考えた方がいいよ。
恐らく『死んだ蝶の葬儀』は教育チームかな…?
でも、今日は『魔弾の射手』は同じ部門ではない気がするんだよね」
モニターには相変わらず、現状の収容施設内部の地図だけ表示されており、収容アブノーマリティは謎のままだ。
「すみません、なんだかウィリーを利用するみたいに訊いてしまいましたね」
259が申し訳なさそうに、それでも笑みを向けると、ウィリーも微笑みながら首を横に振る。
「いや、僕から見に来たんだよ。あくまでも勘なんだけどね。
それにしても、ブランダーさんとシャオさんは、どうする?」
「良かったなシャオ!行くだろ?」
ブランダーが悪戯っぽく微笑む傍らに、シャオが少しだけ戸惑った表情をちらつかせた。
儚げな虚空の瞳には、ためらいが見える。
運良く並んでくれればいいが、そういうわけにもいかないのだろう。
「…順番でいくのです。今日は父さん…、しゃおもブランダーと一緒にいるのです。
そして、明日は父様の側でブランダーと一緒がいいです。」
彼の言葉に、ブランダーは少し驚いた表情を見せた。
静かなシャオが珍しくも気持ちを語る。
「今日しゃおはブランダーと一緒に待つです。
…でももし、もしも、父様が困っていたら、しゃおに任せて欲しいのです」
アブノーマリティに私的な感情を持って接するな、という言葉など、彼らにとっては全く通用しない。
それにも関わらず、彼らはそれ以上に優先させるべきものに触れる。
「ああ~、尊いのう…」
興奮している涙声のキャロンが、頭をテーブルに擦り付けている。
広がっていく水たまりは、涙が、涎か。
「私は絶望ちゃんの所にいけたらなんでもいいよー」
555は落ち着いた様子で手を振ってみせている。
「それにしても、上層下層関係なしに危険度が高くなると、心配ですね。」
259が収容施設内の図解を映したモニターに視線を戻す。
本来の支部であれば、アブノーマリティの配置は例外を除いて固定であるが、様々なアブノーマリティの接触を体験して欲しいという訓練方針だろうか。
彼らが未だ心配を拭えない中、やがてイェソドが入室してきた。
一同は会議を中断し、それぞれの自分の卓に着く。
今日は円卓の席に一つ一つ資料が置かれている。
「お取込み中でしたか?」
イェソドは辺りを気遣うような様子が伺えたが、依然と表情に変わりはない。
「大丈夫です。よろしくお願い致します、イェソド」
柔らかく微笑む259を見て、イェソドは「ふむ」と頷いた。
彼は円卓から孤立したテーブルに資料を置いて続ける。
「私はこの施設のイェソドです。皆さんの訓練と今回の情報についてサポートします。
お手元の資料を確認してください」
彼はそう言うと資料を手にして、モニターで解説をし始めた。
手元にある資料は、それほどの厚みもなく、決まりきったマニュアルと初見の文字がほんの少ししかない。
「管理人の皆さんに案内した通り、今回皆さんに危険視してもらいたいアブノーマリティの情報について、一通り説明します。
まず、対象については多くのことはまだわかっていません。ただ…―――」
イェソドは、画面を切り替えて一見紫とも灰色ともつかない時計盤の画面を表示した。
一部の管理人達にとって、見覚えのあるものではあった。
一同は息を呑む。
「それは、『時の干渉者』である、と。」
その時、急に音を立てて立ち上がった管理人がいた。
見ると、キャロルが席を立っている。
気のせいが、冷静そうな彼女が口の端を震わせたように見える。
ユースティティアの包帯で表情はよく見えないが、明らかに動揺していることが誰にでも分かった。
「どうしましたか?」
イェソドが声を掛けたが、しばらくの沈黙の後、「…否、なんでもない…」と彼女は再び着座する。
冷静を装って、資料を手にする腕は、心なしか震えて見えた。青い長髪が少し、小刻みに震えている。
その様子を見ていた817は、810と顔を見合わせる。
817は、キャロルにほんの少しだけ笑みを浮かべ、息を呑むと再び資料に目を落とした。
「…続けます。我々ロボトミーコーポレーションが可能とした時間のコントロールは、TT2プロトコルにより施設内だけで可能です。
しかし、かのアブノーマリティはTT2プロトコルの制御を逸脱し、あなた達司令塔の管理人にも影響を及ぼします。
記憶貯蔵庫から一日をやり直したとしても、職員に与えられた影響を拭うことはできないという情報もありますが、定かではありません。」
「失礼、影響とは?」
静かにジョンが挙手する。
管理下に置く上で、最も危惧されるのは、コントロールの効かないことだ。
残る影響によっては、危険性がALEPHすら凌駕することも考えられる。
「詳しい情報は開示されていません。
分かっているのは、TT2プロトコルの一部を制限し、管理不能に陥らせることがあるということです。」
「それだけじゃ、ね…」と、どこからか小さなため息をつく声が聞こえた。この情報を貰うためだけに、この訓練に参加した者も数人いるのだ。
危険と隣り合わせである仕事だということは、ここにいる管理人の誰もが存知していることだが、これだけではあまりにも不足すぎる。
「だから…―――」
さきほどまで静かに微笑んでいた817が、そっと口を開く。
「私たちが"時"を信用しすぎないよう、直接管理をしてみる訓練をしているのですよね。」
817は、目元に陰を落としながらも、そこに座るものたちを安心させるためのような微笑みを見せる。
しかし、彼女自身が何か心得ているものを口にしたような感じもした。
「その通りです。まずは管理人、あなたたちが直接管理を行い、
冷静に処理できるイメージをして頂かなくてはなりません。」
イェソドは頷いて手元の資料をまとめると、音を立ててテーブルでそれらを成らす。
「『時の干渉者』とは、別の管轄の一部の支部の管理人が勝手に呼んだことです。
本当の時の干渉者とは、施設内の時間を利用する我々のことにほかならないかもしれませんね。
…私からは以上です。では、管理人の皆さん、ご健闘を。」
彼はそう言って、モニターをリセットさせると、静かに退出した。
「我々が、時の干渉者、…か…」
サイレンは、フィルターでぼやかせた表情から、感慨深いようにその意味を受け止めた。
しばらくの沈黙とため息が、会議室を満たし、259が席を立った。
「とりあえず戦力バランスだけ整えておきましょうか」
259は今日もポインターを動かして、昨日の反省意見を聞きながら管理人達の配置を行っていく。
彼は連携の取りやすさを優先して、極力支部同士の管理人を一緒にしようと気遣ったが、817が挙手をする。
「我々は別々でも大丈夫です。皆さんのお手を煩わせません」
彼女の隣には、自信満々に微笑む810と、521が居た。
まだ状況や管理人達の技能のすべてを把握してはいないが、彼女たちの発言もあり、E.G.Oの能力を見てとりあえずの配置を整えた。
危険度がばらけて収容されていることを危惧すると、対処できる管理人も分散して配属されることが好ましくなるだろう。
「それにしても、こうやってE.G.Oから見ていくと、結構『魔法の弾丸』を持つ人が多いんですね。長距離で、とても強力ですが…」
『ばーん』
259が確認に『魔法の弾丸』所有者管理人を数えて、危惧性を語ろうとして口ごもった所、333が指で鉄砲をつくっている。
E.G.O『魔法の弾丸』は、長距離でとても高いブラックダメージを与える、優れたマスケット銃だ。
そのメリットに反して、デメリットは"普通に打てば敵味方関係なくそこに居た者を射抜く"という点がある。
「狙撃には自信があります。必ず皆さんを攻撃しないように撃つことができます。
その危険性について、私は問題ありません」
ジョンが淡々と話すが、クルミは少し口ごもった。
「あ、私はどうかしらね…。でも管理指示中心にさせてもらうから、あまり鎮圧には加わらないと思うわ。
それにほら、万が一の時はこれで殴れるわよ」
彼女は、青いストック部分を指さして見せる。確かに打撃は与えられるだろう。
後はブランダーだが、彼は生まれながらにして魔弾の射手だ。威風堂々としている。
唐突に「へへ」と卓の中で726の笑いが聞こえたので、一同は彼に注目する。
彼は赤と黒のオッドアイを、珍しく大きく開いている。
それでも切れ長の瞳に、笑みを浮かべて口を開いた。
「『魔弾の射手』の終幕を知っているかね、君達。
歌劇の最期、狩りの魔王ザミエルをもて遊んだカスパールは…」
「こら、そこで変なフラグ立てない…!」
聞き慣れない口調でそう話すので、何かの真似をしていることはすぐに分かったが、
384がすかさずツッコミを入れ、それを遮った。
726は「なんだよー。緊張を解いてやろうとしたんだろー」と剽軽に笑っている。
それを聞いたブランダーは、今まで見たこともない表情を浮かべていた。

「良いねぇ、面白いじゃん」
先ほどまで、少年のように笑うことができていた彼は、まるで別人のような笑みを浮かべている。
口は笑っているが、目が笑っておらず、大きく開いている。まるで彼の中にもう一人の彼がいて、それが目を覚ましたかのようだ。
片方に照準の文様がある瞳孔は、僅かに光っている。
「どんな終幕があろうと、僕は自分の弾丸と生きるつもりだ。負ける気がしないよ、何者にもね」
周りの管理人達は、息を呑んでそれを見守ると、やがて彼も目を細めて、いつも通り少年のそれで微笑んだ。
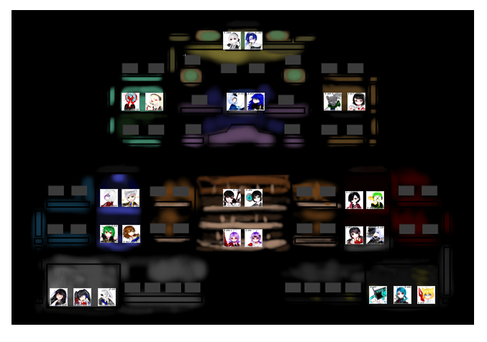
*
『管理人の皆さん。こんにちは。出撃のお時間です。本日も安全に訓練へいってらっしゃい!なお、私物の持ち込みは…――――』
マルクトの声だ。初日にはなかったが、出撃前にアナウンスがかかるらしい。
初日と違う点はアナウンスだけではない。
やがて収容施設に運ばれた管理人達は、初日とは違う光景に目を疑った。
「あれ…?オフィサーが…」
収容施設には、管理人達以外にすでにいそいそと動き回る人々がいた。
彼らには、管理人達のことが見えているらしいが、あまり認識はなく、自らの仕事をこなすために、資料を運んで歩き回っている。
「ちょっと話しかけてみようか…あの、すみません」
懲戒チームに配属された皿面は、なんとなく側を横切った女性のオフィサーに声を掛けてみる。
「…」
オフィサーはとても疲れた表情をしている上に、少し素っ気なく通り過ぎた。掠った感触からして、触れないわけではない。
しかし、こちらから声を掛けても、反応はないようだ。
その瞳は虚ろだ。
「あ、ああ、ごめんねぇ」
皿面はなんとなく謝ってしまったが、オフィサーは確かな生命を仄めかしながらも通り過ぎて行った。
人だ。
確かに、人の感触だが、どこか無機質だ。
「先輩、これって…」
「まるでAIみたいだね。彼らは果たして人なのかな…?」
ラサが言いかけたところで、ウィリーもうなずく。
―――オフィサー。
彼らは部署に配属されているが、管理人達の管轄ではないように、この訓練中もどうやら自分たちの話は聞けないらしい。
いるだけで施設の機能向上などの恩恵は受けられるが、果たして本当にそのためだけに表現されているのだろうか。
「彼らがいるなら、警戒しなくちゃ…」
皿面はモニターを覗き込んで、少し嫌な予感がするのを口に漏らした。
それを聞いていたウィリーも側に寄ってモニターを覗き込む。
「そうだね。今日は運悪く、彼も収容されてるようだよ」
ウィリーが指をさす先は、『笑う死体の山』がいる隣の中央本部チームだ。エリア2の懲戒チーム側の渡り廊下に収容されている。
万が一脱走してしまった場合、人が集中している中央本部チームに先に降りられると、オフィサー達が餌食にされ、
管理人達にも危険な状況に追いやられてしまう可能性がある。
「あの、オフィサーに触れることもできるのなら、避難誘導も可能なんじゃないですか?
こう、無理矢理背中を押したり、パニックになって逃げてるところの向きを変えてあげたり…」
声を掛けてきたのは、ラサだ。ジェスチャーで物を動かすようなしぐさをしている。
少し側の方でソーニャも心配そうな表情をして頷く。
しかし、その問いかけに、彼らはなかなか頷かない。
やがて、皿面はモニターに再び視線を落として言葉を口にした。
「彼らを誘導できるかどうか…わからないけど…。
でも、やってみる価値はあるかもしれないねぇ」
彼は希望を折らないようにそう言ってみせたが、声は全く希望の色を含んでいない。
…内心、不可能な気はしている。
彼女たちの願いは分かる。
自分でも、死人が出ないことにこしたことはないと思う。
しかし、今日の出撃時マルクトのアナウンス、そして昨日は導入されなかったオフィサー。
意図的なものがあるとすれば、昨日までの訓練はただのチュートリアル。
飽く迄も訓練の訓練に過ぎず、本当の訓練はオフィサー達を犠牲にさせてこそ成り立つことになっているのではないか。
考えれば考えるほど、これからが不安になる。
すっ、と、肩にいきなり手が置かれたので、皿面はビクついてしまった。
ウィリーだ。
彼は、皿面の肩を少し撫でるように軽く叩いて手を下ろした。
きっと緊張を解くためにしてくれたのだろう。
しかし、ウィリーの横顔は珍しく微笑んでおらず、口は一文字に結ばれている。
皿面はなんとなく察する。
不可能であるという事を。
*
「……ああー。やっぱ最高やわぁ絶望ちゃん…」
ちゃっかり『絶望の騎士』の加護を受け取ってきた555は、満足そうな笑みを頭巾の下から見せ、情報チームの端末にのしかかりながらに頬杖をついている。
「……」
キャロルはただそれを背後に、モニターを確認しつつ、業務をこなしている。
『貪欲の王』『白雪姫のりんご』中でも早い作業時間で、効率よく済ませる。
ウィリーの勘の通り毎日配置が変わるのは本当で、本日シャッフルされる辺りどうやらリスクレベルも今日から部署に関係ないようだ。
「ああー、1日一度しかいけないなんてつら…
ねぇ、あなたは、愛するアブノーマリティ、いますかー?」
555がゆったりと、キャロルがモニターを確認している横から顔を出してくる。
彼は加護を受け取った分、収容室には出向けない。ただ静かに鎮圧業務を待っている。
「……」
「愛する、や。LOVE」
555がにやにやしながらさらっと言うので、彼女はモニターから目を離し、555の方へ向き直る。
しばらく沈黙して、少し荒げた呼吸で小さく吐き出す。
「…答、ペスト医師」
キャロルの返答に555はしばらく真顔で黙ると、唐突に大笑いし始めた。
彼女はそんな彼を包帯の下から訝し気に見つめている。
「やー、ごめんごめん。まさかここに収容されてない奴だったとは。しかもよりによって、こんにちの訓練で危険対象として話されてる…。
…とは言っても同士ですよ。
アブノーマリティへのひたむきな想いを持つ管理人、のね」
「…否、今回の訓練で危険対象と説明があったのは干からびた胎児であり、ペスト医師様ではない。
懸、ペスト医師様は良いぞ…。少し待ってろ。先に仕事を済ませる」
サティの曲名ではない。
キャロルは、555の意味深な笑みも背後にし、とりあえず業務に戻った。
もうすぐクリフォトの暴走が来る。
同部署に配属された彼にやる気があってもなくても、キャロルは十二分に動けるが、それよりも少しだけペスト医師について語りたく思った。
すごく語りたい。
*
「…『何もない』がいますね」
「ああ、いるな。それがどうした」
安全チームのタブレットを見たサイレンが、冷静に呟くと、1006から素っ気ない返事が来た。
しかし、サイレンは警戒の意味で言葉にしたのではなく、『何もない』が収容されていることに少しだけ嬉しそうなのである。
「私は彼に愛着作業を行ってきますが、脱走だけは避けなければなりません。」
「脱走しても、第一形態の状態で収容室に叩き返す。問題ない。」
サイレンはそれを聞くと、とりあえず頷いて彼を背にして、『何もない』の収容室に向かった。
収容室の前に来て、彼は少し深呼吸をする。まるで久々に会う友人を訪ねるような、そんな心持ちで。
「…彼らにも、できるだけ暴力をふるいたくはない。」
深呼吸の吐く息に混ぜて、すっと彼は低い声でつぶやいた。
オフィサーが背後を通り過ぎていくが、聞こえていないだろう。
入室して、"それ"を見遣る。
大きくつややかな目玉を四つも付けて、大きな口からだらんと垂れ下がった大きな舌、後方には腸らしきもの。
例えるのなら人間の四つん這いに似て、その浮いた腹から、ぽたぽたと彼の足元に何か赤い分泌物が滴り落ちては、透明になっていく。
とても痛々しい様で、息を荒げている。
その荒く小刻みな呼吸は、遊んでもらおうと興奮している犬のようにも、傷ついて震えながら怯えている動物のようにも見える。
サイレンにとって、アブノーマリティは自分たちと同じだ。
実際、管理人達の間では、アブノーマリティは元人間であるという噂が飛び交っている。
殺戮能力があるがゆえに、殺人マシーンになってしまうことがあるだけで、本当は人間と同じ感情表現をしているつもりなのだ。
それが人間に似た怒りや悲しみなのか、愛情表現なのかは誰にも分からない。
アブノーマリティ『何もない』は、不鮮明な言語を話す。
どの国の言葉なのか、不明であるが、時々稀に、誰にでも分かる言葉が聞こえるのだ。
それが人間を真似ているのか、人間であった名残なのかは誰にも分からない。
サイレンは、作業の最後に手を差し出す。
『何もない』は、それに合わせて反射的に、自らの頭部に生えた人の手の面影を残すパーツを、ゆっくり差し出してきた。
本来脱走時には相手を引っ掻いて即死させることもある、凶器たる青い腕だ。
サイレンは、彼のその手に慎重に触れると、そっと握手した。
『何もない』の頭部の、“誰か”の腕は、死人のように冷たい温度を持っていたが、ぎこちないながらに弱々しく、
まるで"握手"ということを、どこかうろ覚えに分かっているかのように、握り返して僅かに上下した。

そして、弱々しく、ほどいた。
彼は、多分知っている。自らのその手で、相手を死に追いやれる力が、我が身に備わっていることを。
サイレンは、人間のいる部屋にするそれのように、深くおじぎをして、収容室を出た。
握手した手には何かぬめった感触がまだ残っている。
*
『もうすぐ一回目のクリフォト暴走がくるね!』
福祉チーム333は、緊張感を持ってモニターを覗き込んでいるが、
ちょっぴり何か楽しみにしているような無邪気さがうかがえる。
もちろん本人にそのつもりはない。真剣な面持ちのつもりだ。
「そうね。こちらには、『銀河の子』『シャーデンフロイデ』『女王蜂』『狂研究者のノート』…
かなり意地悪な組み合わせで来たわね。『銀河の子』から石を受け取ることになったら、今日一日あの子担当よ。
『女王蜂』は結構厄介ね…
『シャーデンフロイデ』はキャロルちゃんに頼めばいいのかしら?」
クルミが333と一緒に画面を見つめて、収容室を確認していく。
「いや、万が一の時シャーデンフロイデは、僕が行っても良い。そのまま見つめなければ脱走もしないかもしれないが、
エネルギーが低下してしまうと、困るのだろう?」
521が腕を組みながら、壁にもたれかかってそう言うので、彼女も「分かったわ。お願いね」と頷いた。
『かんりにんは、女王蜂の作業も得意だよ!』
333が明るい声でそういうが、彼女はそれが少し心配になってしまった。
何しろ『女王蜂』だ。
かなりの攻撃力を持ち、管理が難しい存在で、作業に来た職員の命を容易く奪うこと、充分に施設を潰せるだけの感染力が恐れられている。
そして、その危惧性を巡らせてクルミは、苦笑しながら333を見つめた。
「333ちゃん…気を遣わなくても大丈夫よ。その、無理しないで」
彼女が口ごもりながらそういうので、それを聞いた彼は一瞬真顔になった。
やがてみるみるうちに、それに対してショックを受けた表情になって小刻みに震える。
『…くるみ、かんりにんをこども扱いしてる?かんりにんは平気…どんなアブノーマリティも平気だ…!』
「ち、違うわよ、大丈夫。ありがとう、お願いするわ」
クルミは慌てて333を宥める。そうだ、彼が防具に身に着けているE.G.Oは、『スズメバチ』。彼とて初見ではないだろう。
初日も『地中の天国』へ真っ向から世話に行けるほどの、生き残れる根拠を持っているのだ。
彼女から見て、333は青年なのだが、立ち振る舞いが無邪気で、無駄に心配をしてしまっていた。
「あたしはどうしよっか?」
声を掛けてきたのは810だ。彼女はかなりの鎮圧狂だ。
彼女は足も速く、どこへの部署にも協力的に動けるだろう。
「810ちゃんは、ここで一緒にモニターを監視して待機してもらっていい?
もしかしたら他の部署で鎮圧が必要になるかもしれないから、そこに走って鎮圧に参加して。」
「補欠かー。でもいいよ。状況に応じて自由に動いてOKってことだね」
810は、イタズラめいたウィンクをクルミにしてみせた。
クルミもウィンクを返す。
「そういうことよ。さて、慎重に行くわよ」
『おー』
彼らがしばらく待っていると、やがてクリフォト暴走直前に収容室へと入る合図が館内に響いた。
「"こちら抽出チーム、259です。今からこちらに収容されている『夢見る流れ』に愛着作業を行います。
これでクリフォト暴走に切り替わりますので、皆さん準備をお願いいたしますね"」
259の声だ。間もなくして、彼は宣言通り収容室に入ると、クリフォト暴走を知らせるブザーが施設内に大きく響いた。
結構耳障りな音である。
訓練切っての、初めてのクリフォト暴走だ。
管理人達はそれぞれの部署で、モニターを確認する。
「521くん!」
「了解」
521は掛け声とともに、シャーデンフロイデの収容室に向かっていった。
福祉チームは、今は他に急を要することはない。
『なー』
クルミが胸をほっとなでおろす横で、333と810は少し退屈そうにしている。
しばらくして333も『行ってくるー』と言い残し、自ら『女王蜂』の洞察作業へ行ってしまった。
そして最高の状態を示してみせて、カメラに向かって微笑んで見せる。
セピラルームに戻る前の彼が、モニター越しにちょっと『ドヤ』とアピールするところが可愛い。
*
やがて二日目のエネルギーノルマも残すところ三分の一になった。
しかし、その前に黎明の試練が来る。"緑青"の黎明だ。
「緑青といえば、あのロボットですね。オフィサーさんがこんなにいます。二次被害が起こる可能性がありますね」
教育チーム、モニターを確認し、いつでも向かい打てるように準備している817は、ふとそんなことを呟いた。
冷静に呟きながら、手元にはやがて赤い林檎の付いたケーリュケイオンが現れる。
「確かにな。…奴らの攻撃射程は短いし、動きも遅いが…俺たちからオフィサー達に避難指示は出せない。
危惧すべきは、死体の山だな…。でも、なんとかやってみせよう」
アルジャーノンはそう答えて、案山子の収穫祭を手にする。
爪の先が妙に赤茶けた、鍬のようなガーデンフォーク型の武器の柄を握りしめて、少しだけ指先に緊張が見える。
「"こちら記録チーム配属、ジョン・ドゥです。今から『雪の女王』に作業を開始、クリフォト暴走による試練を起因とさせます。
オフィサーが襲われないとは限りません。ショックを避けるため、試練の攻撃行動を見るに堪えない管理人は、避難お願いします。
連絡終了後カウント8秒、モニターから緑の試練がどこに来るか確認し、充分に構えて下さい。"」
ジョンが放送を切ると、全員は武器を手にして構える。
各部署では、管理人の一人がモニターを確認、他の管理人はモニターを確認している管理人を守るようにして、セピラルーム内を警戒して待った。
このメインルームにいきなり現れないとも言えないのだ。
それにしても、モニターが与えられて随分作業も落ち着いている。
これが無ければ、本当に司令塔で全体を見渡す管理人の声を頼りに行動するしかない。
普段職員たちはこのような状況にも狼狽えずにやってきたというのか。
やがて8秒経ったあたりで、ジョンの宣言通り、クリフォト暴走を告げる耳障りなブザーが響き、警笛のような音が施設を震わせる。
『きた!行くよー!』
扉を見つめていた333が叫ぶ。
福祉チーム扉が唐突に開いて走ってきたのは、パニック状態のオフィサーだ。
かなり迫真に叫んでいるが、死なないで逃げてくれるだけでまだいい。
直後鉄を打つような、耳をつんざく音を立てて、彼を追ってゆっくり入ってきたのは、すすけた銅色の機械だ。
モニターを見つめていたクルミも、すぐにマスケット銃をストック部分で構える。撃つ気はない。
人の顔程の大きな歯車の噛みあう音。細い鉄の足を鳴らし、不気味な目を光らせたそれは、何かを模った形。
人に似せて何もかも違う、肘の先からは錆色の、剣と呼ぶには不格好の、裁断のための鋭利な鉄片がこちらを向いている。
333は長距離からの攻撃が可能で、浮遊するE.G.Oを彼が操ると、炎が空気を焼く音を立てて宙を走る。
炎の羽は火の粉をまき散らしながら、撃ち込まれていく。
810が走り込んでジャスティティアで強く打撃を与え、521は背後からミミックを振りかざす。
耳を裂くような轟音を響かせ、まるで一瞬にして、福祉チームに現れた錆色の機械は膝をついて動かなくなった。
あまりにも素早かったので、クルミはしばらく驚いていたが、810の言葉で我に返る。
「次!どこにいる?」
「…記録チームの機械がこっちに向かっているわ!」
「了解、あたし行くよ!」
彼女はそう言うと、すぐに扉を出て行った。次いで521もミミックを担いだまま走っていく。
333は周りを警戒してどこから何が来ても良いように、クルミを守るように立っている
「よっし、待たせた…!」
810が駆けつけた時、メアリーが小さな身体でひとり立ち向かっているので、彼女はすぐさま応戦する。
メアリーひとりでかなり削れていたらしく、810が一振りするとすぐにそれは倒れた。
「助かり…ました。」
メアリーが小さな声で呟くので、810は「よーしよしよしよぉく頑張ったな」と、少女にしてあげるように、頭を撫でる。
そして、少し遅れてきた521にガッツポーズをしてみせるのだった。
*
「こちらに来ては…!」
懲戒チーム渡り廊下、試練と対峙したソーニャが、オフィサーを誘導しようとしたが、彼らは全く聞いていない。
ラサが驚愕しつつも、一緒に誘導しようとしたが、彼らは自身の仕事であるかのように、
拳銃で対抗し、パニックになって逃げまどい、錆びた機械に打ち倒される。
彼女が、オフィサーを逃がそうと腕を掴んだにも関わらず、オフィサーはそれを乱暴に振りほどいてまで、煤けた機械に走っていったのだ。
「…!ソーニャ先輩…!ダメです!戦いましょう!!」
ラサがE.G.O『くちばし』である拳銃を取り出して、構える。
オーバーキルを見せつけられ、まき散らされた残骸は、彼女たちの目にはフィルターによってコミカルなものに見えるように調節されているが、
目の前だとショックも大きく、ソーニャは怯えながら二丁銃『崇高な誓い』を向けた。
「君達は下がっていて、後方から支援を!」
ウィリーは緊張感を持った声で伝えながら、舞い出るようにして、マスケット銃『ラエティティア』を突きつけた。
彼はマスケットにしては、かなりの至近距離から何度も放ち、相手を引き付けては身をひるがえして、攻撃を軽やかに避けている。
前線に立って引き付けるのは、これ以上進ませないためだ。
「ご、ごめんねぇ!…あッ」
遅れてきた皿面は、懲戒チームのモニターを見ていたが、少し震えていたためか走り寄ったところでつまづき、抱えていたE.G.O『ブラックスワン』が彼の手の中ら躍り出た。
滑り出た『ブラックスワン』は美しく弧を描き、錆色の鉄の歯車に激突、やがて動きを止めるまで至った。
「わぁ、やるね皿面くん」
ウィリーは転んだ皿面に、優しく手を差し出す。
「え、ええ…ただ転んでしまっただけだよ…ありがとう」
彼は、お面の下で明らかに照れたような声で苦笑し、ウィリーの手を恥かしそうに取って立ち上がった。
「運も実力のうちって言うからね」
彼が皿面に微笑んでいると、ラサも駆けつけて、転がる『ブラックスワン』を拾って差し出した。
皿面は恥ずかしそうにこめかみをかいて「ありがとうラサくん」と受け取る。
とりあえず、鎮圧が完了したところで、一同がホッとしているとき、ソーニャが座り込んでいることに気付いた。
「ソーニャくん?大丈夫?」
皿面がその場から、遠く彼女に声を掛けたが小さく「え、ええ」と呟くだけだった。
彼女が力なく座っているのは、鎮圧が完了した安堵だろうか。しかし、視線は度々その、"コミカルな残骸"に向けられている。
むしろ、コミカルに調整されることに悪意を感じるのが正常なのだろうか。
床にも壁に飛び散っているものは、例えようもなく、身も蓋もない。
今日、この招集訓練での、初めて遺体が出たのである。
ラサは、ソーニャと、その傍にまき散らされたオフィサーの残骸を見ながら、振り払われた手の感触が急に思い出された。
彼女にとって、実際の収容所、フィルター越しの遺体を見るのは初めてではなかったが、
先輩と彼らを避難誘導しようとした試み、それがあらぬ方向で破れたことに、少しだけ暗澹とした気持ちに苛まれる。
重々しい雰囲気が立ち込めた時、ラサは沈黙を破って胸を抑えた。
「…あ…ああもう!!心臓がヤバい…!!!ソーニャ先輩!大丈夫ですか?」
ラサの言葉に、彼女は笑顔で応えたが、上手く力が入らないらしい。表情は不自然だ。
ウィリーもゆっくり近づいて、「立てるかい?」と手を差し出す。
ソーニャは小さく謝りながら、手を取って立ち上がった。
*
抽出チームの長い廊下で、レストは舞うように長身の刃を打ち鳴らす。
暗い廊下で金属のぶつかり合う音と共に、眩い火の粉が飛び散った。
火の粉は辺りを瞬時に照らし、視界を切り取るようにしてその度に、機械人形の歯車を吹き飛ばしていく。
力加減もなく、ただそこには足を崩した錆色の鉄だけが残った。
抽出チームの廊下は、暗がりなので、容赦なくやらなければ、駆動可能のまま放置してしまうかもしれないからだ。
「大丈夫ですか?」
「問題ない」
彼女は細身の剣を、錆色の鉄から引き抜いて、セピラへと引き返してきたところだ。
259が追いついた頃にはすでに終わっていた。
彼女はセピラルームに戻ると、すぐにモニターを確認する。
レストが見つめた先は、誰もいなくなったコントロールチームと、その周辺だ。
彼女には、まだ危惧していることがある。
そしてその予感は的中していることを、目の当たりにした。
むしろ、予感が的中していたことに、息をついた。
(いや、犠牲が人でないなら、まだ良いか…
くれぐれも、誰も巻き込まれなければいいがな…)
彼女の視線の先にあったのは、物凄いスピードで動き回る、青黒い点と、光りだった。
*
「アルジャーノンさんは待っていてください。すぐ片付けてきます!」
「いや、俺も行くよ!」
錆色の影を見つけた817は素早く動き始め、アルジャーノンもすぐに行動を共にしようとした。
彼女は早い。
しかし、817が教育チームセピラの扉を出て下の廊下に出た時、すでにそこにはブランダーが立っていて、
今しがた鎮圧を終えた所らしかった。
なおも、鉄を擦るような激しい音が響いてくる。
マスケット銃とは言え、そんなに連射できるのか、そこまでやる必要があるのか。
錆色の機械人形はすでに稼働を止めているにも関わらず、意図的に何度も弾丸を撃ち込まれ、
そしてあっという間にスクラップになっていく。
「…ブランダーさん」
彼女が彼に声をかけようとしたところ、すぐそばで細い腕に引かれる。
シャオだ。二人とも今日はコントロールチームに配属されていたはずだが、ここまで降りてきて手伝ってくれたのだろうか。
「…817さん、今のブランダーに声を掛けちゃダメです…」
シャオはきょうだいの動きをじっと見つめている。
817もその視線の先を見てみると、ブランダーの表情はまた、少年の顔ではなくなっていた。
冷たく、青い。明らかなる殺意。
スクラップを何度も足蹴にして、魔法の弾丸を放つ。その度に飛ぶ青い火花。
鉄の焼ける匂いが立ち込めた頃には、彼は飛び去るようにその場を後にしていった。
「おじゃましましたです」
シャオは、817にそう告げると、颯爽とその後を追っていく。
やがてアルジャーノンが駆けつけた頃には、スクラップを目の前にし、立ち尽くすしかなくなっていた。
「…これまた派手にやったね。き、キミひとりでやったのかい?」「…いいえ」
今日はあまりにも、彼の意外な一面を見せつけられ過ぎている。
*
「…先ほどの話だが」
キャロルは錆色の機械を一瞬で片付けてセピラルームに戻り、555に話しかける。
555も応戦しようとしたが、出た所ですぐに終わっていたので、すぐに引き返してきた。
「…なぁに?」
555が不敵な笑みを浮かべて振り返る。
どこかわざとらしく友好的な声を作ってみる。
秒で片付けられて、彼も退屈していたところだ。
「…唯、ペスト医師様はいいぞ。」
「せやな。絶望ちゃんもいいぞ。」
合言葉のようにお互いに一言ずつ伝えると、両者は示し合わせたかのように、口の端をもちあげる。
「ペスト医師はマジで、最高だ。良い香りだし埋もれるとふわっふわで、すごいんだ。
先ほどお前はLOVEと言ったなまさに私にとってLOVE愛する者はペスト医師である故に私のLOVEペスト医師であるのだ分かってくれるな?」
「わかるで。そして私のLOVEは絶望ちゃんなのだよ。
あの切ない表情も祝福を授ける時のあの子の表情は女神の如くしてあたたかいむしろ女神」
「ああ、収容室でしか、触れ合えないなんて、なんて勿体ないことだ」
「だがそれがいい」「是、それな、愛おしい収容室マジ宝箱」「だれうま」
キャロルは珍しく微笑んでいる。
ジャスティティアの包帯を目に巻かれているので、表情の全貌は確認できないが、ここに来て以来、興奮しているかのようだ。
対して555も、やっと話のできる奴が来たと、アブノーマリティに対する愛を語ることができる。
各々の推しアブノーマリティについて語り合う様は、成り立っていないように見えるが、実はお互いにとってとても満足できるものだ。
アブノーマリティに対する愛情を否定するAIは、今この場にはいない。
それどころか、お互いの心を肯定し合える管理人に出遇えた。全力で同意しあえる。互いに聞いてもらえる。
アブノーマリティに対する愛情を、公に語ることができる場面は大変貴重なのである。
―――ここに奇妙な同盟ができた。(できていません)
*
「つまらん」
黎明の試練なんて、こんなものである。
1006が安全チームのセピラに戻ってきたのをサイレンは佇んで見守っていた。
1006にとって、今日同部署配属の彼が動こうと動くまいと、どちらでもいい。
邪魔さえしないでくれれば、別にどうということもない。
サイレンにとって暴力は苦手な部類だ。
その対象が人間であってもなくても同じ。
手に残ったままの『何もない』の握手の感覚をリフレインしながら、サイレンはじっとモニターを見つめていた。
破壊の意味を感じられない彼に対し、本日同部署になった1006は鎮圧に赴くことを衝動としており、
ある意味良いバランスの取れた組み合わせではある。
確かに、サイレン自身も武器を手にして、いつかアブノーマリティや訓練を攻撃せねばなるまい。
サイレンは、その時は自分に迷いが生じないように、自分にできることをやろうと心に決めている。
*
「終わったよー」
ミカンが中央本部チーム、エリア3の壁付近で錆色の機械人形を討ち果たしたところ、
遠くから支援していた本体と、726、384に大きく手を振った。
彼女はあの重量のミミックを操り、鮮やかな太刀筋ですぐに片づけてしまったのにも関わらず、
直後、優しい少女の笑顔を送っている。
本体が足を止めたのを背景に、726と384はそれでも彼女に駆け寄る。
彼女の努力をねぎらうためだ。
384が優しく微笑み返して軽く会釈をする横で、726はフレンドリーに手を振る。
「お疲れ様です。ミカンさん」
「ミカンちゃん、やるねぇ」
「えへへー」
ミカンも嬉しそうに照れながら微笑むむと、スピードを落として歩いてくる本体に気付いて、彼女は再び手を振る。
本体もふと小さく手を振って応える。
彼の表情は硬いが、とりあえず、黎明の試練を無事に終えられたことには安堵している。
「良い子じゃん、なぁ、あんた」
「…!どこから湧いたんだ!」
さっきまでミカンをちやほやしていた726が、いつの間にか本体の隣にまで戻ってきている。
口元には意味深な笑みを浮かべ続けて、遠く、真っすぐミカンを見つめている。
「おれは、あの子を応援してやりたいね」
「そりゃどうも。…おーい、戻るぞ贋作ー」
本体は、彼の遠い眼差しも、真に受けずに素っ気なく相槌を打ち、ミカンを呼ぶと踵を返して行ってしまった。
ミカンは、384ともすぐに打ち解けたらしく、二人は手を振り合っていた。
*
やがて差し掛かったのは、再び訪れたクリフォト暴走だ。
「ったくまた暴走か!今良いとこやっちゅうのに…!」
555が落胆するように、暴走を告げるブザーに文句をつけた。
ここ一番自分の気持ちを人に打ち明けて、少しハイになっている。
「応、もっともだが問題ない。すぐに終わらせてこよう。」
キャロルがするりと立ち上がり、先ほどまで同じくハイに語っていた表情をいつもの冷静なそれに変え、セピラを出て行った。
555がモニターを見ると『貪欲の王』のクリフォト暴走カウントが表示されている。
しかし、キャロルは対して、それを確認しなくても分かっているように颯爽と『貪欲の王』収容室へと向かっていったようだ。
555は、『絶望の騎士』の加護があるため、もろもろの保護ステータス(主に彼の気分値)が上がっているが、収容室には一切入れなくなっている。
もちろん、彼は『絶望の騎士』に忠誠を誓った身だ。「悪いね」と作業に向かう彼女を見送る。
「…さあ、続きといこうではないか。」
「はやっ」
やがてほんの数秒しか経っていないのにも関わらず、キャロルは宣言通りすぐに済ませて戻ってきた。
*
「父様…!」
心配そうにモニターを見つめていたシャオが小さな叫びを漏らした。
ブザーが鳴り響き、コントロールチームのセピラで、ブランダーとモニターを見つめていたが、彼らの見るところは
本日教育チームにあたる、父親の収容されている施設だ。
そして、シャオの父と同義である『死んだ蝶の葬儀』こそ、今回暴走に選ばれた人物でもある。
「"こちら教育チーム、817です。シャオさん、もしよかったら『死んだ蝶の葬儀』に作業をしていただけますでしょうか?"」
817の温かい声が、優しく唐突に響いてきた。
「良かったなシャオ!」
「…!!!いいのです…?」
シャオは口にためらいを少し含みながらも返事をする前に、嬉しそうにこの父親の収容室に直行した。
代わりにブランダーが、817に返事をする。
「"こちらコントロールチーム、ブランダー。シャオの答えはイエスだよ。今父さんの部屋に飛んで行った。
きょうだいを気遣ってくれて、ありがとな"」
少し照れくさそうにしているが、彼もシャオをとても大切に思っているらしい。
心配ではあるが、彼らは親子だ。きっと大丈夫。ブランダーはそう言い聞かせて、モニター越しに、自身の父親を確認した。
その眼差しは深く、寂し気だ。
"また、君か。"
「父様」
収容室に入って少し寂しそうに声をかける。
彼らきょうだいにとって、収容室は収容室ではない。応接室である。
警戒色のラインも何も関係ない。
「父様…洞察作業よろしくなのです!」
シャオはそう告げると、ぴったりと身を寄せて、分岐点の先にいる父親の顔を見上げた。
彼の暗い虚空の瞳に、『死んだ蝶の葬儀』の白い翅のかんばせが映り込み、光りが宿るようである。
"……"
今日はいたって通常通りに業務しているらしい。
いや、ぴったりと身を寄せている時点でそれは、少し違う。
「……父様は、」
彼は、真っすぐに『死んだ蝶の葬儀』を見上げて、口を開いた。
「父様は、大切な人いますです?」
なんとも藪から棒だ。
「しゃおの父様には大切な人がいたです。父様にも大切な人がちゃんといるです?」
どうも、今日はシャオも訓練施設の"父様"と自身の"父様"を区別して呼んでいるらしい。
"さて、私に大切な存在があるとすれば、皆様の抱える、必ず得られる『帰る場所』でしょう"
『死んだ蝶の葬儀』はさらっとそう言ってみせた。
もちろん彼の本心である。
シャオはそれを聞くと意外にも、安心したように彼の胸元の手に触れた。
「しゃおの父様も同じことを言っていたです。大切な人のいるところが、大切な『帰る場所』だと。
…やっぱり、父様は父様なのです」
シャオは安心して、そっと彼の胸に自分の額を当てると、しばらくして収容室を後にした。
今日は大人しく退室してくれるらしい。
「父様、また来るです!」
彼が精一杯浮かべている儚い笑顔は、いつしか彼の蝶が見せてくれたどこかの自分と、
そのどこかの自分の『大切な人』とよく似ていた。
『死んだ蝶の葬儀』は、それをそっと見送る。
「817さん、ありがとうです」
シャオは、安全チームのセピラに立ち寄って、自分に指示してくれた817に挨拶をしに来た。
「シャオさん。ううん、良かった。」
817は優しくうなずき、シャオを送って行った。
その虚空に見える瞳は、少し輝きが増している。
父親から何かを教えてもらったのかもしれない。
*
福祉チームでは、ブザーが鳴り響くや否や、モニターを遠目に見ていた521が素早く動き、
再びシャーデンフロイデの収容室に向かっていった。
クルミはそれを見送って、すぐにモニターに視線を戻した。
「521くん、やる気満々ね。『女王蜂』もクリフォト暴走カウントが始まったわ。333ちゃん、またお願いできる?」
『おー!いくぞ!』
333は、片手を大きく上げて少し嬉しそうに返事し、軽い足取りでかけていく。
それを見送った810は、クルミとモニターを見つめて少し退屈そうだ。
「810ちゃん、ほらここ。ここ見て!中央本部チームのカウントも始まっているのに、人手が足りないで『大鳥』ちゃんに誰も向かっていないわ。
お願いできるかしら?」
クルミが指を指したのは、福祉チームの真隣りである中央本部チーム下部の『大鳥』の収容室だ。
どうやら、他の中央本部チームの暴走が中心的に起こり、そこに配属された四人全てが出払っているらしい。
「ほんとだ!お隣の部署まで確認するなんてクルミもやるね!あたし行ってくる!!」
810もようやくここで作業ができると、どこか嬉しそうである。さらっとユースティティアのコートを翻し、鼻歌交じりに転がるように走っていった。
手を振って見送ったクルミは、少し緊張感を持った面持ちでモニターを見つめる。
「さて…次は『深紅の試練』ね。あの試練の場合、モニターを常に監視していないといけないわ…。」
彼女が見るところ、エネルギーノルマ達成の直前、この試練は来るだろう。
(…何かしら。胸騒ぎがする)
試練が開始してもごり押しでエネルギーを貯めてしまうのも手段だが、
無理をしてエネルギーを集めるより、余裕を持って確実にノルマを達成した方が良いかもしれない。
何しろ深紅の白昼試練『肉体の調和』、奴の動きは素早く、不確定要素も多い。
他の管理人の目前で現れれば、交戦は免れないだろう。
オフィサーが犠牲になった時の、『笑う死体の山』の脱走も危惧される。
クルミの中で、多くの可能性が交差した。
何やら、訓練二日目で、結構ハードルが上がったように感じる。
*
「とうとう来ちゃいましたね。『深紅の試練』。」
ラサが、少し緊張したようにざわつく。
試練が本日二度目。おそらくこれが本日最後となるだろう。
「ラサくん、よかったら今回君が起因作業に行ってみる…?」
「え…!あたしですか!?」
皿面の言葉に驚愕しながらも、彼女は少し嬉しそうだ。目を輝かせて引き受ける。
というのも、こういう重要な役割を、先輩に任せてもらえるのが嬉しいようだ。
「じゃ、じゃあラサ、行きまーす!」
ラサはどきどきしながらも、モニター越しに試練直前の知らせを放送した。
「"こちら懲戒チーム、ラサです。今からこちらに収容されているヘルパーちゃんに作業を開始します!
『深紅の試練』が始まりますので、皆さん、よろしくお願いします!"」
*
「よっしゃ、俺の獲物だ」
1006が、放送を聞き終えて薙刀を構えた。
『肉体の調和』はどこに現れるかわからない。
しかもすぐにどこかに走って行ってしまう。
初日から鎮圧行動をとりたくて仕方がない1006も、この試練であれば、何かしら奴らを叩き潰すチャンスをくれるだろうと、気合いを入れている。
やがてブザーが鳴り響くと同時に、同部署でモニターを確認していたサイレンの声がする。
彼がいち早く出現場所を見つけた。
「出現を確認、情報チームエリア2です」
「了解」
1006はサイレンにそれだけ告げると、セピラを滑るように抜けた。
情報チームの下の階なら、ここからとても近い。
すぐに駆け付けた1006は、標的を確認し、薙刀の刃先を構えて走っていく。
銀の足が音を立てて床を蹴る。
『肉体の調和』は、見るもおぞましい姿で、いくつかの白い顔らしき部位を付けた赤い身体を、蛇のようにくねらせ四つん這いで走り回る。
赤い体液を溢しながら噛みつきにかかる。さも、びっくり箱のピエロの顔が飛び出すかのように、不安定で素早い動きが繰り出されるのを、
1006は避けながら切りつけた。
体質状、生まれつきの視力を補うために、他の感覚がフルで稼働する。
腐った血に似た異臭が嗅覚を支配しても、殺気を察知する感覚、その異形の顔が振り下ろされる前の、瞬時に流れる勢いを示す微量な風。
察知できる限りのすべての僅かな情報で、あらゆる先を見越す。
「クソっ、降りる気か…!」
次の刃を向ける前、それを察知した直後、奴は情報チームエリア2のエレベーターを使って下に降りた。
中央本部チームだ。
すかさずそれを追う1006の足音が、高く響いた。
中央本部チーム上部に居たオフィサーがどんどん翻弄されていく。
「な、726…!!奴がこっちに向かってる!懲戒チームに向かわせてはダメ!1006さんと挟み撃ちにするよ!」
「りょーかい!」
384がモニターを確認して、少し怯えながら叫んだ。冷静さを保とうとしている。
ここで逃がしては他の部署にも被害が及ぶ。
384は構えて腕を振り下ろす。煌めきながら走っていく星の音は、何度も『肉体の調和』の顔に撃ち込まれたが、
相手は呻くように身体をうねりながらも、こちらへと突進してくる。
飛び散る赤は、生々しい音を立てる。
恐怖。
フィルターのおかげで、いくばくかコミカルに見えるようになっているが、対面するとすごい迫力だ。
しかし、ここで退くわけにはいかない。
奴の後方からは1006も走ってくる。大丈夫だ。
すぐに走り寄った726も、ダ・カーポの大鎌を振りかぶって下ろす。
726の顔にはいつもの笑顔が張り付いたまま『肉体の調和』と応呼するように、大鎌の描く上弦の月と共に吊り上がる。
彼もまた、さながらカーニバルに参加しているかのように。
やがて『肉体の調和』の標的は、726になった。
何度も身体をくねらせて、人のそれとは全く違う不気味な四つん這いで、大きすぎる顔を何度も726にぶつけるようにして大口を開ける。
その度に、726はダ・カーポの大鎌を足元の白い顔に削ぎ入れ、照準をずらすように仕向けた。
奴の腹ばいの下には、みるみるうちに謎の赤い体液が滴り落ちて、広がっていく。
その間も背後で連撃に切り付けていた1006は、そのサソリの尾のようなとりわけ大きな顔の付いた首をついになぎ倒した。
その瞬間である。
「おおーっと?」
726が奴の挙動に気を向ける。
今までその場にとどまっていた『肉体の調和』は唐突に動き始め、その場を突っ切った。
「…!うそ、こっち来るの…!?」
384が距離を保ちながら、後ずさりして、なおも星の音を操り続けた。
近くにはすでに負傷して動けないオフィサーが倒れている。恐怖はあるが、引き下がるわけにはいかない。
これ以上侵入を許しては、懲戒チームに収容された『笑う死体の山』の脱走と、遺体の連結を招きかねない。
「…ッ!!」
奴の動きは素早く、折れた尾を振り回し384を投げ飛ばした。素早くガードの姿勢を取ったが、衝撃は大きい。
飛ばされた384は、慣れない受け身を辛うじてとりながらも、すぐに体制を立て直してその背後を追った。
「大丈夫か?」
「平気…!」
726の問いかけにも、384は即答し、痛みをこらえて走る。
周りを飛びまわる星の音も、まるで彼を心配するかのようにきらりと回った。
少し速度は落ちるものの、すぐにガスで修復され始めていくのを感じる。
そこに、1006も追い越すように張り込んできた。
『肉体の調和』を追って、やがて懲戒チームのエリアまで来てしまった。
そこには、まさかの作業を終えて収容室を今出てきたばかりのラサがいた。
「ラサさん…!」
384が声にならない声で叫ぶ。
「…!…!?マジ…!?ヤバいヤバいヤバい!!」
ラサは驚いて口を手で覆ったが、すぐさまE.G.Oくちばしを手にして構えた。
彼女とて、今まで実践を積んできた若き実力者だ。反応は早い。
一本道の通行路にて奴と対面する。
くちばしのすばやいリロードもあり、連射された弾丸が何度も奴の身体を射抜いたが、それでもまるで動きが鈍らない。
じりじりと不気味にうねりながら、彼女への距離を縮ませる。
「ラサさん…!逃げて…!」
384が叫んだ。しかし、彼女がそれを聞きとっても、銃口を向けたままだった。
「きゃっ…!!」
『肉体の調和』の折れたままの鎌首が大きくスウィングされ、突き飛ばす。
幸い急所を外させたものの、衝撃はすさまじく、彼女の軽い身体は遠くまですべっていく。
同時に、ラサの身体から、携帯電話がこぼれ落ち、乾いた音を立てて転がる。
大きく吹き飛ばされた彼女の身体は、通行路をすべり止まった。
「…っ…」
少し遠くの方で、ぼんやりと白く光ってみる羽のストラップ、自分の携帯が転がっているのが見える。
『肉体の調和』は、サソリにも似た巨体を未だ進軍させ、確実にこちらに向かってきている。
その節々からたれ流されている謎の赤い液体が、みるみる道を染めていき、やがて白く光る小さな羽を飲み込もうとしていた。
少しずつ身体を起こして、くちばしを向ける。しかし腕が震えて、上手く照準が定まらない。
「ラサさん伏せて!!」
384が駆けつけて『肉体の調和』の隙を掻い潜り駆けつけた。
緊張感のある声で叫ぶと、384は即座に彼女を庇うようにして覆う。

「いっくぞー、そぉーっい♪」
同時に726の剽軽な声が響いてきたかと思うと、突然『肉体の調和』は弾け飛び、それと同時に何かが高速で回転しながら、頭上を横切っていった。
「ダ・・・ダ・カーポ・・・?」
E.G.O『ダ・カーポ』。微かに捉えたシルエットは、間違いなく音符の形をした大鎌だ。
それは回転しながら青い軌道を描き、やがてつきあたりの扉上部に突き刺さった。
「よし、こぼれ出たクズに備えろ!」
1006は、標的が倒れたことを確認するや否や、そう吐き捨てて踵を返した。すぐに戻らなければ、『開始の歓声』を見逃すかもしれない。
同部署のサイレンは、鎮圧にあまり乗り気ではないし、何よりもぶった切りたい彼は、すぐに駆け上っていく。
384が急速な出来事に、とりあえず一息をついた。
「……ラサさん、急にごめんなさい。大丈夫ですか?
もう!いきなりE.G.O投げるなんて!!
ラサさんを覆うのに間に合わなかったらどうするの!!」
彼は少しラサを気遣ってから、すぐに立ち上がって726に怒号を飛ばし始めた。
「なんだよー、お前の動きで間に合うって分かってたから投げたんじゃねえか。」
「他の管理人さんを驚かせちゃうでしょ?なんでいきなり投げるの!」
「なんか手頃そうな気がしてな。助かったから良いじゃんー」
726は相変わらず、飄々と相槌を打っている。
よく見ると、384の手はこぶしの状態で小さく震えている。
「…あ、あの!!384先輩、726先輩!!ありがとうございます!!助かりました!!」
ラサはとりあえず、自分の身がお陰で助かったことを伝え、二人の口論を終わらせようとした。
いや、果たしてこれは口論なのか。
384も驚愕のやり場を、文句の形で発散しているだけで、内心はとても安堵はしているようだ。
彼女の言葉に、ハッと我に返った384は少し恥ずかしそうにしている。
「そ、そうですね…良かった。
ほら、1006さんも戻ったし、私達も『開始の歓声』を叩きにいかないと…!!」
384が726を促すと彼は「へいへい」と仕方なさそうに、扉の上部に突き刺さったままのダ・カーポを回収しようとした。
「きゃぁ!」
突如扉が開いて小さな悲鳴を上げたのは、エレベーター内にいたソーニャだ。
ウィリーもいる。どうやら深手を負ったと思ってラサを迎えに来たらしかった。
「おおっとソーニャ嬢!これはこれは失敬ー!
じゃあまたなー!ラ・サ・ちゃーん!」
726がダ・カーポを掲げたまま跳ねるようにして、身軽に手を振って去っていくのを、ラサは「は、ハイ!」と、上体を起こしただけのまま会釈した。
回復促進ガスによる修復力により、少しずつ身体が動くようになってきた。
「ラサさん…!」
「先輩!あたしは大丈夫です!!それより『開始の歓声』を…」
ラサはソーニャに肩を借りながら、よろめきながら立ち上がる。
「今、セピラで皿面君が『開始の歓声』達の場所を確認しているよ。…これキミのだよね?」
「…!!」
ウィリーがいつの間にか、残骸の側で転がっていた携帯電話を拾い上げきたらしい。
あれだけの衝撃、量の残骸が散らばっていた側に転がっていながら、幸いにもそれは汚れていないようだった。
ウィリーが気を効かせて拭いてくれたのか。いや、そんな暇あったろうか。それどころか、傷一つない。もしや回復促進ガスの修復対象だったろうか。
「…あ、ぁああ……良かったぁ………ありがとう、ございます…」
ラサはそれを受け取ると安堵して小さくため息をついた。
「"ウィリーくん!懲戒チーム下の廊下に『開始の歓声』二体来たよ!『地中の天国』収容室ッだだ大至急鎮圧に向かって…!!
ソーニャくんは、ラサくんを保護して一緒にセピラまで戻ってきて…!"」
突如懲戒チームエリア内に、皿面のボイスが流れた。
「了解!」
ウィリーは、軽い身のこなしでさらりとエレベーターへ乗り込んでいった。
それにしても皿面の声は、随分震えていたようだ。
「"ラサくん、キミを危険な目に遭わせてしまったなんて…ごめん、僕の責任だ…
本当に、本当にごめん…ごめんね…"」
懲戒チームのスピーカー越しに、さらに小さく震える皿面の声が聞こえる。
「そんな…!このくらい平気ですよ!なんともありません!」
ラサは思い立ってその場で応えたが、ソーニャが肩を貸したまま「大丈夫、戻って皿面さんにちゃんと伝えましょう」と、微笑みかけた。
部署ごとに連絡することもできるようだが、ここからの返事は届かない。
ラサは強く頷いて、ソーニャの肩につかまりながら、セピラに戻った。
*
「…二体か」
抽出チームのほの暗い廊下で、レストは剣を振り、その剣に残った血液らしきものを一振りで払った。
彼女の周りに散らばるのは、『開始の歓声』をなぎ倒した時にばら撒かれる謎の残骸だ。
こどもぐらいのサイズで、小さな道化師のような外見だが、それを道化師と言うには何もかも無骨だ。
収容室の前でクリフォトカウンターを下げ続け、果てには脱走を促してしまう。
それがALEPHだろうと関係ないのだから、脆くもかなり悪質である。
「レスト!ご無事ですか…!こちらも終わりました」
遠くからE.G.O天国を担いだ259が、レストに労いの言葉をかける。レストは沈黙したまま、片手をあげて応えた。
抽出チームの廊下は一本道なので、両隅に二人が立てば無事に乗り切れるのである。
ルシフェニアはセピラにて『開始の歓声』の出現を監視しているが、ややほの暗いことを抜きにすれば、見通しは良いためすぐに片付く。
「あ!後ろ…!」
「三体」
259が叫んだのとほぼ同時に、レストは自分の背後にいた『開始の歓声』を切り倒した。
ケラケラと、小さく不気味な笑い声がこだまして弾ける。
廊下はかなり長いが、レストの敏捷性はずば抜けて高く、特殊な剣状ジャスティティアの特性を活かせる場でもある。
おかげで抽出チームは、どの収容室もクリフォトカウンターを下げずに終わりそうだ。
「…恐らくここには、もう来ない。俺は戻るぞ」
「あ、はい!」
レストがさらっと言い残して踵を返して行ったので、259もその後ろをついて戻っていく。
*
記録チーム廊下では、ただ一体の『開始の歓声』が人の腕の中で、わたわたと身じろぎしている。
キャロンは、目の前に現れた"それ"をわさわさと触ってみていた。
ただ古い布を張り合わせたような姿、中身には色々謎の肉塊が詰まっているため、
あまりいい匂いはしないのだが、彼女はそれを全く気にしていないようだ。
「うへへ…えへへへ…」
「……困りましたね」
同部署に配属されたジョンは、それをどうしたものか、と眺めている。
しかし、彼が立ちすくんでいるのは、何もキャロンを巻き込む心配があるからではない。
彼の射撃の腕にかかれば、いくら危険がある魔弾であってもキャロンを一切被弾させずに『開始の歓声』を撃ち抜くことができる。
それはとても簡単なことだ。
彼が困って立ちすくんでいるのは、キャロンがあまりにも謎の塊を詰めたその『開始の歓声』に愛着を持っているように見えたからだ。
ここが自分の支部であれば、いくらでも撃ち抜いて処理するのだが、何分事情の違う管理人がそこで異形と戯れているのだ。
それに確かここは『幸せなテディ』収容室の前だ。特に急を要する場面でもない。
ただ腕の中で、彼女の笑い声に応えるような、応えていないようなケタケタ笑い。
しかし、これらはいつ姿を消して移動するのか分からない。
そうなると他の部署に移動し、思わぬ危険を与えてしまうだろう。

「…あんた何やってんですか…」
ついに痺れを切らしたメアリーがセピラから抜けてきて、呆れたようにキャロンに投げかける。
「ああっ!待っとくれぃ!」
腕の中からそれを取り上げられたキャロンは、遊んでいた人形を取られた少女のようにわなついた。
「もう、他の部署に行ったらどうするんですか。…あ」
「あ」
先ほどまでメアリーが蒼い傷跡でわしづかみにしていた『開始の歓声』は、ぽふんと、煙を纏って消えてしまった。
「申し訳ありません。」
「なんでジョンさんが謝るんですか…
でも次からは、うちのキャロンに気にせず、シメちゃって大丈夫ですから」
ジョンが反射的に謝るのを、メアリーはとてもドライにあしらった。それでいいのだろうか。
大人顔負けの少女は、キャロンに歩み寄るととりあえず彼女に立ち上がるよう手を貸していた。
*
(ここには現れていないようだな)
1006は一通り見てセピラに戻ってきたところだった。
サイレンはモニターを確認していたが、彼が戻ってきたのと同時に彼の後ろを指さす。
「あ、1006さん、すぐそこに出現を確認しました。二体です」
「ハイ」
彼はその返事と同時に、すぐ後ろに居たらしい『開始の歓声』を一突きにした。
その個体は結構弱っていたらしく、それはすぐに解れて散らばる。
「…流石です」
「どーも。」
素っ気なく、短いやり取りを交わしながら、収容施設ではやがてエネルギー純化が開始された。
今日も無事に完了するらしい。
辺りからは昨日のように延長の提案もなく、完了申請がなされた。
*
「お疲れさまぁ」
優しいため息のような、柔らかい皿面の声が聞こえる。
今回は訓練初めての試練と言うこともあって、初めてその身で体験する管理人達にはとても緊張感高まる一日となった。
というより、体力的にも精神的にも摩耗が開始された、という感じだった。
「お疲れ様です。…大丈夫ですか?」
「ああ、259くん…お疲れさま。う、うん……」
覗き込むように、259が優しい声をかけてくる。
皿面はそれに無理をして笑顔で応じたが、表情は仮面で隠れているのだった。
しかし、259はそれを感じており、少し寂し気に微笑む。
少しだけ、皿面の中の感じていたものが、単なる緊張としてほぐれていった。
先ほどまで全く空かなかったお腹だが、少しだけ何かを口にできそうになる。
カフェテリアに入っても、心なしか昨日よりは静かで、管理人達の会話より、そこで静かに流れている音楽に耳を傾ける者も多くなった。
「本体ー」
「…なんだ、贋作」
ミカンより足早に歩いていた本体は、彼女の呼びかけに足を止めて振り返る。
彼女はなんだか、いつに増して活き活きとして、目を輝かせている。
「今日は、384さんと、726さんとご飯を食べに行きたいの。良い?」
「……」
彼女のことばに本体は少し驚いた表情をわずかに見せ、小さくため息をついた。
カフェテリアは、収容施設を地下にして、地上一階にある。
コーヒーや、何かの薬品のような香りが漂う、広々としたホールの片隅、
いくつも並べられたテーブルの種類も位置もまちまちで、長いものから丸いテーブルまで、さまざまだ。
不揃いのテーブルに、ジャンルが様々な料理が並ぶと、どことなく不思議なデザイン性が生まれる。
卓上は、色であふれた。
「それにしてもミカンさん、お強いんですね。とても早急な鎮圧でした」
「ううん、みんなのおかげでがんばれるんだよー」
384の優し気な声に応えるミカンは、ちょっと照れくさそうにスープのマグに口をつける。
本体は居づらいように、席をずらして相席している。
彼は会話全部に耳を傾けてはいないが、ミカンが楽しそうに笑うのを見ながら、とりあえず自分もスープのマグに口をつけた。
「それに、ふたりもすごかったの!お星さまきらきらして、
ダカーポをぽーんって!かっこよかったのー」
ミカンの言葉に、384は急にむせた。
*
「ちょっとよろしいでしょうか」
ジョンは、カフェテリアで食後まどろむようにくつろいでいた皿面にそっと会釈する。
皿面のテーブルには、ゆっくり飲んでいただろう優しい香りのお茶が湯気をあげていた。
「あれ、ジョンくん…どうしたの?」
「少し、確認したいことがありまして」
皿面に促されて、ジョンは軽く頭を下げると向かいの席に腰かける。
素顔が見えない者同士だが、お互いの気遣いはよく見える。
「今日の白昼、何かおかしいと思いませんか?
周りの方々が何もおっしゃらないので、
この違和感を感じているのは、自分だけなのかどうか気になりまして。」
「白昼…」
皿面はふむふむと、頷きながら、お茶をすする。
「そういえば、いつもよりなんか多かったよねぇ、歓声ピエロくん…」
その言葉に、ジョンはテーブルの上に手を組んで、静かに頷いた。
静かに、秘密の話をするように。
「そう。いつもならば肉体の調和を撃破後、漏れ出るのは三体。
今日出たのは…八体です」
その言葉に、皿面は息を呑む。まさか、とは思ってはいたが、やはり多かったのだ。
何かおかしい。
奴らは、瞬時に瞬間移動しあらゆる廊下を自在に渡れる。
モニターをしばらく確認していた自分は見ている。おそらく彼も見ていただろう。
少しの異常を。
*
宿舎。
ラサは自身の個室のベッドの上で、目を開けて天井、壁、窓を見つめる。蒼い闇。
手にするスマートフォンの冷たさ。
閉めたブラインド越しに、微かにどしゃぶりの音が確認できる。
「……」
彼女はもう何度も寝返りを繰り返している。
「よっと…」
思い立った彼女は、ベッドから降りて徐に部屋を出た。
リスト型のキーをかざしてドアを開けると、廊下は無機質ながら明るい。ここは夜中もずっと明かりが点いているらしい。
常夜灯と呼ぶには明るすぎる。ホテルの様な仕様の廊下だが、全然やすらげないのは、壁が白すぎるからかもしれない。
精神を地味に削っていくようなワインカラーカーペットの床のことは、あまり考えないようにした。
なんとなくうろついて、疲れたら眠れるだろう、なんて思いながらも、ちっともそれには期待していなかった。
しばらく歩いて長い廊下の先で差し掛かったのは、談話室というか、休憩室の一角だ。
側に給湯室や、飲み放題の自販機もあり、おかしな形の椅子でくつろげるようになっている。
リラックスを促すための、申し訳程度の暖色ランプもあったが、何か無機質で不自然だ。
ココアでもあるかしら、と彼女は自販機に近づくと、背後から声がした。
「…ああ、ラサ。どうしたんですか?」
振り返ると、259がカップを手に持って話しかけてきていた。
「259先輩。あはは、なんだか眠れなくて…」
ラサが苦笑交じりに応えながら、とりあえず自分もココアのボタンを押すことにした。
259がうんうん頷く。
「慣れない所に来ると、眠れないこともありますよね。私も今から起きてる管理人たちと集まろうと思ってたんです。
ラサも一緒にいかがですか?」
259の言葉に一瞬とまどいつつも、それが自分にとっての救いにも感じられた。
なんとなくある胸底の虚しさを誤魔化したくて仕方がない。それに、先輩管理人たちのお話もたくさん聞きたい。
ラサは少しだけ目を輝かせていたらしい。
「ぜひ、お願いします!」
口をついて出る言葉の前から、259から優しい微笑みが返ってきた。
二人はまず、ソーニャの部屋を訪ねた。
寝支度を整えながらも、どうにも眠れないらしい。
声掛けに喜んだ彼女は、「少しお待ちくださいね」と、部屋に戻り、しばらくして黒いブランケットを羽織って出てきた。
結構嬉しそうにしている。
次にクルミの部屋を訪ねた。彼女は全く眠ろうとした気配もなく、扉から垣間見える彼女のデスクには、資料が山積みになっていた。
もしかして忙しいのでは、と一同遠慮気味に躊躇ったが、扉越しのクルミはぱっと笑って「OK、行くわ」と快い返事をして出てきてくれた。
そして、クルミの提案で、1006の部屋を訪ねたが、留守らしかった。
「…カフェテリアかしらね。」
クルミは、ドア越しに手を添えたが、そもそもここをベッドルームにすらしていないかもしれないくらい、出入りの痕跡がない。
4人はとりあえず、休憩室の一角でしばらく話して眠気を待つことにした。
ラサは呼びかけの間、つい先ほどのココアを手にしたまま歩き回ってしまったが、それでもまだ温かい。
マグカップよりは簡素で、紙コップよりは丈夫で効率的な作りのようだ。飲み物も冷めにくい。
すとん、と変な長椅子に腰を下ろすと、それは外見よりは柔らかく、長時間は座っていられそうな作りだった。
彼女は先輩管理人達が各々の飲み物を選んで席につくまで、カップに口をつけるのを待つ。
「何にしました?ココア?」
ソーニャの言葉にラサは「はい」と、カップをちょい、と高い位置に上げて返事をした。
「あ、私もそれにするわ」
クルミもマグを添えるとココアのボタンを押す。
「私も」とソーニャが口に手を添えてふふふと笑っている。
「あ、じゃあここは私も…」
なんとなく他の物を選びづらくなったというのも確かにあったが、たまには気分転換も良い。
次いで259もココアのボタンを選んだ。
ラサにとってココアは愛飲しているものだったが、やはり支給品の無料自販機である。
自支部で飲んでいる自分の選んだココアよりややお粗末な風味に感じたが、
それでもこうしてまたホッと一息つけるのは、嬉しいし、何より先輩たちが一緒なのが彼女にとって楽しみでもあった。
彼女以外の管理人にとって、ココアはとても久しぶりなものだ。
あたたかい湯気に混ざる香りは甘く、ほんのり苦い。
休憩室の一角にある、申し訳程度の暖色ランプは、やっと意味をなすように、温かい。先ほどとは見え方が全く違った。

「それで」と、口を開いたのはクルミだ。
「ラサちゃんは、このお仕事には慣れた?」
マグをそっと下ろして、彼女は優しく語り掛ける。
「まだ全然ヤバいですよ。」
ラサは少し苦笑交じりに応えた。セーターの袖口から覗かせた指で、そっとマグを両手で包むと、じわじわと温かさが広がる。
「けど、885支部のみんな、すごくがんばってくれていて、あたしももっと、もっとがんばらなくちゃって思います」
そっと顔をあげてそう微笑んだ。
聞いていた259がうんうん、と優しく頷いている。
「ラサの支部の人たちの気持ち、なんだかわかりますね」
「うふふ、そうね」
クルミもそれに頷くと、ラサは首を傾げた。
「えっ…」
「あ、がんばれるって気持ちの事よ。つまりはラサちゃんと、ラサちゃんの職員の人たちの気持ちの両輪が成立してるのね」
クルミはマグを片手に、人差し指でくるくると、にこやかに円を描いた。
その横で、ソーニャもココアを口にしながらうなずく。
「ラサさんを見てると、応援したくなりますし、私もがんばれそうな気持ちになれますわ。
それに今日、貴女の訓練中の判断力と決意には驚かされましたもの。頑張り屋さんなのですね」
「そっ…そんな!あたしなんて全然っ…」
先輩たちにほめられ、少し恥ずかしそうにしたラサは、目元をマグで隠すような仕草で首を横に振った。
なんだか、こういったゆったりした交流は久しぶりに感じられる。
彼女は少し微笑むとそっと顔を上げた。
「うふふ、訓練なのに、まるでみんなとお泊りに来ているみたいです。楽しまないとですね!
そうだ、皆さん!この訓練が終わったら打ち上げしませんか!?」
「打ち上げ?良いわね!」
楽しくて口をついたラサの言葉に、クルミが嬉しそうに頷く。
次いで259も楽しそうに身を乗り出す。ソーニャも嬉しそうだ。
「いいですね、どこに行きますか?」
「みんなでお食事になさいますか?それともどこかに旅行に?」
「ラサちゃんは、この前の管理人慰安旅行の時には、まだ来てなかったわね。
ここは、ラサちゃんを連れてどこかにお泊りっていうのもアリかもしれないわ!もちろん、1006ちゃんも連れてね」
楽しそうに話す中、ソーニャが静かに苦笑する。
「1006さん、打ち上げに乗ってくださるかしら」
「あの子は強制連行よ」
即答するクルミに、ラサと259は笑って顔を見合わせた。
「クルミ先輩、1006先輩とは親しいんですか?」
ラサは、ふと問いかける。
ラサはまだ1006とは会話をしていない。会議で顔合わせはしているし、今日彼が『肉体の調和』を追いかけて来たのも見た。
仕事に真面目で、鎮圧に容赦しない。そんなイメージだけが浮かぶ。
「ラサちゃんにもちゃんと紹介してあげなくちゃね。アブノーマリティ鎮圧中には、近づかない方が良いけど、
本当はあの子、すごく面白いのよ。」
あまりにも想像がつかないが、嘘でないことは分かる。
「それにしても、皆さんでお泊りとなったら、可愛い館内着のある宿泊施設だとよいですわね。」
「あ!浴衣とかいいですね!みんなで着てはしゃぐんです!
…って、あたしってばこどもみたいなこと言っちゃって、ごめんなさい」
テンションが最高に上がったラサは、途中で我に返って恥ずかしそうに謝った。
しかし、そこには目を輝かせた先輩たちがいた。
「良い…!!それ最高に良いわね!!みんなではしゃぎましょう!!」
「宿泊施設にプリクラとかあるともっと良いですね。みんなで撮りましょう。
できるだけ他の管理人も誘ったりしましょう」
「そうですわね。その時は皆さんにゆったりとした可愛いアレンジさせて頂いてもいいかしら。」
すごく火をつけてしまったらしい。
先輩たちの熱気にしばらく驚いていたラサだが、それはとても楽しい予感とともに笑顔に変わった。
「ってことは温泉があるところとかがいいわね。ラサちゃん!この訓練が終わるまでにどこの温泉に行きたいか決めてね!」
「あ!あたしが決めて良いんですか…!」
クルミの言葉にラサは目を輝かせる。
―――――しばらく談笑が続いた。
「さて」
「あら?クルミさん、おやすみですか?」
ソーニャが声をかけたのは、席を立ったクルミだ。
カップを返却口に入れ、膝にかけていた白衣を腕に持ち、少し目を細めている。
「ええ。でも、ちょっと差し入れをしてやりたい子が居るのよ。寄って帰るわ。」
彼女はそういうと、新しいカップに再びココアを注ぎ入れた。
「あの子がココアを飲むか、分からないけれど。
まあ、いつもコーヒーばっかり飲んでるだろうから、たまには良いでしょう、ね」
マグが温かいココアで満たされると、備え付けの専用カップハットを被せる。
「そうだわ、これ持って行って差し上げて。多分、ベッドで休んでいないと思うの。」
ソーニャがクルミの横から、自身の羽織っていた黒いブランケットを手渡した。
立ち上るココアの香りに混ざって、ブランケットからは優しくほろ苦い花の香りがする。
「任せて。一緒に渡してくるわ」
クルミはブランケットを受け取り、去り際にそっとラサの方へ振り向く。
「今日は久しぶりによく眠れそうよ。ココアのおかげかしらね。ありがと、ラサちゃん、みんなも。」
彼女の言葉に、ラサは照れくさそうに首を左右に振ると「クルミ先輩も。おやすみなさい」と声をかけた。
ソーニャも「おやすみなさいませ」と頭を下げ、259も「おやすみなさい」と手をそっと振った。
クルミは応えるように手をかざして「おやすみ」と、優しい笑顔で踵を返す。
温かいココア。冷めないうちに運ばなきゃ。
廊下はほの暗く、人の気配がない。
彼女の後姿をしばらく三人は見送ってから、再び会話にぽつぽつ、花を咲かせるのだった。
クルミが人気のないカフェテリアまで降りてくると、やはり彼はいた。
とっくの間にカフェの営業時間も終わり、自動販売機だけが稼働している。
ホテルのフロントにも似た空間で、テーブルの一角、見慣れた白髪ポニーテールの後頭部にそっと歩み寄る。
「お疲れさま」
「…お前か、なんだ」
背後から顔を出したクルミに、1006はそっけなく応えた。
「差し入れよ、さっきラサちゃん達と飲んできたのよ。たまには良いでしょう?
それとも、ココア嫌いだったかしら?」

ココアの入ったカップを差し出すと、彼は「別に」とだけ言いつつも、それを受け取った。
カップ越しから感じる温度は、熱すぎず、ぬるくもない。
テーブルにはすっかり冷めきってしまったコーヒーが置き去りにされたままだ。
1006はココアのカップハットを外すと、すっと口をつけた。普段はあまり飲まないが嫌いなわけではない。
「それから―――はい、これ。ソーニャちゃんがあなたを心配してたわ、これ使ってって。」
「ん」
クルミから黒いブランケットを手渡されて、彼はカップに口を付けたままそれを受け取った。
懐かしい香りがする。甘く優しい花の香り。手触りもふわふわでなかなか良い。
とりあえず、"甘すぎて微妙だな…ここのココア"という感想は、ココアと共に、喉に押し込んだ。今はあまり文句を言う気が起こらない。
それに、ちょうどよい温度だ。お粗末な甘味料のごまかしなどより、彼女たちの計らいには、一応感謝はしている。
「そうだわ!お風呂にお湯を張ってたのよね。とっておきの入浴剤を持ってきているのよ。ね、私一人入るのなんて勿体ないし!入ってかない?」
「は?…え?」
クルミの唐突な提案に1006は、ココアに咽そうになりながら彼女を二度見する。
そして唐突な提案にしては、どこかわざとらしく芝居めいて見える。それでも彼女は楽しそうだ。
「あなた宿舎で休んでいないんでしょ?あなたが宿舎でどうしても休まないって言うのなら別に無理強いはしないわ。でもね!
今日くらいは私のお風呂に入って、ソーニャちゃんのブランケットでゆっくり寝なさい!!」
「…は?!わ、ちょっ!!引っ張るな…!!やめろ!もう!!ココアがこぼれるだろ!!」
彼女は言い終える前に、すでに1006の腕を引っ張っている。
しかし、彼も満更ではないようで、すぐにでも振り払えるような腕を拒否しない。
「ああ、もう、分かった!分かったから!!ちゃんと自分のシャンプーあるから!!それじゃないときしむから!!
あとちゃんと自分で歩くから!!引っ張るなもうっ!!」
生まれつき髪が白く細い彼は、専用のシャンプーを持参している。
やっと素直になった彼を見て、クルミは一安心したように微笑んで、優しく腕をほどいた。
諦めたように小さな荷物を抱えてきた彼を見て、クルミは横に並んで少し前を歩く。
こうでもしてやらないと、多分彼は休憩時間にこのカフェテリアで、ずっと座り続けているのだろう。"なんてことのない、余裕だ"と。
殺伐とした空気が広がっているのは仕方ない。
しかし、彼女は一番新人の管理人のラサと話して感じたのである。
"訓練なのに、まるでみんなとお泊りに来ているみたい。楽しまないと。"
無論ラサも、今日目の当たりにしたことについて、なんのショックもなかったわけではないだろう。
しかし、それでも笑顔の少女の胸の内に、何か懐かしい物を感じることができたのだ。
ただ、時間だけが長い休憩時間。
クルミは1006を連れて、貴重な束の間の休日気分を味わうのだった。
 アイスでも
ホットでも・*゜
アイスでも
ホットでも・*゜