その時だった。
クリフォトの暴走を伝えるブザーが異常なまでに鳴り響き始めた。
あまりにも幾重にも重なって響き出すので、耳を抑えた管理人達もいる。
異常に気付いたラサが震える声を溢す。
「な…何あれ…なんのカウント…?」
ラサの指摘に一同が凍り付いて息を呑む。
多くのモニターの中、中央のモニターが見慣れないメーターとカウントを表示している。
―――60 Second to escape all abnormality.
―――59、58、57…
「すべてのアブノーマリティが脱走するまで…?」
クルミが呟く。
これはどういうことなのか。
「何が起こってるんですか…?これは、一体…」
「おい!!どうなってんだよクソがッ!!!ふざけんなバカ!!!」
817が状況を飲み込めないでいる側で、
ジョンが堪えきれずに怒号を飛ばしながら、モニターの側の機材をストックでぶん殴った。
鈍い音が響く。
「待ってください!皆さん!!落ち着いて…!!深呼吸…!!深呼吸ですよ…!!」
259が動揺を抑えようとしながらも、周りに深呼吸を促す。
彼自身も、この現状に驚きを隠せないことは明らかであった。
皿面も慌てながらも、深呼吸しながら頷いた。
「そそ、そ…そうだよね!ごめん…!ま、まずは落ち着こう…!
ととと、とりあえずここをみんなで脱出しよう…!」
「そうです!とにかく、ここを抜け出して、外部に連絡を取りましょう!!
こんなこと、あってはならないことです…!!」
384はそう言いながらも、震えているようだった。声は悲鳴に近い。
「そうと決まればここを出ようぜ!」
側で726が笑顔を浮かべたまま楽しそうに言う。
その横で、ミカンも強く頷く。
「みんなで生きて帰るの…!」
一同が重い空気の中、緊張感の漂う静寂から、この施設からの離脱を決意をする。
その瞬間、悲鳴が響き渡った。
悲鳴のする方向を見るまでもなく、異常性は全ての管理人がすぐに感じられた。
自分の身で。
ラサは、自分の視界に入ってきた揺れる影を視界にとらえる。
「なにこれ…!!」
背後から…先ほどの授けられた翼、E.G.O『闇の黄昏を過しもの』から、何か布状のものが伸びている。
包帯だ。
幾重かの包帯が、ゆらゆらとゆらいで身に纏わりつく。まるで、拘束するかのように。
「や!!やめろ…!やめ…―――――――!」
ジョンが抵抗しようとしたがその言葉が通じているのか、いないのか、包帯はより強固に口を塞ぐ。
「…っ!!」
少しパニックになったソーニャが、翼を毟ろうとしたが、それは確かな痛みとなって拒絶された。
痛覚が通っている。
その手すら、包帯が包み込んであっという間に身動きが取れなくなった。
「とれないの…!」
「く、ここ…までか…」
先程まで抵抗していたミカンの側で
本体が静かに落胆している。
まさかこの異常事態で、E.G.Oギフトすら暴走に陥ったというのか。
身に着けてきたこれらは、必ずしも我らへの恩恵とは限らないと言うことなのか。
「…E.G.Oギフトの異変だなんて、とても興味深いことだね。
E.G.Oも彼らと性質は同じと聞いていたけど」
ウィリーがまとわりつく包帯を手遊びながら静かに感心している。
「むふふ…この感覚は悪くないのう!!!もっとキツくぅ!!キツく黄昏ぇ!!」
キャロンが包帯に興奮しながら本来の意味とは全く違う動詞のように言う。
『わー!!なんだこれー!!おもしろいな!!』
「あんたたち、楽しんでる場合ですか…」
333とキャロンがぐるぐる巻きを楽しんでいる中、メアリーが深刻に呟いた。
慌てふためく管理人、じっと身を沈め耐える管理人、なんか楽しんでる管理人に分かれた。
こうしている間にも、モニターのカウントは刻一刻と減っていく。
「―――皆さん、落ち着いて下さい。大丈夫です。
装備を…武器を彼らに預けて下さい」
混沌とした空気に錨を投げ入れるように声を掛けたのは、サイレンだ。
辺りは水面が波立ち波紋を広げるように、彼の言葉に集中する。
サイレンは、自分の中にこだまする声を信頼することに決めたのだ。
「装備を預ける…?
なんかよく分からんが、やってみよう!!」
アルジャーノンがぐるぐる巻きになっている中、案山子の収穫祭を掲げた。
身動きが取れないので掲げられない。掲げる意思を表明しただけだった。
刹那、包帯は身に溶けるようにしてE.G.Oを飲み込む。
否、正確にはE.G.Oが包帯を飲み込んだ。
次々に管理人達が、自らの装備、E.G.Oを包帯に任せる。
包帯は薄く光り輝き、静かに溶けていく。身に感じた圧迫感が薄らいで消え、解放に満ちていく。
不安を払拭するようなあたたかさに包まれる。
「これは…なんか…」
「懐かしい感じがするのです…」
ブランダーとシャオには、その神秘性に既視感があった。
幻想、異質と一体化していく。
恐怖も安堵も一体化して溶け込んでいく。
「これは…!!」
1006の鉄の左足に一際分厚く纏わりついた包帯は、ひとつの肉を形成し始めた。
それは義足を飲み込んでいく。
やがて鳥のそれのように、爪と皮膚を蓄え、太ももからは羽が零れる。
『擬態』と呼ぶのに相応しいのかもしれない。
なんとも言えない感触と、触感が通る感覚に、彼は震えた。
「気色悪い…」
しかし、これを利用しない手はない。
これ以上の浸食は許さないが、お互いを牽制し合い、バランスをとった脚となる。
「惟、少しばかり制約に感じるが、悪くはない。」
キャロルも側で何が起こっても恐れない様子でその自身の変化を見守っている。
「なんだこれは…!何が起こって…絶望ちゃんの剣が…!増えた…!」
555の刃は包み込まれ、それは彼の身体に内包されると、二本になって浮遊する。
なんとも心地よい力を感じると、555は自らの身の中から黒い涙が柱のように張り出していることに気付く。
『わー!黒いのに、まぶしい…!!』
333の手元に戻ってきた名誉の羽は、一見黒い羽に変化して見えたが、
空気にそよぐと更に眩しさを増した炎を纏った。
クルミも未だ一度しか発砲していないマスケットの変わり果てた姿を手に取って、そっと息をついた。
「不思議ね、何も言葉になってこないけれど、声を掛けられているような気がするわ。」
「俺たちを、助けて…くれるのか?
まるで、これ自体が生きてるみたいだ…」
アルジャーノンが鳥の爪のような形に変化したガーデンフォークに恐る恐る触れる。
それは、彼の手元に自然に収まるように付属した。
「傘…傘かなぁこれ…」
皿面ははらはらしながら、手元の変化した傘を開く。
ふわふわとしており、とても大きい傘だ。鎖が揺れる。
「……」
259は無言で息をのみ、幹と無数に枝分かれした生き物のような槍を掲げながら、その揺れる鎖を見つめた。
「おいちぃ…」
「食べるんじゃないですよ。
喉つまらせちゃいますよ。」
キャロンが変化したグラインダーから生えた羽を舐めている側で、メアリーが鋭い爪で怪我をさせないよう慎重に止めた。
「ねえ!なんだかすごいよこれ…!!
見たことないし、ごちゃごちゃに見えるけど
結構動きやすいし!」
「白夜ちゃん装備セットが…」
810はテンションが最高潮で、817は僅かに落胆しているように見えた。
521は、さも起こりくることが当然のように変化を飲み込んでおり、とても自然だ。
「敵対反応は、ありません」
「一時的な浸食調和だ。
剥離も容易いが、利用させてもらうぞ」
ルシフェニアとレストもしばらく変化を見つめていたが、当然のように受け入れている。
「わ、わぁ…!E.G.Oの形自体が変わりました…!!」
ラサは手元のくちばしに銃剣と、それの鋭さとは裏腹に備わった小さな羽に感激して触れている。
「羽…?」
384は自らのE.G.Oの星の音に生えた翼を見る。
それは異形であり、見覚えがあり、初めてのものだった。
「なんかわかんねぇけど、変だなこれ!」
726が変形したダ・カーポを面白がって振り回している。
鎖が長くまとわりついて、巨大な鎖鎌のようにも見えるが、まるでそれを邪魔のようにもせず、動きは相変わらず素早い。
「これは…大丈夫なのか?」
「ふわふわー」
本体がすっかり形の変わったくちばしを手に、顔をしかめ、
その側でミカンが羽まみれになったミミックを撫でている。
「これは、面白いことになったね。
E.G.Oギフトすら特定の条件下では、成長し変化を与えることもあるということかな」
ウィリーが感慨深そうに自らの装備と、周囲の装備に生じた変化を吟味している。
E.G.Oであろうとなかろうと、装備を包み込んだ黄昏は、どれも変化が表れ、見たこともない形になった。
司令塔の暗い部屋で、彼らから無数の目が光を放って浮かび上がり、
およそ生命とは呼び難いものの確かな息吹を感じた。
「行きましょう。黄昏は、みなさんが無事にここを脱出するまでの間、力を貸してくれるはずです。」
サイレンが自らのE.G.Oを手にして、静かに告げる。
その素顔は未だに靄がかかり、うかがい知れないが、信用に値するものだった。
「…信じていいのですね」
先ほどまで慌てふためいて怒号を飛ばしていたジョンが、いつものように落ち着きを取り戻し、吹っ切れたように、少しなげやりに、身の変化を受け入れた。
もう迷いも恐怖も一周したようだ。
誰も震えてはいない。
「行きましょう皆さん!!とにかく外へ…!」
ラサが強く希望を含んだ声で促した。
その時だった。
アラートのタイマーが0になってしまったのは。
―――All ABNORMALITIES escaped.
と表示された途端、画面は大きく歪み、収容室から一斉に抜け出すアブノーマリティたちの様子が投影された。
収容室からだけではない。収容施設そのものから抜け出そうとしている。
「告、奴らを恐れるな。
その道がふさがれた時、我が悉く討ち果たし、必ず道を切り拓こう」
「ぎゃるる!!」
「てけり・り!!」
「きゃふっ!」
キャロルが一同を確信に満ちた包容力で包む。いつの間に彼女の元に三体の生物が勢ぞろいで賑やかに現れ、彼らも応戦する気満々に見えた。
「報告、このエレベーターは、スキャンニングの結果、設計上は地上、ホールの中庭に繋がっています。
現在施設内の電圧が不安定であることを検知。
―――推奨、電源が切れる前にここを全員で通過。」
ルシフェニアが司令塔の一部にある扉を指さした。
暗がりでよく見えないが確かに大きなエレベーターがあるらしかった。
先ほど、皿面がアンジェラの姿をしたウイルスに突然拘束されたのは、彼女がここから出入りしていたからだったようだ。
全員でそこに流れ込む。
幸いにも27名乗った所で、エレベーターの重量オーバーはなかった。
広さにも十分な余裕がある。
それと同時に、嫌な予感がよぎる。
これは、恐らく元々人間用のエレベーターではない。
恐らくアブノーマリティのコンテナ搬入用でもあるのかもしれない、と。
「おい!!そんなもの捨て置け…!!」
1006が明らかに怪訝そうな目で、259の腕の中を睨んでいる。
そこには、さきほどまでウィルスの傀儡となっていた、この施設のアンジェラが眠っていた。
「ここに寝かせておくわけにはいきません…!
ここのアブノーマリティがオフィサー型のAIを殺害しているのを見てきた以上、
彼女もその標的になり得ます…!」
傀儡にされていたとは言え、普段は管理人たちをサポートしている存在のはずなのだ。
見捨てていけない。
地上に着くまで、結構時間がかかったように感じられた。
轟音を立てて、到着したエレベーターは開くと停止した。
広い中庭に到着し、そこは宿舎の吹き抜けに通じているものの、一同が足を踏み入れるのは初めてだった。
ガラスの天井で遮られているが、雨天の僅かな白ずんだ外の光が真下に降り注ぐ場所だ。
これで地下収容施設からは、
無事、脱出…とは、とても言い難かった。
全ての電子機器にエラーが生じ始めたのは、それから間もなくしてからのことである。
アブノーマリティの脱走に伴い、耐え切れなくなった電子機器が、
地上の設備にすらエラーを起こしている。
施設内の明かりは少しずつ途切れ、暗くなり始める。
人間たちの世界ではなくなっていく時間のように。まるで地上の黄昏にも似て。
「ドアが電子ロックだと、開かない可能性があるぞ…!!」
アルジャーノンが緊迫して叫ぶ。
「提、いざという時は、私がこの施設内に文字通り突破口を開いてやろう。」
キャロルであれば可能だろうと一同が思うものの、ルシフェニアが音声を放った。
「警告、地下収容防護隔壁が再びOFFに切り替わっています。
テレポート型アブノーマリティの脱走に次いで
収容施設内のアブノーマリティ達がこちらに排出されることが予想されます。
―――…施設外壁を破壊するのは、地上隔壁を物理的に無効にするため、非推奨です。」
「…壁に穴を開けたら、アブノマちゃんたちまですぐ外に出してしまう可能性があるということね…。」
クルミは緊張感を含んだ声で呟く。
収容されているのは、施設の破壊を招く者たちだけではない、世界滅亡の可能性クラスもある。
収容施設、そして宿舎は最悪の場合を除いてアブノーマリティ達を閉鎖しておくために、
電気がすべて落ちても、すぐには外部に脱走できない作りにはなっている。
しかし、それもこの不安定な施設では時間の問題かもしれない。
電気が落ちれば、アルジャーノンの言うように、厳重に電子で管理された扉は開くことができなくなる。
逃げ場はない。
通常であれば、1支部の収容施設内の危険が、その外側に及ぶおそれがある場合、
自動的に特殊部隊に連絡が入り、救援の無い無差別鎮圧及び、
施設の完全な沈黙のために駆け付けられることになっているが、
この状況下だと自動的に連絡が入っているかも怪しく、また来て欲しいとも誰も思わなかった。
「ここで待ち構えて一体ずつ潰せばいいだけの話だ。
不安定な電源が戻るたびに、数人ずつ外に脱出させればいい。」
1006が変化した足と、薙刀で、すこぶる具合が良いように笑みを浮かべる。
この人、残る気だ。と、1006の姿を見てクルミが考えを巡らせる。
その間にもエレベーターの電気は戻ったり消えたりを繰り返しており、
まるでそれ自体が制御不能の生物のように周囲の不安を煽る。
全員が脱出できるまで、この不安定な電気がもってくれるとは思えない。
「待って…。私、退路に覚えがあるわ…。
電気が通ってなくても、外に出られる場所…!」
辺りは緊張した空気で、視線が彼女に集中する。
「…俺もちょっと待って欲しい。
ルシフェニアくんとレストさんと俺で、システム制御室に入って、
システムの復旧ができないか、試してみたいんだ。」
アルジャーノンが息を呑んで伝えた提案に、レストは静かに頷いた。
寡黙な彼女は、厳しいまなざしで辺りを見据えたまま口を開く。
「…試す価値はある。
どちらにしろ、俺たちが逃げたところで、彼奴等は施設を破壊し、いずれは外部に脱走する。
…行くぞ669。」
「了解」
その時、遠く、宿舎の廊下に、巨大な影がうろついているのが見えた。
「あ…あれは…」
384が震えた声で呟く。
歪んだカーニバルの音楽が聞こえてくる。
「急ぎましょう。異常はアブノーマリティ達の脱走だけではないらしい。
システム復旧班とその守護、退路確保班とその守護の二手に分かれて、
少しでも奴らが一か所に集まることだけは阻止しましょう。身動きがとれなくなる可能性があります。
そして、必ず誰かがひとりになるようなことがないように。」
ジョンが怒号を抑えた冷静な声で語る。
『了解…!あんぜんだいいちだよ!』
333の言葉に一同はうなずくと、示し合わせたかのようにエレベーターに光が戻った。
心なしか扉が揺れている。
何か乗せているのかもしれない。
ラサが驚愕した顔でくちばしを手にしている。
「ヤバい…!何か来ちゃいます…!!」
管理人達は、息を呑むと急いで二手に分かれてお互いの目的地に走り出した。
幸いにも、電子ロックされていた中庭のドアは、その時の電気復旧で開くことが叶った。
「もし…!もしも復旧が無理そうだったら、屋上に来て!!
絶対に無理しないで脱出しましょう…!」
クルミが走ったまま振り返り、叫び、アルジャーノンたちは手を振って応える。
二つの団体はまともに会議ができず、お互いの瞬時の判断で二手に分かれたため、勢力がバランス的かどうか、誰にも分らなかった。
システム復旧班は、レストを先頭にルシフェニア、アルジャーノン、皿面、1006、キャロル、ウィリー、ジョン、本体、ミカン、ラサ、ソーニャと、アンジェラを抱えたままの259の13人が走った。
退路確保班は、クルミを先頭に333、ブランダー、シャオ、キャロン、メアリー、384、726、サイレン、555、817、810、521の13人が走った。
人数だけは偶然にも綺麗に二分されて離れた。
*
「システム制御室はこっちだ。急げ!」
レストが時々後ろを振り返る。
辺り一面の色とりどりの宝石が、やがて消えゆく不安定な灯りに照らされて輝いている。
途端、通路中に甘くて優しい香りが充満してくる。花に似た、もしくは花そのものの香りだ。
ふとその香りによく似合うラベンダーアメジストが一人、足を止めて黄昏の翼を翻している。
「ここはワタシに任せて…!」
ミカンが、羽毛に覆われたミミックを向けた先には、アルリウネが佇んでいた。
小さな淡い花吹雪をちらしながら、長い6本のなまめかしい足で立ち、さもオブジェのように微動だにしない。
どうやら不安定になった電源に収容システムが破綻し、ここまでテレポートしてきたらしい。
このまますぐ外にまで出られてしまうと、他のアブノーマリティ達も出て行ってしまう可能性がある。
「俺もここに残る!
鎮圧したらすぐに俺たちも向かうから、先に行ってくれ…!!」
ミカンの後衛に、本体が黄昏のくちばしで発砲しながら叫んだ。
マズルフラッシュは、薄暗くなりつつあるエリアを眩しく照らした。

「わかった…!!本体君、ミカンちゃん、くれぐれも安全を優先してくれ…!!
危なくなったらかまわずこっちに流れて合流してくれ!!」
アルジャーノンがフラグを立てないように慎重に言葉を選ぶ。
「急ぐぞ」
レストは、一対のラベンダーアメジストの双晶がアルリウネに向かっていくところを見届け、
すぐに踵を返して走っていった。
システム復旧班は、システム制御室に続くすぐそこの階段を降りると、開けた暗いホールに辿り着く。
僅かな非常電源に青く暗く照らされている。
その時眩しい光がホールを照らした。
「おい…あれ…」
ジョンが息を呑みながら見上げ、
皿面が言葉に詰まりながらつぶやく。
「あっ…あああ…あ、蒼星…」
暗がりの中、発光して見える。
浮かんでいるのは、大量の脚を持ったハートだった。
その足ひとつひとつが、まるで誰かの別物の意思を持つように、動き、音響を放つと一斉に空気は波打った。
脈動。
蒼星は、ALEPHの中でも脅威的で、その攻撃範囲は施設内全土である。
決して大きな音ではないが、エコーは壁も地も隔たり鳴く平等に響き渡っている。
その光景は、世界が生まれる前を彷彿とさせるほどに美しく、恐ろしい。
黄昏に強化されたE.G.Oとはいえ、ベースに白弱点の性質があれば長い間持ち堪えることはできないかもしれない。
「まずい…これじゃあここにいる管理人達だけじゃなく、向こうで戦ってるミカンちゃんたちや、
退路確保班も危ない…!!最悪の場合、全滅なんてことも…」
アルジャーノンが混乱しながら慌てている間にも、「くそがぁ!!」と叫び散らしながら、ジョンが魔法の弾丸を放っている。
「とても綺麗だけど、このままにはしておけないね」
ウィリーもすぐさまラエティティアを構えると、上空を狙い撃った。
ホールの天井は高く、本来ならば届く位置にいる蒼星が、飛び道具でなければまるで届きそうにない。
未だ眠ったままのアンジェラを抱えた259が、緊張した面持ちでそれを見守る。
「このままじゃ他のアブノーマリティも出てきてしまいます…!!!」
ラサが緊迫した様子で、それでも銃口を向けたまま叫んだ。
「―――…案ずることはない…」
途端キャロルが静かに告げる。
いつもと雰囲気が違う。
前に出た彼女の口元には、笑みが浮かべられている。
「黄昏が融合した面白いE.G.Oも気に入っていたが、仕方がない。
―――…本領発揮と行かせてもらおう」
彼女は、黄昏によって強化され巨大になっているユースティティアの大剣を床に突き立てると、
両腕を広げその場で輝き始めた。
蒼星とは、全く別の世界の光を放ち、ゆっくり浮かび上がると、
少しずつそこにいる全ての存在に距離を詰めていく。
―――否、巨大化していく。
さながら魔法少女のようにして、無数の輝くあぶくに包まれる。
波の性質特有の、反射する光の干渉と屈折により、虹のように見える。
それが晴れた頃には彼女の服装は変化していた。
一瞬の出来事のようだったが、その光景は一同の目に焼き付く。
キャロル自身と蒼星の光は、相容れずとも調和しあい、それは様々な色に見えた。
目元のユースティティアからは、青い瞳をわずかに覗かせており、
ほの暗いホールでは蒼星の光と彼女の眼光が怪しく光っている。

「キャ、キャロル先輩が…お、大きい…!!」
「なっ…!!」
「きれいですわね」
「話には聞いていたけれど、
まさかここで実物を見させてもらえるなんてね」
ラサたちがその姿に驚愕したり、見とれている横で、ウィリーは興味深そうに微笑みながら見上げている。
「……」
黙して見とれる259のメガネ越しの瞳は、青い光を吸い込んでよりいっそう美しく輝いた。
各々が、その予想外の姿に見とれている横で、1006が見慣れた光景を見るような顔をしている。
やがて三メートル近いサイズ、…蒼星と同じくらいのサイズになった彼女は、顕現させた太刀を向け、泡を噴出させた。
黒い泡は、無数の脚に纏わりつき、その動きを鈍らせる。
星から零れ落ちる泡は、まるで静電気のように浮かび対象を包み込み、蒼星の光を埋め尽くそうとしていた。
名状し難い匂いが立ち込める。
「行くがよい。ここは私が引き受けようぞ。」
ひとりでも断じて大丈夫であることは、桁違いのその姿が物語っていた。
圧倒されながらも、一同は歩みを進める。
「わ、わわ分かった…
レストさん、みんな!!行こう…!!」
未だに動揺してはいるが、我に返ったアルジャーノンの声に、一斉にその場を抜け出た。
今はなんとしても、システムを復旧しなくては。
暗い通路を抜けて、再び開けた場所に出る。
やがて辿り着いたシステム制御室で、レスト、ルシフェニア、アルジャーノンは速やかに起動を試みた。
辺りは電源が点き始める。
「よかった、…この辺りの電気は生きてるみたいだな」
照明は乏しいものの、モニターの灯りによって浮かび上がった制御室には、
所狭しと機材が詰め込まれていた。
側には、見覚えのある箱状の警告色に赤いボタンがある。
多分これは、触れてはいけない。
この状況で押した場合、どうなるのだろうか。
ウィリーが無言で触れようとしたところ、
突然アルジャーノンは机を叩いて嘆息する。
「駄目だ…!システムそのものがイカれてる…!」
「システム復帰の試行——————…エラーを確認しました。
もう一度、試行します。」
彼の横では、ルシフェニアとレストが機材の再起動を試みているようだった。
「来やがったな…」
彼らが入ってきた方向とは逆方向の廊下から、『絶頂の身震い』が向かってくるのを1006は見逃さなかった。
1006はすぐに制御室の外側に立つと、地を蹴ってそれに突撃し、反対側へ突き飛ばすように切り付けた。
「援護致しますわ」「はい…!」
「いらん戻れ!」という1006の声もしり目に、ソーニャとラサが後方から並んで発砲してくる。
聞こえているのか、あえて無視しているのか。
騒がしくなり始めた制御室の外側に、警戒しながら管理人たちは少しずつ身を乗り出す。
部屋の外側で制御室を守るように取り囲み、事態の状況を確認しながら体制を整える。
259はそっとシステム制御室に踏み入ってアンジェラを壁にもたれかからせると、すぐさまE.G.Oを手にした。
「皿面、大丈夫ですから…
ここでじっとしていてくださいね」
制御室内、アンジェラのもたれかかる壁とは反対側にいる皿面に声を投げかけた。
皿面はやはり少し不安そうに座り込んでいる。
259はいつもの優しい表情とはほんの少し違う顔をしながら、そっと部屋を出た。
「おや、こちら側にも何か来たみたいだね」
ウィリーが視線を配らせ、ラエティティアを放った先には、上の階から落ちてくるもう一体の『絶頂の身震い』が姿があった。
上の階の柵は大きくひしゃげて、落ちる。
血液ではない何かが広がった床は、大きく割れて凹んでいる。
それにも関わらず、ボロけたツギハギの身体は開いて、まるでなんともないように赤く汚れた鈍器を掲げる腕が現れた。
着地を確認したウィリーと259は、対象が移動を始める前に、すぐさま至近距離まで走っていく。
「ひっ…!こっちくんな…!!」
ジョンが怯えながら魔法の弾丸を放つ。
黄昏によって強化された魔法の弾丸は、威力も射撃の反動も大きく感じられたが、怒号を飛ばしながらでもジョンは容易にコントロールできている。
至近距離で発砲しているウィリーと応戦している259に掠ることもない。
「…!!
みなさん…!何か近付いてくる音がします…!」
259が黄昏によって強化された天国でミートハンマーを防ぎながら、辺りを見渡した。
しかし、まだその姿はない。
『肉体の調和』を鎮圧し終え、辺りには小さな肉の道化師が散らばる。
「生ゴミどもめ…!」
蹴散らす1006の追撃と、後方からの援護射撃によって中からあふれ出た小さなピエロたちは瞬く間に破裂していく。
その時、反対側の通路から何か夥しい数の気配と物音に一同は振り返った。
鉄のぶつかる音が響き渡っている。
広い通路に思えていたが、その道をすべて埋め尽くさんばかりの金属。
照明が乏しく、未だ薄暗い廊下に赤いライトが無数に灯っている。
理解プロセスの大群。
「…!」
歩みだして攻め入る光景は、さながら錆の壁であった。
今、回復炉のないこの場所で一斉射撃されては、ひとたまりもない。
「何が来ようと潰す!!」
1006が掠る夥しい量の弾丸を掻い潜って前面に立ち、それを庇おうと259が身を乗り出そうとし、ジョンとウィリーが加勢に向かおうとしたその時だった。
突如、彼らの視界は遮られた。
黒くて大きく開かれた、巨大な傘。
「皿面…!」「皿面さん!」「先輩…!」
誰よりも前に立ち、E.G.Oを掲げていたのは、あろうことか皿面だった。
黄昏によって変化したブラックスワンは、大きな翼のようなアーチを広げて揺れている。
皿面は、自分でもどうしてこのような行動をとったのかが分からず、お面の下の表情は動揺している。
「…あわわわ……」と小さな悲鳴が聞こえてきた。
理解プロセスの方角の視界が遮られた代わりに、一切の砲撃が止んだ。
ガトリング乱射の音が、遠くで大きく鉄の弾ける破裂音に変わって聞こえる。
皿面は震えている。E.G.Oを伝ってくる振動のたびに、小さな悲鳴を上げている。
怖いオブ怖い。それでも決してE.G.Oを手放すことはできず、巨大な鳥の爪のようなハンドルを握りしめた。
やがて、その鉄の弾ける音すらしなくなった。
皿面が恐る恐る傘を下ろすと、そこには火花を上げたまま破損している理解プロセスの残骸が連なっていた。
「え…ええ…?」
分からないまま自分でとった行動ではあったが、結果に動揺を隠せない。
驚いてよろけそうになっている彼を、ウィリーが支える。
「わぁ、これは全反射だね。
皿面くんはなんともないかい?」
彼は皿面の傘を興味深そうに見つめている。
皿面自身が何よりも驚いている。
「ぼ、僕は大丈夫だけど…、全反射だなんて…
それじゃあこれは、まるで黒鳥の夢が持っている傘そのものだ…」
恐怖、恩恵、畏敬。
このE.G.Oたちのなかで一体何が起こっているというのか。
E.G.Oだけではない。
管理人達の身体の中で明らかな変化が起こっている。
それは1006の左足に限ったことではないらしかった。
「…皆さま!ご無事てすか?」
駆けつけたソーニャとラサが辺りを見渡す。
「私たちなら皿面のおかげで無事ですよ」
259がいつものように微笑む。
とはいえ、前面に鎮圧に向かっていった管理人達は、致命傷とは言えないにしても、無傷ではない。
「かすり傷くらいほっとけばいい」と吐き捨てる1006も確実にダメージが蓄積している。
平気そうにしているが、周りから見れば、皿面が助けてくれなかったらと思うとぞっとする。
「応急処置にはおあつらえ向きの包帯なら沢山あるけどね」
ウィリーは冗談なのか、手段なのか微笑んで応えたが、そもそも素材が幻想体の包帯はこの場合利用しても大丈夫なのだろうか。
「電子機器がエラーを起こしている今、修復のために地下収容施設に戻った所で
システムが正常に機能しているとも思えませんし、地下収容施設にも戻れそうにありませんね…」
259が自分で言い終えた後で、何かに気付いたように制御室内を見渡す。
「システムが正常に機能していないという事は……
アルジャーノン、今TT2は無効になっていますか??」
アルジャーノンは手元を忙しく動かしていたが、259の言葉に首を傾げてしばらく手元を停める。
「え?…ああ、TT2は、今不安定な状態だよ。エネルギーもほとんどあいつに奪われたみたいで、
恐らくこのまま有効にしておいても破綻するのは時間の問題…―――――
……あ!TT2が無効になれば、外部に発信してもエラーを起こさないかもしれない…!!」
「やはりそうですよね。TT2を一時的に無効にしてもらえますか?
私は自支部のアンジェラと連絡を取ってみます。
皆さんは制御室内でしばらく休んでいて下さいね。」
259の言葉にアルジャーノンが息を飲んで応えると、
彼の次の操作で通路に僅かに伺えた外の光が一斉に無くなった。
広がる暗闇に、
非常電源用の照明が点々と灯る。
どうやら外の時間では今、太陽はないらしい。
259は新たな刺客が来ないか、部屋の外の様子を注意深くうかがいながら、おもむろに連絡機器を取り出した。
―――発信が正常に繋がっている音がする。
*
退路確保班は、列を成して階段を駆け上がる。
無論、現在電圧が不安定であるから、エレベーターを使うのは危険だ。
それでも、訓練施設宿舎の階段は薄暗く、足元がよく見えないので、少し注意が必要である。
彼らは階段を目指して開けた薄明るいロビーを走っていた。
毎日通った場所だが、こうなるといつもの風景ではない。
『追手をかくにん…!!』
333が足を止めて振り返ると、錆びた鉄の音を響かせて迫りくる『暖かい心の木こり』がいた。
「きこりちゃん脱走の条件は、作業に行った職員を殺害することよ…!何故脱走しているの…!?」
クルミが緊迫した表情で振り返るも、そこには蠢く何かをたくさん胸に詰めた血濡れのブリキがいる。
肩や頭部に生えた苔には、返り血が滴っている。
「入っているのは…も、もしかして、オフィサー…?」
384がおののく。一同はその言葉に戦慄する。
「胸に入ればなんでもええのやね…!」
このような状況下でも皮肉そうに乾いた笑いで555が叫ぶ。
人間に見えたオフィサー達もAIのように制御されているのだとしたら、
ウイルスによって操られその胸に飛び込むことも容易に予想できた。
そんな彼らを横切って何かが突っ込んでいった。
―――青い影。
「ブランダー…!!」「ブランダーさん!?」
彼は舞うようにして、跳ねまわり、魔法の弾丸をいくつか打ち込んでは、ホーミングのように何度も相手を貫いている。
その様は、青い閃光とともに踊っているかのようだ。
しかし彼の目は、殺意に満ちてとても冷たい。
一同はその冷徹ながらも美しい様に目を奪われる。
その瞬間、油断していたのだ。
元々進行方向であった方角から、無数の『疑問』が少しずつ詰め寄ることに、誰も気付かなかった。
ブランダーがこちらに魔法の弾丸を向けてきたとき、その冷たさに一同は凍り付いた。
一瞬にして放たれた青い閃光は、管理人達の後ろから忍び寄っていた疑問たちを貫く。
奥の方からは、理解プロセスが電気を帯びながら歩みを進めているのが見えた。
ブランダーが自らの殺意に破裂しそうになったその瞬間。
―――彼のものではない青い閃光が射して理解プロセスたちを焼いていく。
「…あの人は…!!」
サイレンは目を疑った。
そこには、非脱走アブノーマリティであるはずの『魔弾の射手』が、銃を構えて揺らめいている姿があった。
黒々とした炎のような頭に灯す、ブランダーと同じ色の瞳からは、全く敵意がない。
本当に支援にきたかのような佇まいだ。
『おー!
魔弾の射手も助けてくれたのかー!!』
333を始め、そこにいる管理人達が驚いている中、ブランダーはその雄姿に見惚れていた。
"ここは 私が できることをやろう。
キミは 皆と できることをやりなさい"
ブランダーには魔弾の射手の言語を正確に拾うことができた。
他の管理人には、魔弾の射手の言葉は聞こえなくても、彼の意図や計らいを受け取ることはできる。
「ありがとう…!!」『さんきゅーだよ!!』
「ああ、あありがとう…」
様々な表情で礼を伝え、一同が魔弾の射手を横切っていく。
一同の最後に、ブランダーも嬉しくなって抱き着いた。
これでお別れなのだ。
どこかの分岐点の先。
見果てぬ夢の、あたたかな青い光。
優しい黒い炎。
皆が遠くなっていく中、ブランダーはこの短い時間でできるだけのお礼を伝えようとしていたのである。
その時、
オールアラウンドヘルパーが、アブノーマリティ、人、区別なく浮遊しながら発砲してきた。
対象に気付いた魔弾の射手は、まだ胸元に抱き着いていたブランダーを庇うようにして包むが、鉄の弾は容赦なく射手を撃ち抜いた。
"—————…!!!"
「…!!!…とう…さ…、ま…!!」
ブランダーの表情は、みるみるうちに変化していった。
驚愕から悲しみ、悲しみから怒りへと。
魔弾の射手の腕が肩から滑り落ちた時、
彼は青い炎となって燃え上がった。
地が震える。
「ブランダー…!」
シャオが思わず呼びかける。
返事がない代わりに、ブランダーは青い光が宿った瞳から、黒い涙を流しシャオを見つめている。
すでに進み始めていた管理人達は何が起こったのか分からず、状況に驚愕したまま足を停める。
側に残っていたのは、シャオと彼の姿に興奮したキャロン、すぐに守りに駆け付けようとした817の三人だった。
その時、オールアラウンドヘルパーは、コミカルな顔を歯車のように高速回転させ、管理人達の列に突っ込む。
「…シャオさん!!」「わしが守るんじゃぁ!!」
ブランダーの様子を近くで見ていたシャオが運悪く標的に選ばれる。
そこに走り込んだのは、ブランダーの姿に興奮したキャロンだった。
「シャオさん…!キャロンさん…!」
キャロンは急いで駆け寄ってシャオ抱え込むようにして守り、
ふたりを守ろうと駆け込んだ817がヘルパーを失楽園で塞き止めている。
ブランダーは打ち震えた。
彼は叫びとも咆哮ともつかない音を立て、姿が大きく変化する。
——————アブノーマリティ。
幻想体と呼ぶのにふさわしい、青く美しい光。
象徴を表す、性質のすがた。
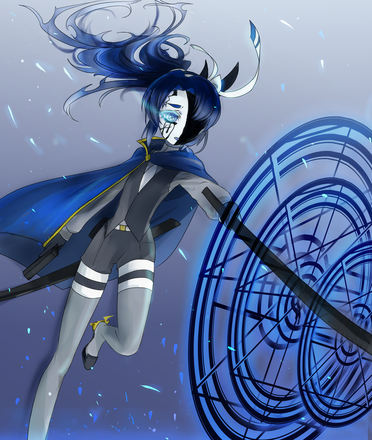
ブランダーは、青黒い太刀と拳銃を握りしめ、辛うじて彼自身の面影を残したまま、
オールアラウンドヘルパーに襲い掛かる。
振るわれた太刀は、青い光の軌道を描き、シャオと、シャオを守るようにしていたキャロン、
ヘルパーのアームを抑え込んでいた817をギリギリの距離で避け、一撃で休止させた。
彼らが無事であることを見届けると、
ブランダーは寂し気に父親の方へ向く。
「……父様」
"最後まで 私を 父と呼ぶのだな。
私は キミを 友と思っているよ"
「それでもいい。父様はすべての魔弾の射手と繋がってる。あなたもだ。」
ブランダーは黒い涙を流しながら、そっと膝をついて、どこかの分岐点の先、
黒く燃える遠くの父の額に手を触れた。
"……行きなさい。
私は 多くの存在を傷付け 大切な人も守れなかった。
しかし 今のキミならば 大切な人を守れるだろう"
魔弾の射手はそれだけを言い終えると、他のアブノーマリティと同様に静かに消えた。
死んだわけではない。
彼らは死ぬことが許されない。
しかし、今ここではそれが別れなのだ。
ブランダーが向こうへ目を向ければ、まだ向こうから大量の鉄くずが溢れ出ている。
「ボクはここにしばらく残る。
シャオは、みんなと退路に向かうんだ」
ブランダーがそう言いかけるも、未だキャロンの腕の中にいるシャオは震えて首を左右に振った。
「…嫌なのです…。ブランダーが残るのなら、しゃおも一緒に残るです…!!
一緒にここで防衛線を張るです…!!」
「シャオ…」
「ううぅ……うう…尊い…尊いのう…尊すぎて…ああぁ…」
涎を垂らすキャロンの腕から這い出たシャオは、キャロンと817に向き直って小さく頷いた。
「ブランダーさん、シャオさん…」
「しゃおたちのことなら、大丈夫です。
ジョンが言ってたです。絶対一人になることのないようにって言ってたです。」
ジョンが危惧した言葉とは、無縁のように、今のブランダーは桁違いに強い。
しかし、ブランダーもシャオの言葉に頭を項垂れながらも、最終的にはうなずくしかなかった。
「…あいつらを一掃したらすぐに後を追う。
ボクたちは大丈夫だから。」
彼らを見送って、817は強く頷き、未だ尊きものたちを拝むキャロンの腕を引いて、他の管理人達を追った。
彼らはクルミを先頭に宿舎の階段を目指す。
白い宿舎の壁には、すでに何かが通過したような赤黒い痕跡がべっとりと残っていた。
「…!!クルミ…!!みんな止まって!!」
「っ…!」
突然クルミの腕を引きとめて、
全員の列を止めたのは810だ。
「これは……
皆さん、もう少し下がりましょう」
サイレンが目の前の状況に息を飲む。
異臭がする。
それと同時に、床が大きく揺れだし、
轟音とともに、目の前に巨大な影が現れた。
大地から大きな口が開いて突きだし、瞬時に閉じる。
牙や飴色の艶やかな目を備えて出現した、
天井をつくほど巨大なコブのようなもの。
ちょうど、祈る手のようなかたちにも見える。
それは揺れながら退路を塞ぎ、共に祈れと
足にすがりついてくるような姿にも感じられた。
―――琥珀の深夜『永遠の食事』。
このような異常事態で、地上施設に試練が現れるのは不本意ながら受け止めてはいたが、
まさか、ここで深夜の試練に遭遇するとは。
一同は不安に駆られる。
「う…うそ…」
384が青ざめた様子で後退りするのを、庇うように726が前に出る。
「ま、待って726!
ここから全員で離れなきゃ…!」
「でも放っといたって危ないだけじゃね?」
384が引き留める声も尻目に、726は鎌を振り下ろす。
それを皮切りに続々と管理人たちが前に進み出た。
「やってみましょう」
サイレンは手元のE.G.Oを何か大砲状のものに変化させると、強力な砲撃を放った。
鐘のような音が響き渡る。
黄昏によって強化されたそれは、包帯に包まれながら変化にも追い付くが、形を見るだけでは何のE.G.Oがベースなのか、彼のみが知る。
「激しく同意する」
521は床を蹴り、大きく飛ぶと更に歪で刺々しくなったミミックを振り下ろす。
ただでさえ彼の攻撃は強力だが、黄昏によって更に強化された打撃は、
巨大な『永遠の食事』を大きく揺らすものだった。
「どこか別のところに現れたら、
他の連中が危ない目に遭うかもしんないからさ!」
810は自信満々に言って、521に続く。
しかし彼女は、別行動をとる管理人達を心配するような口ぶりをしながらも、
彼女自身が変化したE.G.Oを振るうのを楽しんでいるかのようだった。
「今これの攻撃を避けられたのは幸いです。
みなさんに被害が及ぶ前に
ここで鎮圧してしまいましょう…!」
817が翼で更に大きくなった失楽園を振るうと、
その床下からは赤い鎌が広範囲に無数に突き出し、
同時に黒い巨大な爪のようなものも吹き出した。
「どれ…味見してみようかえ!!」
キャロンが躍り出て、嬉しそうに羽の固まりになったメイスを手に飛びかかる。
メアリーは自身の身体の3分の1ほどもあるのではないかと見まごうほどの巨大な爪を振り下ろし、応戦した。
「任せろ…!」
555は宙に浮く二本の黒いレイピアを操りながら、不敵な笑みを被り物の下からのぞかせた。
接近武器であるはずの剣だが、彼の意思の通りに踊り、飛び道具のように距離を保っている。
『くるみと384は安全な場所に下がってて!』
333が操る手元、漂っていた無数の黒い羽は
風圧で金色に変化し、輝きながら注がれていく。
384はしばらく怯えていたが、
口を食い縛りながら自身も星の音を操って応戦する。
黒い羽のようなものが生えたそれは、輝きは星のまま、
鳥のように突進していった。
普段の深夜鎮圧の時とは違い、
『永遠の食事』から聞こえてくるはずの、
何かが犇めく音を掻き消して、E.G.Oの打撃音が響き渡る。
「…そろそろ来るわ!
みんな離れて…!!」
クルミの声に接近して戦っていたキャロンはすぐさまメアリーを連れて引き下がる。
しかし他の管理人たちは未だに追撃を止めない。
巨大なコブは粘着質な音を立てて祈りの手を緩め、
その隙間から大量の『食物連鎖』たちが溢れ出てきた。
どこまでを一区切りのエリアとするのか、
それらは地中に潜ることなく這い続ける。
真正面から接近戦を挑むのは危険だ。
「せーの、そぉーいっ♪」
「ちょっと726?!」
384が驚いたのもそのはず、
726は黄昏によって強化されたダ・カーポを降り投げていた。
覚えた技は積極的に使おう。
ダ・カーポは、大きく風を切る音を立てながら回転し、鎖を伴いながら
『食物連鎖』たちを突き抜けて『永遠の食事』を貫通した。
「よっと」
鎖を思い切り引くと、大鎌は意思を持ったように726の手元に帰ってくる。

宿舎の吹き抜けを挟んで、ふたつ上の階の手すりに捕まっていた521は、
それを見届けてから手すりを蹴ってミミックを振り下ろした。
呻き声のような、巨体から空気が抜けるような、悲鳴のような音を響かせて、
祈りの手はほどけ、そのまま力なく不気味な花のように開く。
その脇から810が飛び出し、残った残党たちを片っ端から切り捨てていった。
先程のダ・カーポの一撃もあり、
それらはあっけなく片付いていく。
「みなさん、お怪我はありませんか?」
817が振り返る。
「は、はい……!
それにしてもこんな短時間で終わるなんて…」
384が息を飲んで辺りを見渡す。
僅かな時間で深夜の試練のうち一体が片付くとは。
黄昏によって強化されたE.G.Oの能力を感じたが、それ以前にまず全員が強い。
「一体は片付きましたが、普段『永遠の食事』は二体でセットです。
この異常な状況でどこまで通例通りかは解りませんが、
いつどこで出てくるか解りません。
注意して向かいましょう」
サイレンが大砲状のE.G.Oを元の釣り鐘の形に戻しながら、警戒ぎみに辺りを見渡す。
クルミも息を飲んで頷いた。
「そうね…
ここでは逃げ場がなくなることも充分に考えられるわ。
少し急ぐけど注意しながら退路を確保しましょ…!」
大きく開いたままの『永遠の食事』だが、
脇はかろうじて通過することはできる。
艶々とした残骸を避けながら、一同は階段を目指した。
*
「贋作…!いくらなんでも、無理しすぎだ!!退いてあいつらと合流するぞ!!」
後ろから響く本体の声を聞き届けてミカンは「へいき」と短く相槌を打つ。
先ほどのアルリウネを無事に鎮圧し終えた後、合流に進もうとした彼らだが、
途中で【規制済み】の列が通りかかった。
アルジャーノン達のいる制御室は近いはずだ。
そのままにしてはおけない。
【規制済み】は一体何を取り込んだのか、多くの眷属【規制済み】を連れてゆっくり進行している。
【規制済み】が【規制済み】をした途端、地響きを立てて、その衝撃に小刻みに壁は揺れた。
未だに【規制済み】の群れは中庭に続くガラスを割って進行してきている。
ミカンは、その小柄な身体の倍はあるだろうミミックを軽やかに振るい、進行を塞き止めているが、先ほどからこれらを相手に一人で前衛をこなしている。
素早く相手の攻撃を見切って避けていたのも先ほどまでの事だが、少しずつ様子がおかしくなっているのは、遠目に見ても明白だ。
耐久戦で、いくらなんでも無理をしすぎだ。
彼女の背は、徐々に震えている。
恐怖ではない。
恐らく疲労と不安が、彼女の興奮状態に歯止めを効かなくさせている。
「おい、贋作…―――!!」
さすがに心配した本体が彼女の腕を取って退避しようとした、その時だった。
突然青い巨体の影が遮り、ミカンを持ち上げた。
「…!!!…!!」「お前は…!狼…!?」
大きくて多分悪い狼。
彼は脱走の姿、人の言葉を失ったままミカンを咥えると、
本体の方に向いて鼻を鳴らし、そのまま別方向へと走っていった。
飲み込んでしまわないところを見ると、まるで敵意はなく、何か考えがあるようだ。
「…つれていく気か…!!?」
ウイルスの影響により多くのアブノーマリティが脱走させられているにもかかわらず、この状況下で理性を保っているというのか。
本体は狼と、咥えられたミカンを追って、【規制済み】の大群を掻い潜り走り抜けて行く。
やがて彼らはロビーに戻ってきて、宿舎棟の階段を登って行った。
狼は滑るように駆け登り、度々本体がついてきていることを確認しに、振り返っては足を止めている。
その間にも、咥えているミカンに細心の注意を払ってくれているらしかった。
(どこまで行く気だ…?!)
本体は口元で揺れているミカンが無事であることを確認し、狼を睨み上げた。
どこまで登ったか、ある階層に差し掛かって、狼は階段を上るのをやめ、通路を走った。
「お!!大きくて多分悪い狼…!!!
あ、あれ…口に咥えられているのは、もしかして…ミカンさん…?!」
聞き覚えのある声に、本体は速度を落とした。
狼も、そこでスピードを落とし、やがて足を止める。
向こう側でこちらに声を掛けていたのは、384だ。
彼の他に、726をはじめ、退路確保班の一同が連なっている。
「おぉ!ミカンちゃん…!!こんなとこでばったり会えるなんてな~」
726が飄々と歩み寄ってきた。
「726さん~。それにみんなも~。」
狼の口元に、子猫のように咥えられたミカンが手を振っている。
「一体どこに連れてこられるかと思えば退路確保班だったとはな…」
本体は息を整えながら、安堵と呆れの表情で狼の脇から出てくる。
「お二人とも無事でよかった……
システム復旧班の他の皆さんはご無事なんですか?」
817が彼を心配しながら歩み寄る。
「それが…」と、本体が言いかけた時であった。
唐突に響いた発砲音とともに、狼は急に苦しみ始め、ミカンを口から落とした。
「わ…!」
「ミカンさん!!」「よっと!セェーフ…」
零れ落ちる彼女を、ちょうど下にいた384と726が抱き止める。
【毛皮野郎ォォオオオ!!!!】
反対側の通路から来たのは、あろうことか、赤頭巾の傭兵だった。
狼に出くわして、彼女も赤い光を纏い、人の言葉を失いつつあった。
「赤ずきんちゃん…!
真っ向からあの子と戦うなんて無茶よ…!」
クルミが叫ぶも、更に銃撃の音が続き、すっ飛んできた手鎌が管理人達の間を高速で通過した。
それは狼の肩を裂いて、通路の壁に突き刺さる。
『止めなきゃ…!!』
333が彼女の銃に被弾しつつも、名誉の羽を操って打ち込む。
赤頭巾の手鎌で頬を切ったらしい333の傷口は、すぐに塞がっていく。
「よっと」
次に飛んできた手鎌から726は、384とミカンたちを守るように巨大な鎌で弾き落とすと、そのまま振りかざしてぶん投げる。
張り合っているわけではない。
「クルミさん…!下がっていてください!」
817が杖を振りかざすと、床からは赤い光を放ちながら鎌の花と黒い爪が咲き誇った。
「メアリーもクルミしゃんと下がっておいで!」
キャロンはメアリーを背後に下げさせ、クルミもメアリーを庇うようにして、見守る。
「アネゴ!久しぶりだねぇ!!」
810が嬉しそうに飛びかかる。
背後をとってその背に乗り込むようにして切りつけた。
かなりの威力が見て取れるが、それでもひるむ様子は全くない。
555が不本意そうに剣を向ける。
「赤頭巾の傭兵を倒さないといけないとは
正直嫌やけど、しゃーない!行くで…!!」
一同が赤頭巾の傭兵を取り囲み、狼への進路を阻害した。
ミカンもすぐに応戦しようとするも、身体が思うように動かない。
思ったよりもダメージが溜まっていたらしかった。
「ミカンさん、無理しないで下さい…!」
384がミカンを介抱する側、726が立ち上がって赤頭巾に刃を向け、521も応戦する。
収容施設外、同じエリアというものがどういったことで成立するのか分からないが、星の音の効果を祈る他ない。
ましてや、アブノーマリティである、瀕死の狼にすらその効果を与えられるとは考えがたい。
防衛してはいるが、狼を目の前にした赤頭巾の傭兵の攻撃は常軌を逸する。
「このままでは、巻き込まれてしまうのも時間の問題…」
サイレンは見届けながら考えていた。
狼を守り、赤頭巾の傭兵と戦わずに済む方法を。
「―――皆さん…!赤頭巾の傭兵を拘束してください…!
このままでは、狼も我々ももたない…!」
彼の言葉を聞いて、真っ先に飛び付いて躍り出たのはキャロンだ。
「ネェエキィ!!!ぐふふふふ!!つーかまーえたァっ!!」
キャロンが赤頭巾の傭兵を背後から羽交い締めにした。
かなり腕力のあるはずの810がかなりの威力で殴っても決して怯まなかった赤頭巾の傭兵を、
欲求だけで見事に抑え込んでいる。
もちろん彼女は、グラインダーを使おうとはしない。このままキープしたそうだ。
サイレンの指示でもあったが、彼女の意思でもある。
『赤ずきんー!』
333が赤頭巾にすがりつくように抱きついた。
彼は先ほどからどんな打撃も平気で受け止め、彼女に呼びかけ続けていた。
「キャロンちゃん…!333ちゃん…!危ない…!
巻き込まれちゃうわ!!」
クルミが言いかけた時、低く呻いた赤頭巾は、未だに憎悪の宿敵を捉えて、銃口の照準を合わせている。
迷いがない。
クルミの忠告が聞こえても、巻き込まれることを恐れない333がその照準を反らさせようと必死に腕を掴む。しかし、華奢な彼ではまるで敵わない。
即座に身を滑り込ませるようにして、サイレンが立ちはだかる。
赤頭巾のその姿に釣り合うような覚悟でその銃弾を身に受けようとした時、
521がサイレンを庇うようにして銃弾を身に飲み込ませた。
「521さん…!」
「はは、…今キミがどのような表情で僕を見ているのか、
見られないのが残念だな」
521は、横目でサイレンを見ながら笑みを浮かべる。
その目は黒く、瞳は鋭く光っていた。
赤頭巾の傭兵が拘束されいるにも関わらず、力一杯手鎌を投げてきた。
それを完全に見きっている726は、切れ長の瞳を開きながら軽々と弾く。
金属の音が響き渡らせた手鎌は、天井につき刺さって落ちた。
「やれやれだぜー」
726はそう言いつつも、余裕がありそうだ。
いつものように口の端を持ち上げている。
ミカンは自身のダメージも省みず、
自分を連れてきた狼のぐったりした巨体を心配そうに見つめながら触れる。
「…星の音……」
普段、アブノーマリティが怖くてたまらない384が、震えながら狼に触れる。
この狼は、かつて、ミカンを飲み込み、管理人達を翻弄し、傷付けてきた。
それまでも、どんなに酷いことをしてきたか、想像したくはない。
赤頭巾の傭兵の怒りこそ、正当なものか、分からない。
それでも。
こうすることが、彼にとってできる最善の選択に感じられたのだ。
形を変えた星の音から、水色の優しい光があふれ出し、僅かに狼を包む。
「……!」
その時、狼は牙を食いしばって呻きながら上体を起こすと、突然収容時のコミカルな姿に戻った。
しかし、そのお腹は今もとてもやせ細っているままだ。
彼は、大きな丸い目を苦し紛れに瞑りながら口を開いた。
「……お前たち、先を急いでるんだろ?」
「…!!」
彼はくぐもった声で、ようやく言語のような声を口にする。
むしろ、言葉を口にするために、獣の姿を抑えているのだ。
「赤ずきんが狙っているのは、ご覧の通り俺なんだよ。
このままここで足止めを喰らわせるわけにはいかない。
…お嬢さん達をここまで連れてきた意味がないからな。」
「……」
本体がその様子を見つめていた。
その視線に気づいた狼は、本体にそっと牙を見せて微笑んだらしかった。
「お前ら本当は、赤ずきんのことも俺のことも、今鎮圧したくなんてないんだろう。
なんとなく見えていたぞ。そんな風に。まったく、俺はいつでも、このお嬢さんを飲み込めるって言うのにな。」
狼の怪しい言葉にも、誰も動じなかった。
ミカンはただ、赤スグリ色の瞳でまっすぐ狼を見つめていた。
優しく、強く、美しい眼差しで。
「オオカミさんはもう、ワタシを飲まないよ」
彼女の言葉に、狼は苦し紛れに「どうかな」と苦笑する。
「お嬢さんたちは行ってくれ。一緒に連れ出して欲しいけど、そういう役はガラじゃないな。
…俺は逃げる。赤ずきんからどこまでも逃げて見せるさ。
なんて言ったって、"俺は誰も傷付けることはない"からな!」
狼はそういってのけると、すでに身体を再び毛羽立たせて膨れ、獣の姿になっていった。
くぐもり始めた声で、384に"ありがとう"と伝えると、そのまま走り去っていった。
「待って…!」
ミカンは呼ぶも、大きくて多分悪い狼は既に人語を失った後だ。
そこから振り返るそぶりも見せずに、赤頭巾の前を横切って走っていった。
赤頭巾は宿敵が去るのを許すことができず、333とキャロンの腕を振りほどくと立ち上がった。
【邪魔しないで】
僅かに発した彼女の言葉を誰もが聞き取った。
蒼紅の闘いは終わらないのだろう。
彼らの背後を見送りながら、誰もが佇むしかなくなった。
「…あぁ……」
緊張感が解けたのか、先ほどまで狼に触れていたことを思い出した384が、
力なくその場で倒れ込みそうになった。
アブノーマリティからお礼の言葉も確かに聞き届けて、情報量でいっぱいになる。
726が急いで駆け寄って支える。
「わ、わたしは大丈夫だから…」
384は、目眩が楽になっていく中、心配そうにミカンを見つめた。
「行くぞ贋作、歩けるか…?」
しばらく息を飲んで狼と赤頭巾の背を見守っていた本体が、ミカンに手を差し伸べる。
彼女もまた静かに頷いて、彼の手を取ると他の管理人たちに見守られながら歩みを進めた。
*
「…提言、これらのシステムはすべて破損しています。
推奨、外部から復旧プログラムを新たに導入するか、制御室を放棄して脱出。」
ルシフェニアの淡々としたプログラム口調に、一同は顔を見合わせた。
「今、外部と通信が完了しました。
ここにはしばらくしたら、特殊部隊が到着します。
彼らは施設の破壊より、保護を優先してくれると約束してくれたようですが…」
259が言いつつ、顔を曇らせて続ける。
「なにぶんここの転送装置は破壊されていて、ポイントが見つからないそうで、到着までに持ち堪えるか、
アブノーマリティ脱走を防ぐために施設の隔壁を破壊しないよう、各自で脱出して欲しいとのことでした。
ウイルスについては、外部も知らなかったそうです…」
緊張感が高まる。
ここにはいられない。
「退路確保班に合流だね」
制御室の隅で『触れてはいけない』とおぼしき箱にもたれかかるようにして休んでいたウィリーが呟く。
その側でジョンが怒りに顔を歪ませている。
「しかし…アブノーマリティがこの施設ごと破壊するのも時間の問題です…。
どうしろっつうんだよクソが!!ふざけんな!!!」
彼は冷静を保とうとして、とうとう怒号交じりに叫んでいた。
「混乱するのは分かります。でも、259も皆さんを守るように努めます。
とにかく急ぎましょう。少しずつ向こうからも試練たちがあふれ出ているようです…。」
259が天国の切っ先を向けた先には、鉄くずと化した理解プロセスの残骸が広がっており、
その向こうから更に、何か大きなものが蠢いて見えた。
「…分かった…その通りにしよう。」
アルジャーノンはしばらく悔しそうに息をついていたが、やがて立ち上がった。
レストもその横でそっと立ち上がり、制御室を放棄すると認識したルシフェニアも続いた。
「……行きましょう」
心配そうに見守っていたラサの腕をソーニャが引く。
彼女たちもシステム復旧が不可能と知って、不安が晴れない。
「退路確保班が向かったのは宿舎の屋上。こっちの方が手っ取り早い道だ。
全員急げ」
レストは制御室を出ると、来た道でも、試練が湧きだす道でもない方向を指さす。
照明は不安定だ。さながら鼓動に合わせて血管が動くように、明滅する空間がずっと続いている。
とても不気味だ。
「皿面、大丈夫ですか?皆さんも行けますか?」
259が眠ったままのアンジェラを再び抱き上げると、皿面たちに声を掛けた。
一同はそっと頷くが、皿面は不安そうに後ろを振り返る。
「う…うん。けど、向こうで戦っててくれるミカンくんと本体くん…キャロルくんは大丈夫かなぁ…」
「キャロルなら心配いらん。奴はALEPH級だ。
恐らくクソ脚なんてとっくの間に潰して、496の奴らの支援にでも向かってるだろ」
1006が投げやりに応える。
しかし、その視線はまっすぐ通路を見据え、緊張感を含んだものだった。
彼らは制御室を放棄し、明滅する通路を急ぎ通る。
不安定な灯りの下は、歩くだけで酔いそうになる。
その途中、アルジャーノンがある部屋の前で足を止めた。
開かれたままの部屋は、暗く廊下と同じように激しく明滅している。
不安定な灯りの下、部屋の中ににわずかに見えるもの。
アルジャーノンはそれを見つめると躊躇なく入り込んだ。
―――ホドがいる。
ホドだけではない。
この訓練施設で見た数名のセフィラたちが、
拘束され、意識を失っている。
「どうしたのアルジャーノンくん…?」
皿面が驚いて部屋を覗き込むと、アルジャーノンはしゃがみこんで一室の機材に触れていた。
「キミ達は先に行っててくれ…!俺は、この仕事を終わらせてから行く…!!」
アルジャーノンは見向きもせず、ホドの拘束具を外そうとしている。
しかし、電子系の拘束具はエラーを起こし、思うように外れない。
皿面が首を傾げて部屋に入り、その光景に驚愕して口元を抑える。
未だ拘束されたまま、目を覚ましたホドが苦し紛れに呻いた。
「う…管理人さん…逃げてください…」
「キミは俺が助ける…!」
ホドの言いかけた言葉をかき消すように、アルジャーノンは拘束具を解除させた。
無事に外れた拘束具を確認し、アルジャーノンはホドに手を差し伸べる。
「キミ、歩けるかい?すぐにみんなと一緒に走ってくれ!
俺は他のセフィラも解放しに…」
「どうして…ですか…」
ホドの表情は今にも泣きそうになって、アルジャーノンを視界に捉えた。
未だに拘束された時のダメージが残っているのか、彼女は苦しそうに呟く。
「どうしてですか、この支部のAIは皆さんウイルス感染者です…私も。逃げても皆さんに迷惑がかかります。
私達のことは放っておいて…管理人さんたちだけで…逃げてください…」
彼女がそう言い終えるまで、アルジャーノンはしばらく彼女を見つめていたが、すぐ首を振ると立ち上がった。
「…馬鹿野郎!…俺は、俺のホドちゃんに教えてもらったことが沢山あるんだ!!
迷惑だろうがなんだろうが、助けずに放って逃げるわけにいかないんだ…!」
「管理人さ…ん…」
アルジャーノンはそれを伝えると歯を食いしばって、すぐにイェソドの拘束具を解除しに向かった。
「アルジャーノン…!!」
一度は通り過ぎた259が、眼を疑ってすぐさま引き返してきた。
「259くん…!キミも先に行っててくれ…!」
アルジャーノンは一瞥すると作業を急いだ。
しかし、259も部屋に入り、アンジェラを再び壁にもたれかからせると、その側の壁にもたれるように倒れていたマルクトの拘束具を解除し始める。
天国を弱い力加減で突き立てると、それはあっけなく壊れた。
「259くん…!!
皿面くんまで…」
アルジャーノンが驚いて見上げるも、259に次いで、皿面もすぐにティファレトの拘束を解こうと奮闘している。
彼が見渡すと、管理人たちはぞろぞろと部屋に入って、セフィラの解放に急いでいた。
「どうやら、ここが今の不安定なこの施設の心臓部みたいだね。
セフィラの数がやはり足りないようだけど…」
ウィリーがケセドを解放し終えて興味深そうに辺りを見渡した。
セフィラの数はやはり上層と中層のみで、下層のセフィラが見当たらない。ティファレトに至っては一人だ。
「大丈夫ですか?」
ラサがゲブラーを解放して声をかけるが、彼女は辛そうにしている。
腕力があるはずの彼女が力任せに拘束を抜け出せなかったということは、単なる拘束具ではないらしい。
ネツァクに至っては、すでに全てを諦めきったように微動だにしない。
ジョンが声をかけても、なんの反応もない。
「669、セフィラどもの解放を支援しろ。
俺はここで彼奴らの足止めをする。急げ」
「了解」
部屋の遠くから蠢く気配を察知したレストは、通路に立った。
彼女の指示に従い、ルシフェニアも部屋に歩みを進めると、セフィラの解放にかけつける。
それとすれ違い様に、1006が薙刀を構えて部屋の入口の左側に着いた。
「護衛は一室、視界は不安定な攻防戦。上等だ。
ここを通る化物を片っ端から切ってやるよ。
―――666、俺ひとりで充分だ」
レストも細身のユースティティアをすらりと手に取り、入り口の右側に着く。
「俺もそのつもりだ」
言った側、来た方向に僅かに『働き蜂』の姿が明滅する照明越しに向かってきているのが見えた。
気味が悪いまでに、数えきれないほど次々と列を成している。
反対側からは、大量の『掃除屋』が確実にこちらに進んできている。
咽そうなほどの嫌な血生臭さが漂う。

1006が薙刀を構えて走り込み、その細い四肢を旋回して斬りつけ薙ぎ倒す。
反射する血濡れた昆虫翅は、柔らかく光を反射する。
レストは反対側で、盗掘を続ける汚れた連中を閃光のように弾き飛ばした。
それ自体が、まるで宝石のように結晶化して砕ける。
「管理人さん…もうこれ以上は……ここにいては危険です。
私達の機体に残されたエネルギーを使って、一時的に出口を開きますから、皆さんで逃げて下さい」
解放されたホドが、真剣な表情で見つめる。
セフィラたちは拘束を解かれても、意識がはっきりしきらないのか、その表情は暗い。
「キミたちも一緒に逃げるんだよ!!ここに居ては危険なのは、キミたちも同じだろ?!
そうだ…修復プログラム…それさえあれば、アブノーマリティの収容システムや、電気制御もできるんだけど…」
アルジャーノンの言葉に、ティファレトは寂し気に首を横に振った。
「手紙に書いたでしょう?
アンジェラ様の様子がおかしくなった時から、私たちもすでにおかしくなっているのよ。
修復プログラムは外部からじゃないと効かないわ」
「貴様らをこんなことに巻き込んで、申し訳ないと思っている…
罪滅ぼしには到底及ばないが、時間稼ぎなら私がしよう。」
ゲブラーは、やはり申し訳なさそうな表情でこちらを見つめている。
その手にはミミックが握られていた。
ティファレトがすがるように彼女の足元に抱き着いた。
「…ゲブラー!!貴女が壊れちゃうわ…!」
「私達はもうとっくに壊れている」
ゲブラーの言葉にティファレトが静かに落胆する。
「このままだとどちらにしても、アブノーマリティが施設を破壊するのも時間の問題なんです。
みんなで逃げましょう!セフィラがウイルス感染していても、連れ出して治す方法はきっとあります!!!
ここで誰かが殺されるなんて、私が許しません!!!」
259が必死に説得するも、頷くセフィラは誰も居なかった。
「……」
「……」
「……ひとつだけ、方法があります。」
沈黙を破ったのは、イェソドだった。
「…ここの外側、裏に出た場所に、この施設の時間を制御するエネルギーのコアがあります。
今、エネルギーはほとんど奪われて不安定ですが、この施設と我々に残ったエネルギー全てを使って
この施設全体を停止させるんです。私たちがここに残ってコントロールし、……停止させます。
大丈夫です、その方法はかなり昔にホクマーから教えてもらっていましたから。」
「……!!」
彼らの驚愕するさまを見ても、イェソドは続ける。
「エネルギーの全てを停止につぎ込むため、出口をエネルギーで開くより、皆さんには壁を破壊して頂かなくてはいけません。
今恐らくこの異常事態で、コアにもエネルギー流出を防ぐ非常栓が自動的にされているはずです。
壁を破壊後、アブノーマリティ達が外部に抜け出す前に、速やかにコアに向かい、非常線を破壊…管理人の皆さんはそのまま脱出してください。
エネルギーが繋がったことを確認したら、即座に施設全体の時間を全停止させます。」
「でも…そんなことしたら…!!」
皿面が言いかける。
辺りには動揺の空気が漂った。
マルクトが寂し気に微笑む。
「宿舎の皆さんの荷物のことはごめんなさい。でも、さっき管理人さんの誰かが特殊部隊に連絡してくれたようですね。
事情を知っている解体チームが駆けつけた時、この施設を解体して皆さんの私物を回収してくれるはずです。」
「そうじゃなくて…!!そうじゃなくて、ここのセフィラのみんなは…!!」
彼が言いかけるも、セフィラ達は、少し翳った表情のまま、微笑んだ。
「俺たちは平気だよ。一時的に凍結するだけさ。
次に俺たちが目を覚ました時は、解体チームがこの施設を解体し、俺たちを回収した時。
俺たちも、アンジェラ様も、重要参考人として、おそらくまた拘束されるけどね。
何も消されるわけじゃない。さあ、行って、管理人…」
ケセドがそう言い終えると、ホドはアルジャーノンに微笑みかけた。
寂しくも、悲し気で、精いっぱい微笑んで見せているようだ。
「管理人さん、助けようとして下さって…―――いいえ、助けて下さって…ありがとうございます。」
しばらくの沈黙の後、アルジャーノンは静かに頷いた。
「分かった…あ、ありがとう、ホド…ちゃん…」
「皆さん、どうか停止解体まで、どうかご無事で…!!」
「……」
肩を震わせていたアルジャーノンは、259と皿面に肩を引かれるようにして、全員でその部屋を後にした。
セフィラが見守る中、彼らは上階層に繋がる階段へ向かう。
「ふ…」
項垂れたままのネツァクは、そっと息をついて笑ったらしかった。
明かりが明滅する長い通路を抜けて、彼らは突き当り暗い階段に差し掛かる。
階段を上った先は見覚えのある宿舎棟に繋がっていた。
とはいえ、非常電源に切り替わった今、明かりは乏しく、薄暗い。
途端、あどけない少女の笑い声がこだまして聞こえてきた。
「せ…先輩、後方貪欲ちゃんが来ます!!」
ラサは緊張感を持って告げると、
辺りが黄金色の魔方陣に眩しく照らされる。
「了解!!」
ウィリーはラエティティア撃ち、走り抜けたレストは壁を蹴りながら
向こう側へ渡ると、『貪欲の王』を背後から容赦なくとどめをさした。
すべて電子ロックされている宿舎の扉は、電圧が不安定な今、
開きそうにないため入室してやり過ごすのも不可能だ。
そのくせ収容施設と違って複雑な構造をしているため死角が多い。
遠くのものを狙うのは優位だが、どこから何が飛び出してくるか分からない。
「向こうにマッチガールを確認…!」
「了解…!!」
施設内では見慣れた脱走も、ここではまた形の違う緊張感が伴っていた。
途端、薄暗い視界の中、異常なまでの土煙が見慣れたワインレッドのカーペットから吹き上がり始めた。
「………みんな、ちょっと壁沿いにいてもらえるかい?」
ウィリーはそう静かに告げ、全員がそれに従った瞬間。
宿舎棟の吹き抜けを通して大きな口を開いた『永遠の食事』が現れた。
「こ…琥珀色の深夜…!!?」
「ひゃ…!!」
アルジャーノンが息を飲む。
皿面は飛び上がると壁にもたれかかって座り込んだ。
もとい、地から飛び出す振動はかなり大きく、立っていることは難しい。
それは土を舞い上げると、宿舎棟に響くほどの、がしゃりという大きな租借音を立て、
非常電源のわずかな明かりに照らされながら不気味につやつやと目を潤ませていた。
「ちょうどいい。殴れるものを探していたところだ」
「い、1006くん…?!」
1006はそう告げると、皿面の動揺も聞かずに柵を乗り越え吹き抜けへ着地すると走っていった。
「確かに、放置できません…!」
危惧した259も、さらりと柵を飛び越えると鎮圧に参戦する。
「――――――予測。『永遠の食事』から『食物連鎖』の排出まで、残りおよそ25秒。
それまでに退避してください。」
「芋虫の前に立たなければ関係ない、芋虫もろともここで潰す!」
ルシフェニアの言葉も置いて、1006は黒い薙刀を振り下ろした。
レストも細い柵の上にそっと立つと、
軽やかに降りながらユースティティアの切っ先で切りつけ始めた。
青い宝石の光が飛び散る。
「クッソ、無視したい…!!虫だけに…!!!」
ジョンは吐き捨てながらも、その悪態とは裏腹に魔法の弾丸を構えて狙いを定める。
片付かなければ、全員で先に進めないからだ。
「ふふ、そうだね」
ウィリーも相槌を打ちながら柵を乗り越えて至近距離から攻撃する。
薄暗い施設内に四人の赤と青と黒の閃光が美しく飛び交った。
「せ、先輩…向こうからは理解プロセスが来ました…!迎撃します…!!」
ラサがくちばしを構えた方向には、理解プロセスの大群が押し寄せてきていた。
「ラ、ラサちゃん、前に出すぎちゃ危険だ…!!」
アルジャーノンも迎撃に加わるため、鳥爪のガーデンフォークを掲げる。
とはいえ、迎撃は厳しい状態だ。
今鎮圧が得意な管理人たちは全員深夜の試練へと向かってしまっている。
「あ…あわわわ…」
皿面もあわててよろけながら立ち上がろうとするが、琥珀色の深夜を側にして手が震える。
――――――その時、前に出たのはソーニャだった。
彼女は皿面に微笑みかけ「大丈夫ですわ」と伝えると、少し離れた位置の部屋を確認する。
「もふぁにえる…!出てきて…!」
彼女がそう叫んだのと、理解プロセスがガトリングの腕を掲げたのは、同時だった。
恐怖が襲い来る、一瞬の動悸の高鳴り。
その瞬間、手前の部屋の扉がそのまま大きく外れ、人影が飛び出してきた。
人影は、外した扉を回転させて突っ込んでいく。
銃弾は鉄扉を盾に遮られ、妨げられた弾道は僅かな火花を散らす。
「あ…あなたは…?!」
ラサは驚愕してそれを見つめる。
人影は確かに人の姿をしていた。
しかし、人間とは言い難い、どこか無機質な雰囲気が漂っている。
青くうねった長髪に、ユースティティアを身に着けた人影は、鉄扉を理解プロセスに向けて投げつけると、
目の前を蹂躙し始めた。
マリオネットエージェント、もふぁにえる。
彼女はソーニャが自分の私物とともにこの施設に持ち込んでいた人形だった。
今では操りながらも両手が使えるため、そのままソーニャは崇高な誓いを向ける。
「大丈夫、彼女は味方ですわ」
しばらく驚愕して沈黙していたラサとアルジャーノンだったが、
状況を飲み込むとすぐにE.G.Oを構える。
「こ、これで勝つる…!?」
呂律が回らないわけではない。
アルジャーノンもそこに追撃を食らわせながら、いまだうかがい知れない薄暗い通路を見やる。
「"お人形"まで出してきて、雑魚に手間取ってんのか」
「ふふ、さすが1006さんたちは、おはやいですわね」
鎮圧を終えたらしい1006が、柵を飛び越えて前線に戻る。
レストはその間にも青い軌道を描いて、錆の軍勢を宝石の光で弾き飛ばしていた。
「だがキリがねぇのは何故だ…!!」
「どこかに親機が残っているのかもしれないね」
キレかかったジョンとウィリーも加勢して、前方から湧き続ける理解プロセスを焼き続ける。
それらは、切れ目がないように這い上がってきている。
その時、向こうから何か煌めく青い光を見た。
理解プロセスではない、何かが駆け上がってくる。
「あれは…ブランダー先輩…?!」
ラサは目を疑った。
向こうから現れたのは、変異したブランダーの姿だった。
その姿に彼らは目を疑う。
舞うように飛んだ彼は殺気立った瞳で睨み、理解プロセスを太刀ですっぱり切り捨て、
拳銃でその残骸もろとも吹き飛ばす。
その度に、ものすごい鉄のはじける音がして、焦げた匂いが広がった。
その背後からは、シャオも後衛フォローで応戦している。
辺りにはあっという間に火花を散らす鉄くずが積み上がり、道が開ける。
「ブランダー先輩!シャオ先輩!どうしてここに?」
理解プロセスたちがひれ伏すと、ラサは二人に駆け寄った。
「そっちも無事だったか。
ボクたちは一時的に班から離れて、今から退路確保班と合流するところだよ。
ラサ達こそ、どうしてここに…」
ブランダーが言いかけた時だった。
彼らの側で、見たこともない人影が彼の視界に映った。
ユースティティアを身に纏った突然参加の"味方"。
ブランダーは、再び殺気立った瞳で睨み、太刀を向ける。
「…お前、ニンギョウカ…?」
「……」
その殺気に、辺りは凍り付いた。
刃を突き付ける、変異したブランダーの姿があった。
「…よりによってブランダーくんが見つけてしまったようだね」
ウィリーがそっと呟く。それが何なのかを知っていても、彼に伝えてはいけない。
"動く人形"だという事を。
ソーニャは口を閉ざした。
彼女たちは事情を知らなくとも、
ブランダーがある種の条件のものに対しての殺意がこれまでも垣間見えたように、
動く無機物に対して強い憎悪を持つことは明白だった。
「……答えろ」
「……」
「……」
「……もっふぁ!」
ブランダーの殺気立った声に、しばらくの沈黙の後、人形はそう答えた。
明らかに許してくれなさそうなブランダーは太刀を振り上げる。
やはり、こんなことで誤魔化されるわけはない。
「お待ちくださいブランダーさん…!!」
ソーニャの声に彼は少し留まるも、破壊を止める気はないようだ。
流れ続ける、瞳の青い光に照らされた黒い涙。
彼の憎悪は、彼女に向けたものでなくとも、ただならぬ理由のもと、尽きることのないものだった。
冷酷ながらも、悲しみが動力として彼を突き動かし続けている。
その時、彼らの間に入り込んだのは、水色の光だった。
「危険を察知。庇護します。」
「ルシフェニアさん…?!」
振り下ろされた冷酷な黒い太刀を身に受けたのは、階段を高速で駆け上がってきたルシフェニアだった。
彼の一撃を喰らい、おおきく衝撃に揺らぐも、膝をつきながら完全停止は免れた。
居合わせた全員が驚いている中、ルシフェニアはゆっくりと立ち上がる。
未だブランダーは冷ややかな目で見降ろしている。
無機物たちを。
「提言、管理人X-1069。破壊衝動を抑えられないのであれば、管理人X-669の破壊を推奨します。
しかし、事態は急を要します。管理人一同は退路確保班と合流し、この施設を脱出しなければなりません。
推奨、速やかに退路確保班と合流。」
ルシフェニアの言葉を終始睨みながら聞いていたブランダーは、自分の肩にすがりつく者を感じた。
見てみるとシャオが、ブランダーの顔を覗き込み、階段を指さしている。
「急ぐぞ」
レストが凛とした声で促す。
ブランダーは憎悪の対象を睨み、一瞥するとすぐに階段を駆け上がった。
照明が不安定なのは分かっていたものの、ここだけはやけに暗く、何も見えない。
「…!!」
「シャオ…!!!」
何かにつまづいたシャオが、軽やかな足取りを取られた。
「大丈夫ですか?!
こ、これは…蜘蛛の糸…?!」
ブランダーがシャオに手を貸す横、259が緊張を含んだ声で辺りを見渡す。
不安定な電圧の暗がりの中、灰色のゴムを幾重にも束ねたかのような繊維が、暗がりの階段に張り巡らされていた。
まさか、と管理人達が辺りを見渡した時、それはいた。
暗がりの中、赤く光る目をいくつもつけた塊は、こちらに気付くとゆっくりと下がってきた。
蜘蛛の糸が張り巡らされ、上階の階段の様子すらよく見えなくなっているため、どこから降りてきているのかは、正確には分からなかった。
その全貌すらうかがい知れない。
「母なる蜘蛛…!?冗談はやめてくれ…!
マダムは非脱走オブジェクトのは、ずだ、ろ…」
アルジャーノンは笑い飛ばそうとしたが、それが冗談ではないことは目の前の光景が何よりも語っていた。
「収容システムが不安定になっている今、こういったことも起こりえるんだね。
脱走している血の風呂や、銀河の子に会えたりするのかな?」
この状況下、ウィリーが何やら感心を示している。
「と、とにかく回り道しましょう。上への階段はもう一つありましたよね」
ソーニャはゆっくり後ろを振り向くも、辺りは暗がりでどこが前なのかよく分からなかった。
「気を付けて下さい…!子蜘蛛がいるかもしれません!」
「っ」
259が言ったものの、行った側からソーニャは足を止めた。
夥しい波。犇めく小さな子供たちが、薄暗くも見えた。
幸いまだ、踏まずに済んでいるが、引き返せない。眼下に世界を広げている。
子を失う辛さなら、苦しいほど知っていたつもりだった。
しかし、眼下に広がる無数の子たちに彼女は眩暈を覚える。
蜘蛛は捕らえた獲物を巣食い、子にする。それが生活だった。
「もろとも斬る」
1006が薙刀を向けようとしている。
しかし、本来非脱走オブジェクトであるものは鎮圧できるものなのか。
蜘蛛に捕らえられた者はすぐには死なない。
エネルギーが上昇するため、救出が禁じられているだけで、本来は救出可能ではある。
しかし、糸には神経毒がある上に、全員一度に捕らえられては詰む。
「敵意を検知しました。
推奨、速やかにこの場を退室。」
ルシフェニアが語るものの、どうやって退室したらいいものか
一同が考えを巡らせ、こちらに向けられた蜘蛛の関心がそれるのを待った。
一同は何も踏んでいないし、何も行動を起こしていないのに、
それは起こってしまった。
「きゃぁ!!!」
「・・・!!」
突然悲鳴が上がる。
「シャオくん…!!ソーニャくん…!!」
皿面が震えた声で叫ぶ先、シャオとソーニャが高く吊り下げられている光景があった。
鱗翅のように白い姿が揺れて見える。
「どうしようっ…どうしよう…」
「どうしようもこうしようも、今すぐ親玉を叩き斬る!!」
「待ってろシャオ…!!」
慌てふためく皿面を背に、1006とブランダーは殺気立って母なる蜘蛛の核を狙う。
大きく赤い無数の目が彼らを捉え、斬りつける刃の軌道を読む。
幾重もの繊維が彼らの周りに見え始めると、彼らもいち早くそれを破壊した。
しかし、それは終わりのないように、粘着質に彼らを狙って纏わりつこうとする。
ブランダーの放つ拳銃の閃光に、辺りの暗がりはフラッシュライトの如く照らされ
その一瞬で、無数の子どもたちの数が、先ほどまでの認知をはるかに上回っていたこと知る。
笑顔を失った259が、天国を一差しするも、あろうことかそれは確かな手ごたえを持って糸の塊に阻害された。
259をとらえようとした足を、レストが細身のジャスティティアで打ち止める。
収容中はTETHクラスであり、行動を間違えなければ、危険性はない。
しかし、それは収容されている場合の話である。
母なる蜘蛛は脱走して人を襲うことはまずない。ましてや子蜘蛛を踏んだわけでもない。
否、すでにこの状況下、夥しい子蜘蛛の数を思えば、知らずと踏んでいてもおかしくはない。
事故であろうとなんであろうと、母子の絆に他人の言い訳は通用しない。
いつのまにか、引き返そうとした階段の先すら、糸が巻き付き始めていた。
子蜘蛛が小さくも大量に糸を張り始めているようだ。
ウィリーがラエティティアを向けて母蜘蛛の足を遮りながら呟いた。
「鎮圧が可能とは思えないけどね…。
糸を切るなりして二人を救出して突破口を探した方が得策じゃないかな。
ねぇ、ジョンさん」
「…分かりました。糸を撃ちましょう。」
戦う彼らの背後で、息を凝らし照準を合わせていたジョンは、
直後、吊り下げられた糸だけを見事に魔弾で撃ち抜いた。
「了解」
撃ち落とされた二人をルシフェニアともふぁにえるがすばやく受け止める。
心配してかけつけたラサがすぐに二人の無事を確認し、絡まっている糸をほどこうと手を掛けた。
「ソーニャ先輩!!シャオ先輩!!」
「ラサさん貴女は触れてはだめ…!彼女の糸は毒性があります…!」
ソーニャは苦し紛れにラサをいさめながらも、シャオの糸をほどいている。
足は未だに拘束されたままで、上手く動けない。
ルシフェニアともふぁにえるもその解放を手伝うが、糸とは案外丈夫なもので、E.G.Oでなければ切れそうにない。
ラサは手元の黄昏が融合して備わったくちばしの銃剣を見たが、これで解放するためには、糸はあまりにも密着して巻き付きすぎている。
「っ!!」
ラサは警告を無視してソーニャの足に纏わりついていた糸に手をほどき始めた。
これは炎症を起こすタイプのものだということは、今の彼女にとってどうでもいいことのように。
「ラサさん…!」
ソーニャはしばらく驚いてそれを見ていたが、今の自分に説得力がないことに気付く。
後輩に心配をかけてしまった。それが一度や二度ではない。
ソーニャもすぐにシャオの糸をほどいた。
手袋越しに明らかに少しずつ感覚異常があるのを思うと、素手で触れた時の影響が心配でならない。
「ほどけました…!あたし加勢に行ってきます…!!」
ラサの希望を持った声に、ソーニャは言葉を失い、ただその後姿を見つめるしかできなかった。
「…ラサさん、退路確保をしてもらえるかい?」
ウィリーは、ラエティティアを母なる蜘蛛に向けたまま、加勢に来たラサに気付く。
鎮圧は望めないことに確信を持っていた。彼が撃って阻害しているのも、鎮圧中の管理人達を捕えようと延びてくる糸ばかりだ。
「了解ですっ!」
ラサは、やや違和感の走る手でくちばしの引き金に手を掛けると、
引き返そうとした道に、新たに重なり始めていた網にくちばしを撃ち込んだ。
黄昏色のマズルフラッシュは、あたりに光をもたらすように、大きな口を開く。
暗くなり始めていた階段にわずかに光が見えると、ラサは銃口を下ろした。
その足元には、未だ蜘蛛の群れが列を成し、踏まずに越えるには灯りも乏しい。
しかし、ここを越えなければならない。
開いた口には、新たに糸が掛かり始めようとしていた。
「先輩!!退路確保できました…!蜘蛛ちゃんたちを跨いで、一度退避しましょう!!!」
「推奨、できるだけ一度に全員で退避」
ラサとルシフェニアの言葉に、皿面とアルジャーノンとジョンは背後へと向かうが、未だに闘いは終わらない。
「…いや、殺す!!!」
1006は笑み交じりに即答し、ブランダーも同じく殺意と怒りを抑えられず、一頻りに黒曜の太刀を振るっている。
「ブラン、ダー……」
ルシフェニアの腕の中、シャオがわずかな意識できょうだいに解放されたばかりの手を伸ばした。
その時、退路から無数の白い花びらが舞うのが見えた。
美しく弱く発光して見える吹雪のようにそれは大量に押し寄せてくる。
「あ、あれ…!!」
突然の光景に、259が天国の手を止める。
蝶だ。
白い蝶の大群が押し寄せてくる。
「父様…!!!」
小さな声でシャオが叫ぶ。弱くもその声には希望が灯っている。
ラサが開いた突破口から姿を現したのは、死んだ蝶の葬儀だった。
蝶たちは幻想のように舞うと、蜘蛛の糸を通り過ぎるようにして錯乱させた。
無数の蝶たちがこれも定めと、文字通り身命を賭し辺りに弱々しい光が灯る。
新たに降りつつあった糸の幕に身を掛けて、阻害している。
それが安らかな眠りなのか、誰にも分からない。
ただ、美しく苦しい。
「あの、蝶の葬儀…助けてくれたの、か…?」
アルジャーノンが緊張を含んだ声で辺りを見渡した。
死んだ蝶の葬儀は、するりと階段の暗がりに身を進ませる。
シャオの虚無の暗い瞳に、光が映り込む。
「父様、助けに来てくださったのです。やっぱり父様は、父様なのです…」
彼がおぼつかない身体で、蝶の葬儀の頬、羽のかんばせに触れる。
"勘違いしないで頂きたい。私の役目は誰もをここから帰すことです。
私はあなたを守るためではなく、
あなたをあなたの父親の元に帰すために、力を貸しています。"
シャオはそれでも儚く微笑んだ。
道は大きく開かれ、僅かながらも灯った白い光は、辺りを照らしている。
子蜘蛛の道が今ならよく見える。
アルジャーノンは未だ緊張感に満ちた表情で、固唾を飲むと足を踏み出した。
「よ、よし、みんな行こう…!!ラサちゃんが開けた突破口が再び塞がれる前に…!!
ありがとう、蝶葬くん…!」
「う、うん!!ひゃ…ッ!!…ありがとう…」
皿面が時々肩に触れる白い蝶に怯えながらいそいそと死んだ蝶の葬儀の横を通り過ぎた。
その背後をジョンが魔法の弾丸を構えて警戒しながら、慎重についていく。
「やだ!!離せ!!またこのパターンかよ!!」
未だに攻撃を止めなかった1006を、259が力任せに抱きかかえて出口へと走る。
その隣には、レストに静止させられたブランダーが、ようやく正気を取り戻してシャオの元へと戻った。
もふぁにえるがソーニャを抱え、その後にラサと、背後を警戒しながらウィリーも続く。
ルシフェニアの腕の中、シャオはそっと遠くの父親に細い手指を伸ばし、黒いひとひらの蝶を彼の肩に留めた。
「……また、どこかで…」
遠くなっていく暗い階段の入り口を、シャオはずっと見つめていた。
一同は反対側の非常用階段へ向かう。
その時、吹き抜けの下に、マッチガールが歩いてくるのが見えた。
「マッチガールちゃん…さっき鎮圧したばかりなのに…」
ラサが震える声で見下ろす。
「恐らく収容室が意味をなしていない。鎮圧は一時的な時間稼ぎにしかならん。急げ。」
レストは走りながら、下を確認せずに前を見据えた。
電気が不安定な中、未だに収容施設からはアブノーマリティ達が排出されているらしい。
*
「みなさん…!!」
「みんな…!」
向こう側から259の声がし、
通路を歩いていたクルミたちは振り返る。
乏しいランプが灯る通路は、一気に賑やかになった。
システム復旧班と、退路確保班が合流し、
残るはキャロルのみだ。
合流できたことに「良かった」、と言いかけた384は彼らの状態を見るが、無事には無事なものの、数名には怪我が見てとれ、二人の管理人は抱きかかえられている。
そして、見覚えのない人が一人混ざっている。
「あの…皆さんお怪我は、大丈夫ですか?
というか、こちらの方は…」
突然現れた一人のエージェントの姿があることに気付いて、彼らはどこなく身構えてしまう。
「えっと…助っ人です!」
ラサが言うと、そのエージェントはにっこり笑って頷いた。
脱出する人数が一人増えたにしても、
一人足りない。
「キャロルさんは大丈夫でしょうか?」
817が心配そうに辺りを見渡したが、その心配を打ち砕くように1006が言い放つ。
「キャロなら足止めでもしてくれてんだろ。
心配はいらん。」
キャロルの桁違いの強さを目の当たりにしてきた管理人たちにとっては、それは納得に足るものだった。
「―――……みんな、…ちょっと良いかな。
ここを脱出してから手を貸して欲しいことがあるんだけど…。」
アルジャーノンは、心苦しさをひた隠しながら、そっと静かな声で告げた。
*
クルミが先導して一同が進んだ先は、屋上に続く階段だ。
普段電気が並んだ明るい廊下も、今では非常用電源の電気に変わっており、それもところどころ消えている。
ある程度の位置まで登ると宿舎のエリアは途切れ、ただ階段と空間の開けた場所に出た。
広い踊り場といったあたりのところである。
辺りは静かそうな印象を受けたが、何か異様な声がしていた。
『クルミ…!危ない…!!!』
「…!」
やや前列のほうで先導していたクルミは、その踊場へ登り詰めたところで333に思い切り腕を引かれる。
危うく転びかけたのを817が支えると、壁に白い棘状の骨のようなものが突き刺さっていたのが確認できた。
あまりにも早く、目で追えなかったため、壁から突き出したかのような錯覚を覚える。
「これは…」
クルミを未だ支えたままの817が壁を見やってつぶやく。
壁とは反対側の向こうに、蠢く巨大な人影がある。
皮膚を剥いだような赤い裸体は、僅かな照明にぬらりと生々しく反射している。
こちらにすぐに気付いたそれは、大粒の目を輝かせて非友好的に迫りつつあった。
ほぼ顔面になる大きく開いた口が湛えているのは、笑顔ではない。
かつて誰かの笑顔であったことは違いない。
―――否、笑顔だったろうか。
何もない。
そこから垂れる臓物は、彼の動きに連動して揺れる。まるでそれが舌べらのようである。
回復促進ガスはない。
一部管理人は手負い。
全滅もあり得る。
彼の目前を、一同の一斉移動をしたところで、リスクは大きくなる。
黄昏で強化されたE.G.Oとはいえ、それさえも厳しい状況ではあった。
「――――――――――…!!!」
384やジョンがひきつった声で叫びそうなのを背後に、
皿面はとうとう緊張が頂点に達して膝から崩れて落ちてしまった。
倒れる彼を259が受け止める。
「…ご、ごめんねぇ…」
今対応できる管理人は大きく限られる。
いくつもの制約の中、彼を打ち倒すか、興味が逸れるまで一度、
最後の階段を前に引き返すかにかかっていた。
しかし、そのような体力も余力も、全員に残ってはいない。
「う…うそでしょ…」
384は戦意を失っており、泣きそうな声で震えた。
外見的な恐怖だけではない。
「お部屋に帰してあげるまで…!!」
810が飛び出し、ユースティティアを振りかぶって上から激突した。
黄昏のジャスティティアは黒い軌道を描いて、『何もない』の腹を滑る。
人語に近い音を発した『何もない』は、棍棒状の腕を振り下ろし、
810に打撃を与えるが、彼女は喰らいながらも退こうとはしない。
「810!!攻撃を避けることを優先してください!!これは持久戦ではなく消耗戦です…!!」
後方から攻撃していた817が黄昏のケーリュケイオンを振りかざして叫ぶ。
微かな動揺で翼が揺れる。
星の音を装備した384が傍にいるとはいえ、普段の収容施設のように迂闊にダメージを食らい続ければ危険だ。
『とげとげが来るぞ!!』
何もないがこちらに細く長い指をかざすと、いち早く徴候に気付いた333が注意を呼び掛けた。
ソーニャを抱えたもふぁにえるや、シャオを抱えたルシフェニア、
手負いの管理人達は退避を始めるが、少し間に合わない。
「……!!皿面さん…!!」
間に合わないと思った皿面がすぐに手元のブラックスワンを恐る恐る広げた。
尋常でないほどの恐怖心を漂わせ、震える手で傘を握って祈る。
どんな攻撃も反射するのは『何もない』の放った棘も例外ではない。
しかし、跳ね返った棘は『何もない』に突き刺さると、飲み込むようにして、別の個所から生えるように再生する。
ありとあらゆる物理攻撃は通じない。
そして、皿面もまたこの状況下でそれを掲げ続けることができそうにもない。
確実に管理人たちの身を守った行動とは裏腹に、恐怖で泣いていた。
そんな震える彼の前を、何かが横切る。
259。

彼はは天国を地に突き立てると、
自分は武器を置いて身ひとつで飛び込んだ。
黄昏によって強化された天国は赤黒く、黒の森のひと枝のようにも見えたが、
その時そこに蓄えられたいくつもの瞳や鎖、
そして259本人もその時、一瞬だけうっすらと柔らかな美しい金色に光を放って見えた。
「259さん…!」
パチパチと、枝を割るような音や、果実を潰すような音がして、
床を割り、せり出してきたものは、天国の赤い枝だ。
ゆったりとしながらも、樹木と言うには圧倒的なスピードで成長していく。
非常電源の乏しい灯りの中。
それは血管に血液が張り巡らされていくように、植物のように枝を広げ伸ばして生い茂ると、
無数の艶やかな黄昏色の瞳を開く。
神秘的で、おぞましさを覚えながらも人を惹き付ける美しい光景だった。
さながら生垣の様だ。
彼の、背後を守ろうとする意志が、E.G.Oにそのような変化をもたらしているのだろうか。
「退避できる方は退避を…!戦える方は鎮圧行動をお願いします!!
259は『何もない』の片腕を抑えます…!!」
「僕はできるだけ彼の注意を引いてみるね」
ウィリーは、259の天国の垣根を楽しそうに見つめていたが、
軽やかに飛び越えると、前衛に特攻してラエティティアを構えた。
521もミミックを床に突き立てると、259と同様に身ひとつで入り込んだ。
黄昏に強化されたとはいえ、武器の属性は黄昏と違い変わらないのかもしれないが、
521は戦う以外の戦い方を知っている。
するりと身を滑らせるように駆け付けた彼は、
259とウィリーのに向く攻撃を自ら受けるようにして彼らを庇った。
『何もない』の斧がその肩を切り落としても、彼の表情は一点も揺らがない。
出血の代わりに黒い波が揺れる。
「521さん…!」
「ウィリーさんは放っておくと無茶しすぎる。それにキミは今も怪我持ちだろう。
盾は僕にさせてくれたらいい。―――どうせ僕は死ねないんだし」
彼は未だ溢れる黒い波に身を包みながら、『何もない』に片手で捕まる。
『かんりにんも平気だよ!』
次いで333が『何もない』の目前にまで歩み寄って黄昏の羽を撃ち込んだ。
振り下ろされた腕を333くるりと回ってかわすと、259もすかさずその腕を床へ蹴りつけて抑える。
皿面は圧倒されるように259の作った赤黒い垣根から見守っていた。
「―――推奨、速やかに安全地帯へ退避」
未だシャオを抱えたままのルシフェニアが皿面にそっと声をかける。
プログラム口調ながらも、心配と気遣いが垣間見える。
皿面は後ろ髪引かれるような気持で、彼の後ろについて下がった。
中には退避せずに固唾を飲んで見守っている管理人達もいた。
とりわけ1006はもどかしそうにしている。
「なにやってんだよそこ!遅い!!」
「1006先輩、後方から案山子が来てます!
怪我してる先輩たちが襲われる前に行きましょう!」
ラサの言葉を聞いて1006はスイッチを切り替えるように、薙刀を構えて向き直る。
「HEの雑魚か。つまらんが後衛がいねぇならちょうどいい。
俺一人であたるから、ラサ、お前は怪我人の介抱でもしてろ」
「はい!」
1006が素早く駆け抜けていくと、そこには案山子だけでなく、
数体のアブノーマリティや試練たちが見えた。
しばらく退屈しなさそうだ。
ラサが避難している管理人たちの方へ駆け寄ると
クルミは動けない管理人の側で彼らの状態を気にかけつつ、
固唾を飲んで1006の様子や、何もないの鎮圧を見守っていた。
ソーニャはまだ動けないらしくエージェントに抱えられたままだったが、
384の星の音の効果か先ほどよりは落ち着いてきているらしい。
ルシフェニアの腕の中のシャオも似た状態だったが未だ、少し寂しそうに来た道を振り返っている。
メアリーはキャロンに抱きかかえられるようにして、待機している。危険にはさらしたくないらしい。
加勢に行きたいと、もどかしそうにしているミカンを、本体は休むように言いつけていた。
その時、555が自らの鋭利な涙の剣を二本振りかざし、自分の身を貫かせた。
側に居た817がぎょっとする。
「なっ!!何やってるんですか555さん…!!」
「来たれ…!!絶望ちゃん…!!!」
817が叫ぶももう遅い。
555は自らの身を貫く儀式を続け、やがてこのフロアに女性のすすり泣きが聞こえ始めた。
地下収容施設を抜け出した一同だが、祝福はまだ残っていたらしい。
「…ふ、ふふふふ……」
555は、がっくりと項垂れながらも、涙の剣を自らに突き立て続ける。
やがて光に包まれて出現したのは、黒い涙を流しながら、無数の剣を浮遊させる女性、絶望の騎士だった。
「ま、まさか…自らのE.G.Oでパニックを誘発して、絶望の騎士を召喚し、
自らのE.G.Oでパニックから正気に戻るなんて…!!いえ、正気の沙汰ではありません…!!」

「いや、私は正気よ。今正気に戻った。絶望ちゃんを召喚し、共に戦う。最高やで…!!」
555は現れた絶望の騎士に忠誠を誓う姿勢を見せ、彼女の耳元で何か囁く。
…言葉が通じているのか、彼女はこちらに一切敵意を向けず、『何もない』に向かっていった。
817は驚愕しながら見守っている。
あまりにも突発的な行動で、むしろ尊敬の念を抱く。
これも黄昏によって強化されたE.G.Oの効果なのか、はたまた彼の忠誠心で繋がったものが成せる業なのか。
「…行きます」
サイレンはやや暗い口ぶりで黄昏の対価を振り上げた。
この施設の『何もない』が、どれだけ自分を気遣い、どれだけ自分を支えてくれていたか、
彼の中には今も残っている。
幻想などではない。
彼の中でその欠片が目の前の物に危険信号を発した時、自分に依れるものを考える。
ブランダーは先ほどから大きく飛び回り、狙いを定めて拳銃を放ち、
上空から黒曜の太刀でなぜて、『何もない』を翻弄している。
『何もない』の動きは読むことができれば、一撃たりとも喰らわずに済む。
レストは、完全に相手の動きを見切った上、
なおかつ前衛の隙間を狙って正確に無駄のない動きで刃先を撃ち込んだ。
赤い肌の上に、青く光る宝石の軌道が残る。
これだけの人数が寄ってたかっても、ジョンの魔弾は管理人を掠れず、的確なタイミングで隙をついている。
とはいえ、彼の内心はとにかく怒号でまみれていた。
259の天国によって作り上げられたバリケード越しとはいえ、棘のタイミングは見計らわねばならない故に、
慎重を要された。
慎重にやるのであれば長期戦を覚悟しなくてはならないが、
収容システムが破綻した今、いつ何が来るのかもわからない。
1006が後衛を一人でやっているが、テレポートしてくる奴らがいつここに来てもおかしくない。
『何もない』の腕を抑えつけている259は、確かに負った傷がすぐに再生されてはいるが、笑顔の気配が全くない表情は凍てついている。
ウィリーは、傷を気にすることなく未だに至近距離からラエティティアを連射している。521がさきほどから庇い続けてはいるが、いつ倒れてもおかしくない状況だ。
当の521は再生に時間がかかっている。辛うじて残っている口元からは僅かな笑みを浮かばせて。
サイレンはそれでも対価を振るい続け、攻撃を受けても緩やかな様は痛々しい。彼は警鐘をある程度無視して無理をしている。
810が包帯の血をさらににじませながら、先ほどの817の警告をすっかり忘れて、退くことを全くしない。
側では555が、絶望の騎士とともに無数の刃を突き付けるが、無論、彼も無傷などではない。自らが呼び出した絶望の騎士を全力で庇っているからだ。
アルジャーノンは全員の間合いを読んで合いの手を入れるように少しずつ武器を振り下ろしていたが、周りの状態に少しずつためらっているようだ。
彼らは皆、痛みがないわけではないはずだ。
726は大鎌を持っているとは思えないほどの躍動で、何もないの裂けた腸の口を蹴り、追撃を食らわせていたが、384が恐怖のあまり気絶してしまうと、すぐに彼の保護に戻った。
「384、一旦後方に下がるぞ」
「ま、待って726…
星の音の効果を少しでも皆さんに届けなくちゃ…ここで…」
ここで皆と立っていなければ。
384が苦し紛れにそう呟こうとしたが、とても平気には思えない。
必死で掴んでいた意識も、無理に身を削って持続させているように見えた。
726は大丈夫そうではない384だけでも、と、天国の垣根の向こう側へ抱えていく。
随分消耗が激しい。
『み、みんな!しっかりして!
あ!アルジャーノン…!危ないっ…わぷっ!』
アルジャーノンに斧を振り上げた『何もない』の間に333が滑り込む。
「333くん…!!」
『へ、平気だよ…!
セロハンテープでくっつけなきゃ…』
333が明らかに痛々しい姿になりながらも、すぐに前線に戻ろうとしている。
「333くんも無理はするんじゃない!キミも痛くないわけじゃないだろう…!!」
アルジャーノンがすぐに駆け寄るも、
333は相手を安心させようと傷の再生が完了しないままそっと微笑んで見せるのだった。
(このままじゃ…)
817が騒然とした、辺りを静かに見渡す。
『何もない』と自分たち管理人の誰かが先に倒れてしまうのか、全く見当がつかなかった。
彼女は知らずと、祈っていた。祈るしかなかった。

(こんな時…こんな時、あの方が居て下さったら……どうか…)
彼女の心が破裂しそうになった、その時だった。
ふわり、と彼女の背後から揺れる羽の感触を感じた。
自らが戴いている翼ではない。
もっと大きな、偉大な…――――――――――――
『…?』「何…!」「何が起こったの…!?」
辺りが光に包まれる。
否、それは光とは呼び難い。
しかし、一部の管理人には光として認識されたことは間違いない。
――――――――"汝ら、恐れることはない"
ひとつに、声が降った。
しかし、同時に本能的に聞いてはいけない声のような気もした。
降り注いだ声は、空気を揺るがし、声が反響した音が聖歌の旋律を静かに奏で始めた。
人が歌っているのではないはずで、自然なる反響音であるはずなのに、
それはまるで声の主を賛美するように。
「こ、この声は…白夜ちゃん!!」
817が耳を疑って辺りを見渡した。しかしその姿はない。
代わりに、817の背後で翼が大きく揺れて大輪の花のように羽を散らしている。
「白夜の声…?!ええ…?!」
アルジャーノンが引き気味に音を拾う。
すごく胡散臭い。
この状況下で、災厄である『白夜』が"脱走"したのであれば状況は絶望的だった。
しかし817の少し安堵を垣間見せる表情から、"脱走"ではないということが分かる。
――――――――"汝らが苦痛を超えるとき、我は汝と共にある。
苦難が汝を囲うとき、そのものが苦痛で終ることのないように。
許しを得るものよ、恐れるな。新世界は、ここから遠からず。
苦痛を我に委ねよ、臆するな。時満ちて、汝は出会うだろう。"
意味が分からない。(本当に。)
壁を反響し、施設内に渡る言葉は、聞いてはいけないことのようにも思う。
このアブノーマリティの言葉は、人に魅了を掛けているものだからだ。
しかし、その不快不可解な言葉とは裏腹に、
次に部屋を照らした光が817を中心として周囲を通過した時、管理人たちの身に変化は訪れた。
「傷が…!!」「…!」
サイレンが自分の身に刻まれた傷が、みるみる内に塞がっていくことに気付いた。
奇跡、などとは思いたくはない。これは飽く迄もアブノーマリティの力であり、性質である。
とはいえ、全てのダメージが回復していくようだ。
「これは…とても興味深い現象だね。この光は本来使徒たちを回復させるためのものじゃないかい?
彼は果たして僕たちの味方なのかな?それとも…」
ウィリーは言いかけながらも再びラエティティアを構える。
「今は何でもいい…!とにかく行こう!!」
810の瞳には、先ほどに増して光が宿り始める。
不死身の管理人の身体の再生は著しく速度を上げ、元の状態に戻った。
『いつもより回復がはやかったぞー!』
333も元気に立ち上がり、管理人達は、E.G.Oを掲げる。回復した521も攻撃を体ではなく素手で受け止めた。
側では555も絶望の騎士に侍りながら、涙の剣を無数に振りかざしていた。
「行くよぉ!!絶望ちゃん…!!!」
ブランダーとレストは、何が起こったのか理解していたように、すぐに回復を受け入れていた。
これは転機と、一気に畳みかけるように『何もない』に太刀を振りかざした。
やがて、その振動が部屋を包み込んだ時。
『何もない』は大きく揺れ、静かに膝をつき、
巨体はうずくまるようにしてその肉の身から流れ出た繊維に小さく包まれていく。
鎮圧の完了。
しかしながらそれは、
収容システムが破綻している今、一時的にリスポーンに押し戻すことが叶ったに過ぎない。
「……訓練の間、お世話になりました。いつかどこかの収容室で、またお会いできることを願って。」
サイレンは膝を折るとそっと小さな肉の卵に触れる。
訓練の間、新しく生まれた知覚、頬の目から、何かが伝うのを、彼はそっと受け止めた。
「絶望ちゃん…」
555はそっと、ひざまづくと絶望の騎士に忠誠の意思を示した。
555は一瞬パニックになったことで、絶望の騎士の祝福はなくなっていたはずだが、
絶望の騎士は脱走行動としての攻撃は管理人たちには向けられず、
また、相変わらず黒い涙を流しながらも、もうすすり泣きは聞こえてこない。
ただ、静かに555を見据えている。
「絶望ちゃん、あなたに会えて良かった…」
絶望の騎士から声はしなかったが、彼らの間で何かは交わされていたのだろう。
555が微笑むと、静かな騎士は、逆光を放ちながら姿を消した。
煌めきだけがそよいで落ちる。
流れ星のように。
しばらくその場でじっとしていた彼だが「……ぬぉぉぉおおお絶望ちゃぁあん!!」
と、たまらなくなってむせび泣くように叫び回った。
「555さん…サイレンさん…」
817はそれぞれのそんな別れの様子をそっと見守っていた。
*
「みなさん…!!」
384が天国の垣根の向こうから来る管理人達に気付いて、ぱっと顔を上げる。
しかしその表情は疲弊していた。
鎮圧に向かった管理人たちが無事だったとはいえ、
彼はここで二度目の危険なアブノーマリティの声を聴いてしまったからだろう。
「良かった、皆さんもご無事で…」
259も安堵する。いつも通りの優しい笑顔だ。
とはいえ、脱出にはまだ一人合流できていない。
先ほどまで退屈そうに後衛を単独で担っていた1006は、
彼らの様子を見て一仕事終えたようにそっと息をついた。
「あとは、キャロか…まだ下で戦ってるのか…」
1006が遥か地上を見下ろして、彼女の気配を追った。
彼女の力にかかれば、ALEPH級アブノーマリティであろうとすぐに鎮圧が叶うはずだが、
この繰り返し排出されているアブノーマリティ達を鎮圧してくれているのかもしれない――――――
…誰もがそう思っていた時、
遠くから何か聞き覚えのある声で、聴き慣れない叫びが聞こえてきた。
――――"どこだああああああああ!!!姿を現わせ残念大福めがあ!!!捻りつぶしてくれるわ!!!!"
「キャロルさん…?!!」
817は目を疑った。
キャロルは、3メートル近い身体で浮かび上がりながら暴れまわっている。
「おい!!キャロ…!!」
1006が吹き抜けの辺りでキャロルを見つけると、柵越しに呼びかけた。
――――"シエロ…!無事であったか…!
それより白い毒ミジンコはどこにいった?奴め、コッパミジンコにしてくれる…!!"
「お前バリエーション豊富だな。そんなことより、全員でここを出る。」
不服そうに彼が説明するよりも、
退避していた管理人達の介抱をしていたクルミがすぐに駆け付けてきた。
259が立てた天国の生垣からは、退避していた管理人達が、辺りを見渡している。
「キャロルちゃん!良かった…無事だったのね。今すぐ一緒に来て!」
キャロルは、しばらく辺りを悔しそうに見まわしてから、黒い泡を纏って輝くと、元の姿に戻っていった。
口調も物静かな普段通りの彼女のものになる。
「…応、話はビヤーキーから聞いている。脱出してコアの非常栓を破壊に行くのだろう。
宜、817たちも無事であるな。
巨大なハイドネリウムピッキーがまた出てきたら私を呼ぶがいい。瞬きの間に狩り取って見せよう」
「…????巨大キノコですか?分かりました」
817は終始首を傾げながらも、全員が合流できたことに安心する。
こうして管理人一同がすべて合流することが叶ったのである。
*
「この先だわ…!」
屋上につながる最後の階段で、
クルミを中心に、一同は歩みを進めた。
何が来るか分からないのは同じだった。
非常電源に切り替わった時から、照明はどこも乏しいものだったが、
この階段の薄暗さは電気が不安定な今も変わらずに間接照明のような乏しいランプだけが続く。
誰も持つことのない屋上の鍵を、何故クルミが持っていたのかについて、
管理人たちは疑問を後回しにし、彼女を先頭に一同は屋上に出る。
眼前の宵闇に、雨は止んでいた。

ドーム状の鉄の柵越しに、澄んだ風がまとわりついてくる。
雨に洗われた夜の空気は、水晶のように透き通っていて冷たく、無数の星が久しく望める。
地に眩しく細胞のように寄り合っていた無人の夜景たちは、弱い光の中、儚く揺れながら眼下に広がっている。
そこら中雨に濡れたアスファルトにつややかに反射している光は、今や星たちの方かもしれないほどに。
足元で濡れた細い月が躍る。
「今って一体いつなの…?」
クルミが走りながらつぶやく。
TT2が無効になり、施設内も今では外部と同じ時間が流れている。
「現在は…訓練開始日の次の日の深夜のようです!
三日も経っていません…!」
時刻を確認した259の言葉に一同は驚く。
「分かっちゃいたけど、まだ二日目とはなぁ…」
アルジャーノンがため息混じりにこぼした。
あの数日間、訓練施設外で降り続いていたと思しき雨は、初日の雨を繰り返し見せていたのか。
二日目の深夜からは、このように晴れ渡っていたのだ。
「確か…あったわ!ここよ!」
彼女は鍵を取り出し、雨に濡れて冷ややかな鉄の柵に触れた。
錆びたような小さな金属音をたて、
ゆっくり開かれた扉。
何にも阻害されることのない、
透明な闇色の空の下が広がる。
――――――あの夜、ネツァクはまるで、
「この世界から解放されるために」
「闇に身を投じることができるように」
鍵を託してくれたようだった。
その手段が手元にあるだけで、
もう少しだけがんばることができる。
そして、彼女自身もそうだと思っていた。
しかしあの時暗く、また眼下の夜景に眩んで見えなかったものが、
長時間暗い施設を歩き回ったことによる暗順応によって
今認識することが叶い、やっと知ることができた。
わずか3メートルほど下には、
施設の屋根とも思しき足場があり、
分かり辛い位置には、
そこに至るまでのはしごがある。
とはいえ、足場はかなり右側に位置し、油断すれば、もしくはその気があれば、大地に身を投じるのも可能そうだった。
大地は遥か下にある。
見下ろすだけで足がすくみそうだ。
ネツァクは、最初からこの時のために鍵を託せる管理人を待っていたのか。
しかし彼にそんな演技ができるようには思えない。
或いは彼ならば、そんなことよりも本気で……――――。
「ここを降りるわよ!
ゆっくりで良いから落ち着いて気を付けて…!」
クルミは駆け巡る考察を一旦投げ捨て、管理人たちに手で促す。
管理人達は順次降りていく。
1006は梯子をガイドでしかないように、片手でするすると降りていった。
817も滑空するように駆け降り、
810と521は飛ぶように降りて着地し、
三人は次の管理人が安心して降りられるよう、サポートの姿勢を取った。
並んで259も降り、サポートできるように待機する。
本体も慎重にかけ降り、
後に降りるミカンの着地を見守った。
333はほとんど梯子に触れずに軽々と、ふわりと着地する。
キャロルも同じく、ほとんど梯子に触れずに軽々と着地した。
ジョンは周りにアブノーマリティが居なければ冷静に降りられるようだが、緊張感と疲労感が続いたために、よろけた肩を259が支える。
ウィリーは他の管理人たちを観察するように見ていたが、静かに降りると残った彼らの方を見上げる。
555とアルジャーノンは少し名残惜しそうに施設の方を見ていたが、
息を飲んで次々降りていく。
ラサは少し緊張しながら降りていたが、先に待つ先輩管理人たちの励ます声が聞こえる中、無事に降りた。
キャロンがふらつきながら降りた後、小柄なメアリーが降りるとそっと抱き締める。
726も跳躍するようにかけ降り、
続いてよろけて着地した384の手を取った。
シャオはブランダーに抱えられ、
ソーニャは人形エージェントに抱えられ、
はしごを使わずに軽々と降りた。
ルシフェニアとレストも、軽やかに降りていく。
着地地点にはブランダーの柔らかい青色の光や、ルシフェニアの優しい水色のライトが灯る。
やがて、残ったのはサイレンと、皿面、クルミだった。
「サイレンくんは…?」
皿面が不安そうにサイレンを見つめるが、サイレンは先に行くように手で促した。
「私は、皆さんが無事に到達したのを確認してから行きます。」
彼が時々気にしていた背後、屋上のアスファルトには、いつの間にか振動とともにヒビが走り始めていた。
その隙間から、僅かに漏れ出しているのは、緑色の蔦だった。
「急いで…!!」
クルミの声に、皿面はその蔦を確認し、怯えるように降りて行った。
震えている彼の着地を333と259が支えた。
「私は最後にこの柵の鍵を閉めるわ。
サイレンくん先に行って…!」
「…分かりました」
クルミは彼を促し、度々背後に気を配っていた。
蔦の成長は相変わらず早く、あっという間に屋上を埋め尽くそうとしている。
遥か、地下に捕らわれていたアブノーマリティが、陽光にさらされるときがきても、それ以上のことを叶えてやることはできない。

クルミは、自分もはしごに捕まると、片手で柵の扉を閉め、アブノーマリティが外に出ないよう丁寧に鍵をかける。
遠くの一角の柵に、すでに絡みつき始める蔦を見届けながら。
蔦を纏ってひしゃげ始める柵は囚人を囲い、
囚人は柵を握り外を羨望するように。
一同は歩みを進めて行く。
鉄板の道は雨に濡れていて、
とても良い足場とはいえない状態である。
その時、突風が吹いて、メアリーの小さな身体が持ち上がった。
「きゃぁ…!!!」
「メアリー…!!」
彼女を追いかけてキャロンも飛び掛かる。
一同がどきりと飛び上がった瞬間だった。
あたりからは悲鳴が漏れる。
「…!!」
更に彼女達を追って、無言で飛び込んだのは259だ。
「あんたも落ちてどうすんねん…!」
555が叫んだのを背後に、259は落下しながら彼女たちに腕を伸ばす。
一部の管理人たちが悲鳴混じりに青ざめていく中、キャロルは姿を消した。
(間に合う…!)
空中で259がメアリーを抱え込むことに成功し、キャロンの腕を掴む。
槍を壁に突き立てようとするも、
二人を庇いながらでは難しい。
その時だった。
突如、再び巨大化したキャロルが現れ、
落下する259とメアリーとキャロンを下から受け止めた。
浮遊している。
こちらの道の高さまで浮かび上がってきた彼らを見て「よかった」と安堵の声も出そうで出ないくらい、何が起こったのか理解できない管理人が大半だった。
巨大化したキャロルは、ユースティティアの包帯の隙間から青い瞳を覗かせ、こちらを見つめている。
「雨に濡れた道でそこまで向かうのは至難であろう。
我らに捕まるが良い」
キャロルが差し出した腕と鎖は、風にわずかにはためきながら光を歪曲させ、この世のものではないことを現しながらも、雨に濡れた足場よりは遥かに信頼できそうだった。
すぐに彼女の中から姿を現した生物たちも、管理人の力になろうと元気に溢れていた。
数人に分かれ、乗せられて、一同はコアへ向かう。
視界は先ほどまでの足場を下に臨み、澄んだ夜空の星々と、弱々しい無人の夜景の間を浮遊している。
それはそれで、足がすくむような光景のはずだが、管理人たちは不思議と恐れを忘れていた。
セフィラから聞いていたコアは、宿舎棟とは離れた位置にある、ドーム状の形をしていた核だった。
そこには無数の道や巨大な配線が繋がれ、さながら脳を象徴したかのようにも見える建造物だ。
今でも稼働しているように見えたが、エネルギーを正常に生産し、純化する術はもうない。
「これが…」
アルジャーノンがコアとその非常栓らしき設備を前にして息を飲んだ。
これを壊せば全てが停止する。
中で彼らの行動を待っているセフィラたちが、彼らもろとも停止させる。
「解説、配線の調節システムが破綻しているので、施設の動力に繋がる非常栓を破壊し、
直接エネルギーを物理的に接続します。」
「とにかく叩いて壊せ、か。」
ルシフェニアの言葉に、1006は不服そうに黄昏の薙刀を構える。
訓練最後の相手が静物では少し退屈なようだ。
「ありがとうございます、キャロル先輩!わんちゃん!」
ラサも軽やかに着地すると、自分を乗せてくれていた猟犬を撫で、先輩たちに続く。
キャロルは各々が無事に着地し、そこへ向かっていくのを見届ける。
彼女一人で破壊することも容易かったが、それは言わない。
危機的状況でないのなら、全員で収拾をつけるべきと判断したからだ。
今の彼らにとっても、
それは弱く脆い最後の壁に思える。
夜風を感じられるような開けた空の下、
E.G.Oを振るうのは不思議な感覚だった。
会話のない時間。
一点に集中する黙した時間。
色々な光が混ざり合って、蒸発現象を度々起こす。
施設の外側で、彼らが集めてきたエネルギーがわずかに残るコアに向けられている強烈な光。
そして、これだけの光の中にいながら、誰も目が一時的に眩むことはない。
破壊はなんともあっけなく、充分だった。
破壊された栓から、光が通過するのが見える。
「…来たれ。
皆で行く末を見届けるがよい」
管理人たちは、キャロルの言葉にそっとうなずき合い、再び肩を借りて浮遊しながらコアと訓練施設を見守った。
エネルギーが施設に到達後、
間もなく敷地全体が光に包まれ、
すべての音がかき消される。
衝撃。光。
そんな情景とは裏腹に広がる静寂。
施設全土を包み込んだ光は、やがて明滅し、消えた。
全てを停止させて。
屋上に蔦を張り巡らせたまま、空を見上げ祈るように静止したままの白雪姫の林檎。
屋内にわずかに見えるもの、進軍を続けたままの【規制済み】たち。
心配するように空を見つめる絶望の騎士。外に張り出した貪欲の王。
赤頭巾の傭兵の放った手鎌、霧となり逃げ回る大きくて多分悪い狼。
今破裂したばかりのマッチガール。
蝶の群れを導く、死んだ蝶の葬儀。
ランプを揺らそうとしている大鳥。
施設内の土埃。
今割れたガラス窓。
こぼれ落ちて行く水滴。
全て、そのまま停止している。
管理人達は、施設の外側からそれを見守った。
空は黎明を迎え、停止したままの施設を眩く照らし始めていた。
 アイスでも
ホットでも・*゜
アイスでも
ホットでも・*゜